『けーし風』第57号(新沖縄フォーラム刊行会議、2007/12)は、辺野古基地反対が過半数を占めた名護市民投票から10年が経つことを境に、民主主義のあり方を特集している。ところで、定期購読せず毎回本屋で買っているのだが、神保町の「書肆アクセス」がお店をたたんでしまったので、東京で置いているところが新宿の「模索舎」のみになってしまった。せめて三省堂の地方出版コーナーで取り扱ってもらえないものだろうか。(ついでに色々な本を物色するのが目的でもあるから、まあいいのだが。)

住民投票という方法は、地方自治のなかに位置を占めているが、その結果は拘束力のない「民意」となってしまっているようだ。
沖縄県名護市においても、辺野古基地反対という「民意」が示されたにも関わらず、その後すぐに名護市長は政府のプッシュにより、基地受け入れを表明して辞任するという考えられないことを行っている。それ以前に、住民投票直前に、防衛庁(現、防衛省)と那覇防衛施設局(現、沖縄防衛局)が、職員を動員して賛成票を集めるという露骨な策に出ている。つまり、政府自らが住民投票という手段を否定してかかっていたわけだ。
山口県岩国市でも、米軍機の岩国基地への移転に関して住民投票を行い(2006年)、やはり反対票が圧倒的多数という結果になっている。それにも関わらず、市議会では、容認を求める議員たちの圧力により、つい先日、市長が辞任に追い込まれている。これには、「米軍機移転に容認しないなら補助金を出さない」という政府の策が直接的に効いている。これも、住民投票による「民意」と議会とのねじれがある。民意を反映しない議会制民主主義とはなんなのか。
沖縄の北部振興策と同様、多額の補助金は基地受け入れとセットということが前提になっているわけである。ロジックとしては、「基地負担をしてもらっているのでそれに見合う補助金を渡す」ではなく、カネ依存体質にしておいて「受け入れないならもう麻薬(=カネ)は渡さない」ということになる。
故・小田実が繰り返し指摘していたように、民主主義イコール多数決主義ではなく、市民はさまざまな形で自らの意思を表明していき(集会も意見書もデモもあり、住民投票もそのひとつだろう)、それらをなるべく反映させていくというカオスが、そこにはなければならない。この、当たり前の話が、多くの場所で成立していないのだろう。これを許してしまう社会は何か。
『けーし風』の座談会では、真喜志好一氏(建築家・ジュゴン環境アセスメント監視団)、新城和博氏(ボーダーインク・編集者)、平良識子氏(那覇市議)、内海正三氏(沖縄環境ネットワーク)が、その点について多くの指摘をしている。
○少数者(辺野古近くで直接被害を被る市民)の意見が、多数決という手段で否定される。
○戦後教育では、徹底的に話し合うことや少数者の権利を無視してはいけないことが欠落している。その結果、アイヌ、沖縄、在日朝鮮人、ニューカマーの人々の意見が軽視されている。
○その構図は、少数者(沖縄、名護市、辺野古)の意思を多数(政府の方針)が抑圧しているという現状にもそのまま当てはまる。
○住民投票は、市民の自己決定権としてもっと然るべき位置を与えられるべきではないか。
○情報を市民に隠すという手法も、その精神からかけ離れている。(辺野古について言えば、公明正大にアセスを行わないこと、陸上を飛行すること、配備するのは危険性の指摘されているヘリ・オスプレイであること、など)
○多数決という最大多数の最大幸福ではなく、切り捨てられた少数者に思いを馳せる共生の思想こそが大事にされるべきだ。
辺野古での本来成立しえない環境アセスのプロセスについては、桜井国俊氏(沖縄大学学長)が、これまでの問題点を整理している。そのなかで、今回のような環境アセス法破壊がまかり通ってしまっては、恐るべき前例になってしまうことへの危機感をアピールしているのが印象的だ。また、「方法書」を再作成せよとした沖縄県環境影響評価審査会の意見が、極めて真っ当であることも明言されている。(それにも関わらず、沖縄県知事が、トーンダウンした意見を出すにとどまったことは、記憶に残しておくべきことだろう。)
連載の「佐喜真美術館だより」では、普天間基地から一部返還された土地に建てたという意義のあるこの美術館の目玉である、丸木夫妻の『沖縄戦の図』に関する記事を書いている。恐るべき訴求力をもつこの絵をもってさえ、過去の体験を内部化できない人が増えていることを嘆いている。
この年末に、佐喜真美術館(設計は上述の真喜志氏)をはじめて訪れ、『沖縄戦の図』の連作を鑑賞した。館長のご説明も聴くことができた。極限状況に追いやられ、爆弾が雨あられとふって死体が肉片と化した中、自分の家族に手をかけるという悲劇、いわゆる「集団自決」。じっと観ていて、ごくごく一部でもその事実が自分のなかに入ってくるとたまらない気持ちになる。
絵の左下には、「沖縄戦の図/恥ずかしめを受けぬ前に死ね/手りゅうだんを下さい/鎌や鍬やカミソリでやれ/親は子を 夫は妻を/若者はとしよりを/エメラルドの海は紅に/集団自決とは/手を下さない虐殺である」という丸木夫妻の言葉がある。


丸木位里・丸木俊・水上勉『鎮魂の道 原爆・水俣・沖縄』(岩波書店、1984年)より、丸木夫妻『沖縄戦の図』
●『けーし風』読者の集い(関東) 2008/1/19(土)14時~@神保町区民館




















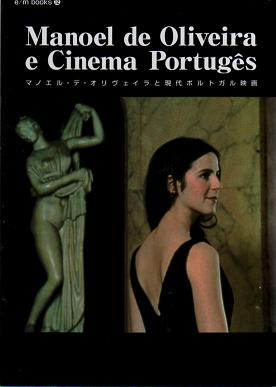

 =====
=====



















 =====
=====















