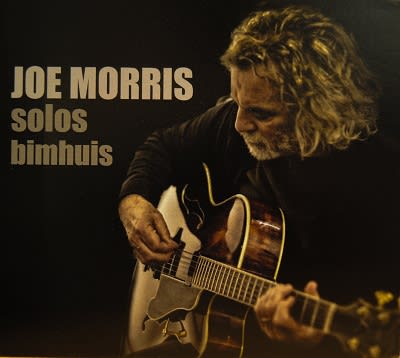5回目のウランバートル。

■ イフ・モンゴリア(ビアガーデン)
結構暑く、みんな外のテラスに出ている。しかも1リットルのジョッキ(それをストローで飲む女性もいる)。わたしは根性がないので500ミリリットル。もう夏至前夜、ようやく夜10時半ころになって薄暗くなってきた。

■ レインボウ(フローズンヨーグルト)
ソウル通りに新しい店ができていた。夜遅くまで開いていて、つい食べてしまう。シーバックソーン味はとても旨かった。

■ オリエンタル・トレジャー(台湾料理)
旨いタイ料理店があると聞いて行ってみるとなんだか様子がヘン。タイではなく台湾だった。味はふつう。
なお、隣には、実に旨いインド料理店デリー・ダルバールがある。

■ ナーダム(全般)
ウランバートルにシャングリラ・ホテルができたばかりで、高くて泊まれないので、中のレストランで宴会をした。
ナーダムとはモンゴルを代表するお祭りで、今年は7月10日から。人によっては田舎に戻って1か月近く休みを取る。この店の名前の下には「1年中」と書いてあり笑ってしまう。
気が向いてラム肉のハンバーガーを食べた。

■ 京泰飯店(中華料理)
再訪、ふつうの中華料理。太刀魚の揚げ物があったのでつい食べてしまった。ところで、太刀魚食い文化の広がりはずっと気になっている。韓国では一般的な魚だが、日本では西だけだと思う。

■ ピョンヤン(北朝鮮料理)
料理とサービスとパフォーマンスのあまりのハイクオリティぶりに感動して、ついに3回目。大喜びで観ていたら、手を引っ張られて踊る羽目になってしまった。ああ恥ずかしい。
参鶏湯に似ているが汁で煮込むのではなく蒸す料理があって、見るからに滋養の塊。体調がよくなるに違いない。


●参照
旨いウランバートル
旨いウランバートル その2