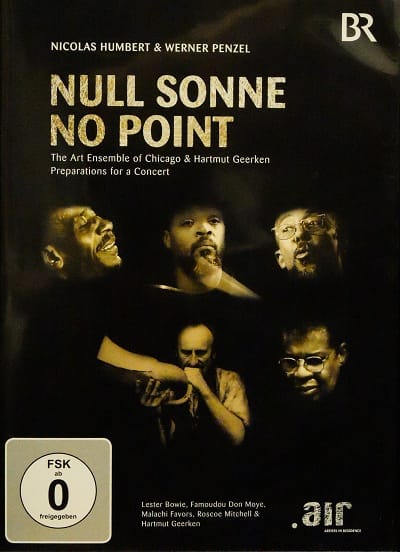吉祥寺のsound cafe dzumiが年末で店をたたんでしまう、しかも最後のイベントは「今井和雄 デレク・ベイリーを語る」だということで、足を運んだ(2015/12/26)。

狭い空間に30人くらいがぎゅうぎゅうに詰め合うように座った。これほど集まったのは、大友良英のライヴ(開店時)、バール・フィリップスのライヴ以来だとのことだった。
今井さんはたくさんのCDと試奏用のギターを持って現れ、音源を再生したり、デレク・ベイリーの奏法を弾いてみたりしながら、ベイリーの音楽について語った。横に座った店主の泉さんが、ときどきツッコミを入れる。場は大変盛り上がり、1時間延長して終わった。

テーマは、主に、アントン・ウェーベルンの12音技法がデレク・ベイリーに与えた影響、時代的な背景、そして、それを即興演奏に反映することを可能としたベイリーの確かな演奏の技量。
◆◆◆
曰く。
あるとき、今井さんはデレク・ベイリーが書いたスコアを入手した。それはのちに、ベイリーの『Pieces for Guiter 1966-67』のジャケット裏にも印刷されたものであり、ウェーベルンの12音技法からの影響が如実に表れたものだった。1オクターブ内の12音階による調性から逸脱すべく、12の音符を平等に扱い、さらにそこから複数の音列を作成し、組み合わせる技法である。
もとより、ベイリーはジャズやブルースが好きでなかったのだろう。ギャビン・ブライヤーズ、トニー・オクスレーと組んだ「Joseph Holbrooke」によるシングルカット盤『Joseph Holbrooke in rehearsal 1965』が残っているが、演奏している曲はなぜかジョン・コルトレーンの「Miles' Mode」。かれはアメリカのフリージャズとは異なる世界へと進んで行く。
ベイリーの技法は、無調や12音技法など調性からの逸脱に加え、ギターならではの特徴を活かしたものだった。隣同士の半音を多用し音を混ぜ、音楽の中心がわからなくなること。1オクターブ跳躍するメジャー7th。弦に触れながら弾くハーモニクス。これらによる跳躍の幅の広さ。「ジム・ホールが好きだ」というかれは、紛れもないギタリストであった(なお、ベイリーも、やはりホールを愛好した高柳昌行も、ホールも、ほぼ同世代である)。
調性とはロマンティックな世界でもあり、そこからの逸脱は、自ら規制を課して、その中で如何に即興を多様化するかというものであった。1960年代という時代には、多くの音楽家たちがそれを実践した。
●ジミー・ジュフリー『Free Fall』(1962年)。その前年からポール・ブレイを入れたトリオを組んだ。
●ガンサー・シュラー(ジョン・ルイス『Jazz Abstractions』(1961年)、エリック・ドルフィー『Vintage Dolphy』(1962-63年))。シュラーは12音技法をジャズに取り入れようとした。コードについてまるで理解していなかったオーネット・コールマンは、シュラーのもとに8か月通った。
●アルバート・アイラー『In Greenwich Village』(1967年)における「For John Coltrane」。背後の響きはまさにこのような雰囲気。アイラーの吹き方も、ペーター・ブロッツマンなどその後のヨーロッパ的な吹き方。管楽器により「ブヒッ」と吹くことで、技法的な跳躍とは異なる形で調性感から逸脱したのだった。
●『John Cage & David Tudor』(1965年)。
●MEV (Musica Elettronica Viva)(1966年~)。
●AMM『AMM Music 1966』(1966年)。今井さんは師匠の高柳昌行に貸したことがあるのだという。
●Nuova Consonanza。エンニオ・モリコーネも、映画音楽に進む前に所属し、作曲やトランペット演奏も行っていた。
●Terry Riley『In C』(1964年)。34のパターンに分け、各演奏者は次のパターンに移ってもよいという即興演奏。
●小杉武久。
高柳昌行は、日本にあってやはりフリージャズからのアプローチを取っていたものの、独自の即興に対するコンセプトを持っていた。氏は今井さんを含む弟子に基本的な技術のみを教え、音楽は自分で獲得するものだというスタンスであった。技術がなければ即興音楽も実現しにくい。日本において即興演奏といえば、規制のない思い付きのように捉えられるが、今井さんは、それは違うという。ベイリーもその地平に立っていた。
◆◆◆
残念ながら、sound cafe dzumiもこれで見納めだ。


●参照
今井和雄、2009年5月、入谷
齋藤徹+今井和雄『ORBIT ZERO』(2009年)
バール・フィリップス@歌舞伎町ナルシス(2012年)(今井和雄とのデュオ盤)
デレク・ベイリー晩年のソロ映像『Live at G's Club』、『All Thumbs』
ウィレム・ブロイカーが亡くなったので、デレク・ベイリー『Playing for Friends on 5th Street』を観る
犬童一心『メゾン・ド・ヒミコ』、田中泯+デレク・ベイリー『Mountain Stage』
デレク・ベイリー『New Sights, Old Sounds』、『Aida』
デレク・ベイリー+ジョン・ブッチャー+ジノ・ロベール『Scrutables』
デレク・ベイリーvs.サンプリング音源
デレク・ベイリーの『Standards』
『Improvised Music New York 1981』
1988年、ベルリンのセシル・テイラー
ペーター・コヴァルトのソロ、デュオ
ジャズ的写真集(6) 五海裕治『自由の意思』
トニー・ウィリアムスのメモ