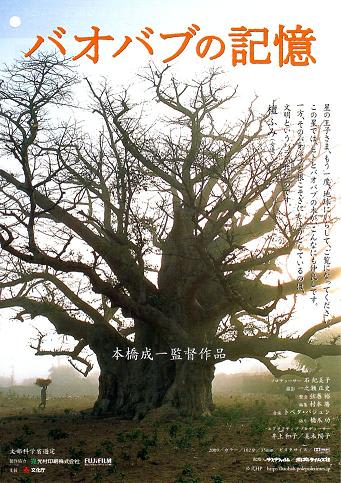J・G・バラードは随分と好きだった作家で、人間の内的なトリップと外的世界との関係性のようなもの(もちろん、そのそれらの破綻も含む)に、いつまでも偏執した存在だった。つい先日の4月、亡くなったとの報道があって、何となくいつまでも世界のどこかで妙な作品を書き続けるような印象を持っていたためか、哀しい心持になった。
最近はあまり読んでいなかったことも事実で、追悼の気持ちで、『楽園への疾走』(創元SF文庫、原著1994年)を読んだ。

タヒチ沖の島に、アホウドリなどの希少生物が棲息しているにも関わらず、フランスが軍事基地を造るために虐殺し、さらに核実験を行おうとしている。これに反対する女医が強烈ながら人を惹きつける人物であり、メディアも巻き込み、「ジュゴン号」という船で島に向かう。フランス軍を追い出した彼らは自給自足生活を始めるのだが、やがて、女医の信念に基づき、女性優位社会を構築する。そのため、男性たちは魚を捕り、子孫を残すことのみに奉仕させられ、挙句に女性たちに殺されはじめる。
この作品もまさにバラード。内的世界と外的世界のどちらなのかわからなくなるほど強靭なイメージが次から次へと繰り出され、どこに連れて行かれるのだろうという不安を感じながら読み続ける。この作家には、『残虐行為展覧会』(1970年)といい、『クラッシュ』(1973年)といい、そこまで書いたら「いけない」だろうと唖然としてしまうような狂気があり、しかもそれが揺るぎない。ということは、同じ人間が書くものであるから、強迫観念を昇華しているというわけである。禁忌がないため、しばしばモラルや常識の壁で防御している心の一部分をがりがりと掻きむしられ、抉られるような気分にさせられる。もちろん、どうしようもない残酷な犯罪小説などとは全く異なる位相にあるのであって、バラード作品には想像力の世界が無限に拡がっている。
ところで、バラードの小説『The Unlimited Dream Company』を、『限りない夢の仲間たち』ではなく、あえて『夢幻会社』という珍妙なタイトル(会社なんか出てこないのに)としてしまった前歴のある訳者がここでも翻訳している。読んでいて、ときどき違和感のある直訳風の訳が出てくると、読んでいてテンポが狂ってしまう。訳者があとがきでも触れていることだが、「exposure」がバラード独自の言葉という理由で、「ひどい火傷」などとせず「被爆」としている。確かに核実験の候補地であり、それを思わせる効果はあるのだろうが、まだ実験されていないはずの場所で「顔の被爆が・・・」と書かれても、わけがわからないだけだ。
バラードは、その作品群のなかでターニングポイントの1つであったに違いない傑作『太陽の帝国』以降、次のような長編小説を発表している。
太陽の帝国(1984年)
奇跡の大河(1987年)
殺す(1988年)
女たちのやさしさ(1991年)
楽園への疾走(1994年)
コカイン・ナイト(1996年)
スーパー・カンヌ(2000年)
Millenium People(2003年)※未邦訳
Kingdom Come(2006年)※未邦訳
『太陽の帝国』の続編『女たちのやさしさ』は日本語訳が待ちきれなくて英語で読んだため、たぶん、いい加減な理解をしている(タイミング悪く、読んでいる途中に岩波が日本語訳を出したので、買いはしたが本棚で眠っている)。それから『殺す』と本作は読んだが、あとはまだ読んでいない。亡くなってからまた読みはじめるのも奇妙だが、また順に読んでみたい。2008年には、『Miracles of Life』という自伝も出たようである。
J