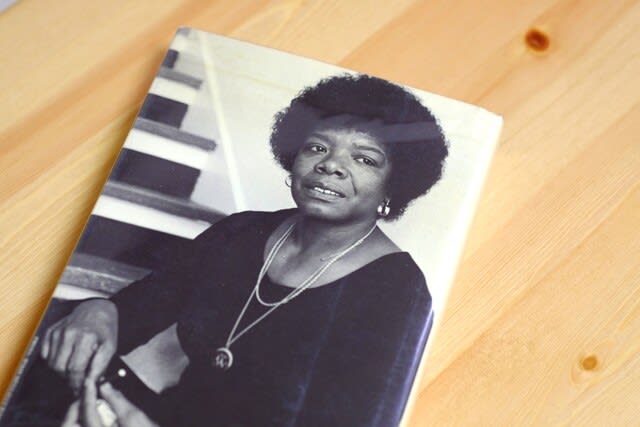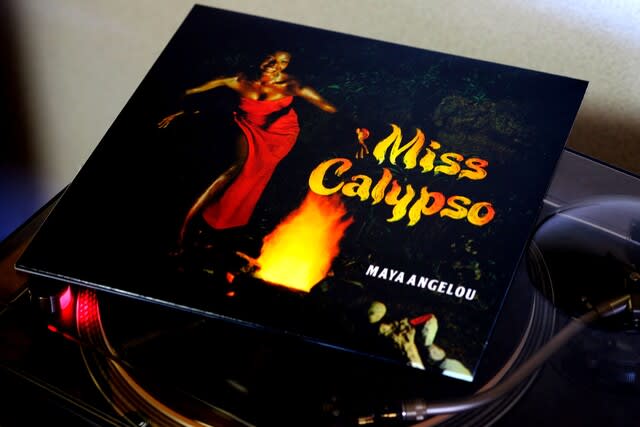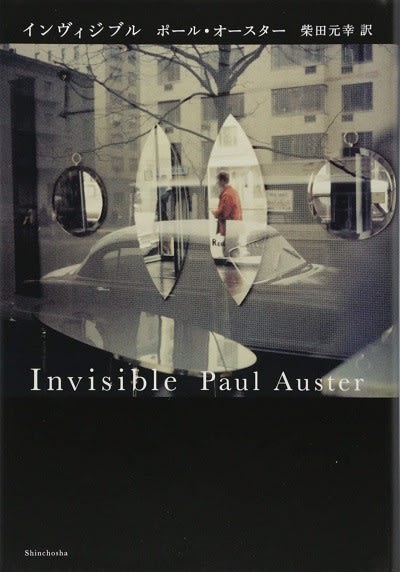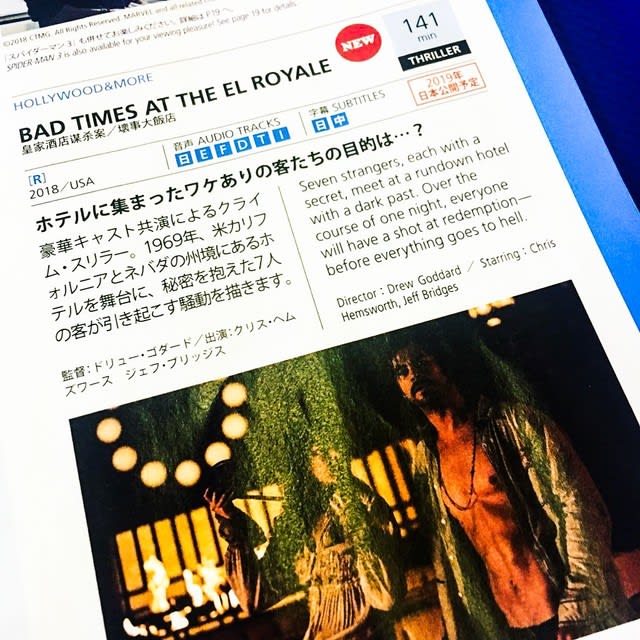トランプの大統領当選(2016年)の驚きは、都市部の視線で分析していては実態を捉えられないということも意味した。金成隆一『ルポ トランプ王国』(岩波新書、2017年)は錆びついた地域=ラストベルトの住民の声を拾い上げた傑作だった。大統領選が迫ってきて気になるので、その続編(岩波新書、2019年)と、辻浩平『トランプ再熱狂の正体』(新潮新書、2024年)を一読。生存に直結するオカネの問題、それからアイデンティティの問題。
辻さんの本によれば、かつてオバマはこんな発言をしたという。「民主党の人間は東海岸と西海岸に住み、リベラルで、カフェラテを飲み、ポリティカル・コレクトネスを守り、普通の人間と感覚がずれていると思われている」と。保守派がリベラルを揶揄するときには、カフェラテを飲む(latte-sipping)、テスラ(電気自動車)に乗る、寿司を食べる、ニューヨーク・タイムズを読んでいる、などの表現が使われる、と。日本における左右の断絶とどこが共通しどこが違うのか、やっぱり気になるところ。

●参照
金成隆一『記者、ラストベルトに住む』(2018年)
吉見俊哉『トランプのアメリカに住む』(2018年)
貴堂嘉之『移民国家アメリカの歴史』(2018年)
金成隆一『ルポ トランプ王国―もう一つのアメリカを行く』(2017年)
渡辺将人『アメリカ政治の壁』(2016年)
四方田犬彦『ニューヨークより不思議』(1987、2015年)
佐藤学さん講演「米国政治の内側から考えるTPP・集団的自衛権―オバマ政権のアジア政策とジレンマ」(2014年)
室謙二『非アメリカを生きる』(2012年)
成澤宗男『オバマの危険 新政権の隠された本性』を読む(2009年)
鎌田遵『ネイティブ・アメリカン』(2009年)
尾崎哲夫『英単語500でわかる現代アメリカ』(2008年)
吉見俊哉『親米と反米』(2007年)
上岡伸雄『ニューヨークを読む』(2004年)
亀井俊介『ニューヨーク』(2002年)