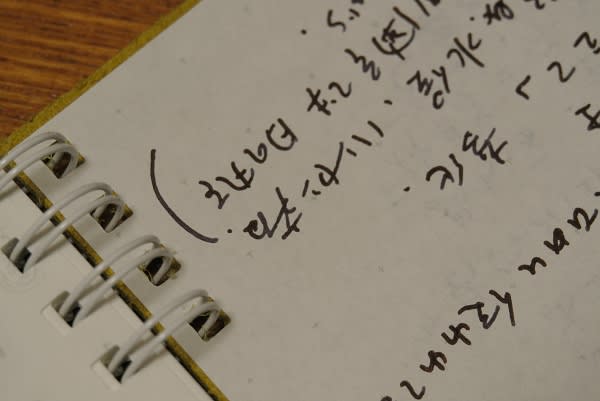沖縄の諸問題に詳しいOさんに貸していただいて、NHKのドキュメンタリーを2本。
■ 『沖縄 島言葉(しまくとぅば)の楽園』(ETV特集、2014/10/4)(>> リンク)
UNESCOは、琉球弧において、消滅の危機に瀕している言語グループが大きく6種類(国頭、沖縄、宮古、与那国、八重山、奄美)あるとして懸念を示している。沖縄本島の「ウチナーグチ」は全沖縄を代表するわけではなく、そのひとつに過ぎない。沖縄には800を超える言葉があるという。
8世紀以前に九州にあった言葉を源流として、近畿に流れた言葉が日本語となり、11世紀頃に沖縄に流れた言葉が「島言葉(しまくとぅば)」となったという。支配の言葉たる首里の言葉が公用語、しかし、琉球王国では地方の言葉を抑圧することはなかった。
番組には、沖縄本島の最北端にある奥(国頭村)や、那覇の栄町市場が登場する。
国頭村には20の集落があり、それぞれ言葉が微妙に異なっていた(往来も難しかったからだろうね)。そこで紹介される昔からの文化は面白い。イジュの樹皮から弱い毒を取り出し、それによって海の魚を獲る「ブレーザサ」。近代にいたり、機能を求め強い毒が使われるようになり、獲り過ぎや毒の影響が問題視されて「ブレーザサ」は言葉もろとも衰退した。また、2年に1回行われる「ビーンクイクイ」という祭は、豊作や長寿を祈り、集落の長老を桶に入れて練り歩くというもの。奥には沖縄最初の共同店もある(わたしは100周年のときに訪れたことがある)。また行きたくなる魅力がある。
栄町市場では、「庶民の言葉」である那覇の言葉を大事に残そうとする動きの紹介。確かに栄町には、たまに行くたびに何かの変化があって、商店街の活性化というだけにとどまらない面白さがある。
国連の人種差別撤廃委員会は、日本政府に対し、沖縄の先住民族を認めるよう勧告するとともに、島言葉での教育の必要性についても言及している。このことは、日本による沖縄支配の歴史の正当性を問うものでもある。
最後に、スコットランドの自治権拡大の紹介(島袋純さん)。スコットランドは18世紀にイギリスに統合されたが、1999年に大幅な自治権の獲得、特に教育に関する立法権の獲得に成功した(分権改革)。その後、ゲール語の復興と多言語社会への志向が強まっていった。2014年の独立国民投票は、イギリスに残るという結果となったが、島袋さんは、このプロセスはさらなる自治権の拡大につながるだろうとみる。
言葉は文化そのものであり、人間そのものでもある。これまで奪われてきた独自の言葉を取り戻そうとする動きには共感するところが大きかった。
■ 『狂気の戦場 ペリリュー ~"忘れられた島"の記録~』(NHKスペシャル、2014/8/13)(>> リンク)
太平洋・パラオ諸島の小島ペリリューは、太平洋戦争の中でもかなり異質な日米間の戦闘が行われた地である。米軍はフィリピン・レイテ島を攻めるための拠点として、ペリリューに海兵隊を派遣した。日本軍はやはり防衛の重要拠点として関東軍の精鋭を派遣した。
1944年9月、アメリカ海兵隊が上陸。当初は2-3日で制圧できるものと考えていたという。しかし、その直前に、日本軍の大本営は、戦争を長引かせるための持久戦を行うよう方針転換を行っていた。石灰岩でできた山には網目のようなトンネルが掘られ、日本軍にとって天然の要塞と化した。戦車の性能には大きな差があったが、米兵にとって、いつどこから攻撃されるかわからないという恐怖心は大きく、精神に異常をきたすものもあらわれた。
1944年10月、米軍(マッカーサー)はレイテ島を直接攻撃。ペリリューの戦略的な意義は失われたが、それでも、戦闘は継続された。米軍は130m届く火炎放射器や飛行機から投下するナパーム弾を投入し、日本軍のほぼ全員を殺戮した。一方、大部分の米兵も死傷した。異常な戦闘であった。
これが、その後、「本土防衛の捨て石」として展開される硫黄島や沖縄戦のはじまりであり、また、それらの場所では、火炎放射器やナパーム弾がより大規模に使われることとなった。
●参照
『海と山の恵み』 備瀬のサンゴ礁、奥間のヤードゥイ
島袋純さん講演会「"アイデンティティ"をめぐる戦い―沖縄知事選とその後の展望―」
城間ヨシさん、インターリュード、栄町市場
Leitz Elmarit 90mm/f2.8 で撮る栄町市場と大城美佐子
栄町市場ライヴ
栄町市場
米国撮影のフィルム『粟国島侵攻』、『海兵隊の作戦行動』