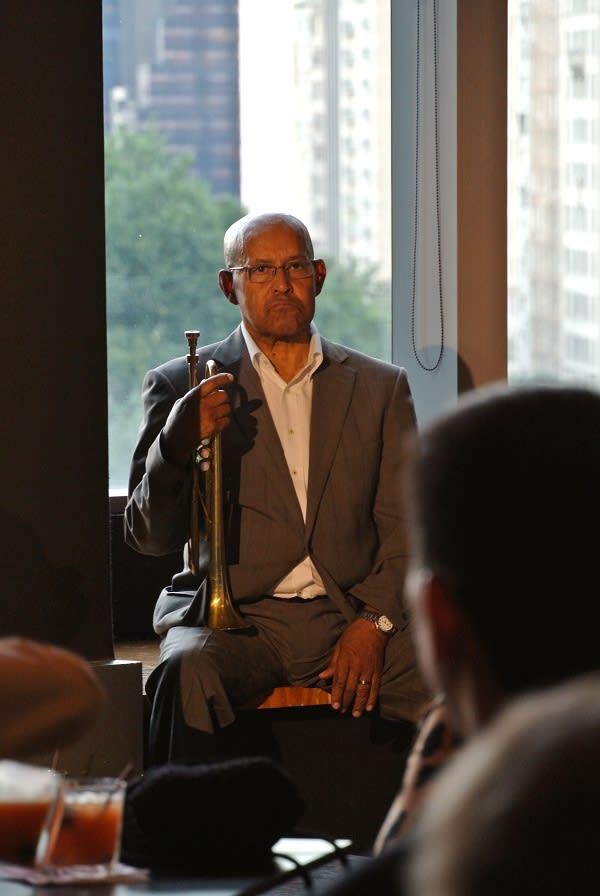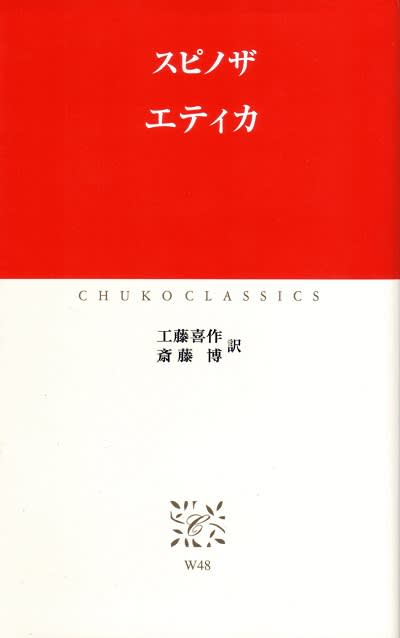イーストヴィレッジにある「The Stone」は、ジョン・ゾーンがディレクターをつとめる小屋。足を運んでみると、よくよく注意しないと通り過ぎてしまうような佇まいである。中には50脚くらいのパイプ椅子が置いてあり、飲みものなどはまったく出ない。

◆ Death Rattle
20時からのセッション。かなり楽しみにしていた。
Ingrid Laubrock (ts)
Mary Halvorson (g)
Kris Davis (p)
体感すると確かに格が違う。まるで3つの恒星が、互いの周りを高速で回り続ける三体問題である。
イングリッド・ラウブロックのサックスの音域がとても広い。ヘンな音もノイズも精力的に繰り出してくる。マウスピースを外して吹いたりもして。メアリー・ハルヴァーソンのギター音は、猛烈に立っていて、鼓膜と頭蓋を直撃する。そして、鋭く押したり忍び込んだりするクリス・デイヴィス。
終わった後にメアリーさんと少し話をした。今度来日だねと訊くと、ヴィザが果たして間に合うか?と不安そうな発言。とりあえず、アンソニー・ブラクストンと一緒に来てほしいと熱烈要望。







◆ Kris Davis' Capricorn Climber
22時からのセッション。目当てはマット・マネリである。
Mat Maneri (viola)
Ingrid Laubrock (ts)
Kris Davis (p)
Eivind Opsvik (b)
Tom Rainey (ds)
もう空調を止めた会場が暑くて酸欠状態、ぼんやりしながら聴く。しかし、さっきの三者パラレルのセッションとは異なり、主役はやはりマネリ。マネリのヴィオラとラウブロックのサックスとがつかず離れずシンクロし、大きな流れのようなものを作りだしていたからだ。
しかし、最後にはラウブロックがエキサイトして速いフレーズを吹き始め、マネリは明らかに困ったような顔をして追随していた。




●参照
イングリッド・ラウブロック(Anti-House)『Strong Place』
メアリー・ハルヴァーソン『Thumbscrew』http://blog.goo.ne.jp/sightsong/e/fbe3c7979d4d3c71d8a02864b21dda29
ウィーゼル・ウォルター+メアリー・ハルヴァーソン+ピーター・エヴァンス『Electric Fruit』
ウィーゼル・ウォルター+メアリー・ハルヴァーソン+ピーター・エヴァンス『Mechanical Malfunction』