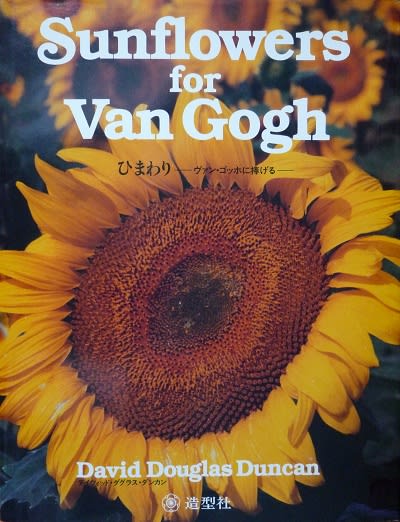ジョー・ヘンダーソンが「テナー・タイタン」などと再評価されたのはさほど古い話ではないと記憶しているが、ジョーヘンのテナーサックスの音は若い頃から最晩年まで変わっていないのであって、周りが変わったのは、ある時期からまとまった良いアルバムを出しはじめたことにもよるのだろう。『Lush Life / The Music of Billy Strayhorn』(Verve、1991年)もそんな盤のひとつで、昔ずいぶん気に入っていたこともあって、また中古盤で入手してしまった。

もう少し破天荒に突き破るところがあってほしいとも思うが、それなら70年代のMilestone時代のジョーヘンを聴けばよいのだ。ここでは、ステファン・スコット(ピアノ)、クリスチャン・マクブライド(ベース)、グレゴリー・ハッチンソン(ドラムス)、それから目玉としてウィントン・マルサリス(トランペット)と、当時の一級の若手を従えて、曲によって編成を変えながら、ビリー・ストレイホーンの音楽を愉しそうに演奏している。
この盤はグラミー賞を受賞していて、『Switch』(1993年9月)において、秋吉満ちるがジョーヘンに行ったインタビューでもそのことに触れている。
「―――この春、あなたがグラミー賞を受賞したことは記憶に新しいですね。
JH あれは私の人生の中で最も信じられない出来事のひとつだったよ。身体が浮き立つようなことだった。いまは少しほとぼりが覚めてきたが、受賞してから24時間は天にも昇る(クラウド・ナイン)心地だった。
―――ここに来る前に母(※秋吉敏子)に会ったのですが、『ラッシュ・ライフ』を褒めちぎっていました。他人のアルバムを褒めるなんて母にはとても珍しいことなんですが。
JH それは嬉しいね。あのアルバムを作ってからゆうに1年はたっていて、何度か聴き返したけれど、確かにとてもいいレコードだな(笑)。」
「Cloud Nine」という言葉は英語で「意気揚々」を意味するそうで、使ったことはない。いつか伝わるかどうか試しに使ってみたい(笑)。

ソニー・ロリンズが若い頃に『Worktime』(Prestige、1955年)に吹き込んだ印象が強い「Rain Check」では、ピアノレスのサックス・トリオ。「Lotus Blossom」では、ピアノのイントロからしっとりとしたデュオ。「A Flower Is A Lovesome Thing」では全員で演奏、このような綺麗にまとまった枠組内でウィントンが見せる実力は凄い。最後にうねうねとしたサックスソロで締める「Lush Life」も素晴らしい。どこを切ってもジョーヘンは枯れていて、このような組み合わせがちょうど良かったのだろうね。
中でも嬉しいのは、ドラムスとのデュオによる「Take The "A" Train」。ハッチンソンのドラムはハーレムに向かう列車を気取ったリズムを刻む。サックスとドラムスでのこの曲の演奏といえば、まず、ジミー・ライオンズ+アンドリュー・シリル『Something In Return』(Black Saint、1981年)を思い出す。改めて棚から出して聴いてみると、確かにフリーの雄ふたりによる色はあって、ライオンズの逸脱もシリルの叫びもあって、とても良い感じである。しかし、たまにチャーリー・パーカーのフレーズも聴こえたりして、意外にオーソドックスだなという発見もあった。
ジョーヘンにもこのくらいの破綻があっても・・・それなら70年代を。