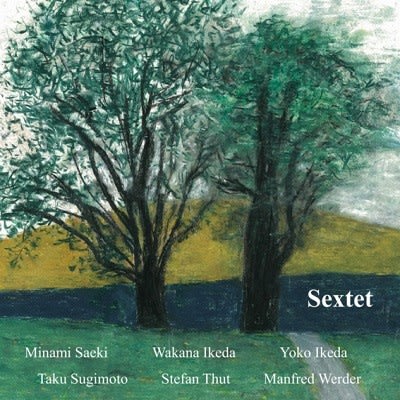仕事が終わってFBを覗いたら、近くでレイモンド・マクモーリンが吹いている。セカンド・セットに間に合いそう。そんなわけで、何年ぶりだろう、御茶ノ水のNARU(2019/1/28)。

Raymond McMorrin (ts)
Mayuko Katakura 片倉真由子 (p)
Takumi Ayawa 粟谷巧 (b)
Gene Jackson (ds)
Guest:
Satsuki Kusui 楠井五月 (b)
扉を開けたらレイモンドと女性がおしゃべりしている。何年か前まで近所のスタバでバイトしていた子だった。思いつきの行動には嬉しい出来事が付いてくる。
セカンドセットは「Punch」(オリジナル)、「Before Then」(ジーン・ジャクソン)、「In a Sentimental Mood」、「Milestones」(古い方の)。サードセットは、ザッカイ・カーティスのアレンジだという5拍子の「Inner Urge」(ジョー・ヘンダーソン)、「Evidence」、「My One and Only Love」、コルトレーンやファラオ・サンダースのイメージで作ったという「Spiritual Journey」(オリジナル)。
もちろんヘヴィ級にしてキメ技炸裂のジーン・ジャクソンは素晴らしいのだけれど、この日は、とにかく片倉さんのピアノに魅せられた。知的でエモーショナルなのに残らずどこかに去っていってしまう。深い深いジャズが本当に愉しそうだ。こちらも脳内がジャズ一色。
レイモンドのテナーは、毎回手作りで思考しながらソロを構築する、そのアプローチがとても好きである。良い隙間がその結果として生まれている。粟谷さんのベースがじわりじわりとサウンドを浮揚させるものだとして、モンクの「Evidence」でシットインした楠井さんのベースはもう少し高めの領域を滑空する感覚で、その違いが面白かった。
●レイモンド・マクモーリン
レイモンド・マクモーリン『All of A Sudden』(2018年)
レイモンド・マクモーリン+片倉真由子@小岩COCHI(2018年)
レイモンド・マクモーリン+山崎比呂志@なってるハウス(2017年)
レイモンド・マクモーリン+山崎比呂志@なってるハウス(2017年)
山崎比呂志 4 Spirits@新宿ピットイン(2017年)
レイモンド・マクモーリン@Body & Soul(JazzTokyo)(2016年)
レイモンド・マクモーリン@h.s.trash(2015年)
レイモンド・マクモーリン『RayMack』、ジョシュ・エヴァンス『Portrait』(2011、12年)
●片倉真由子
レイモンド・マクモーリン『All of A Sudden』(2018年)
レイモンド・マクモーリン+片倉真由子@小岩COCHI(2018年)
ジーン・ジャクソン・トリオ@Body & Soul(2018年)
北川潔『Turning Point』(2017年)
●ジーン・ジャクソン
レイモンド・マクモーリン『All of A Sudden』(2018年)
ジーン・ジャクソン・トリオ@Body & Soul(2018年)
ジーン・ジャクソン(Trio NuYorx)『Power of Love』(JazzTokyo)(2017年)
オンドジェイ・ストベラチェク『Sketches』(2016年)
レイモンド・マクモーリン@Body & Soul(JazzTokyo)(2016年)
及部恭子+クリス・スピード@Body & Soul(2015年)
松本茜『Memories of You』(2015年)
デイヴ・ホランド『Dream of the Elders』(1995年)
●粟谷巧
レイモンド・マクモーリン『All of A Sudden』(2018年)