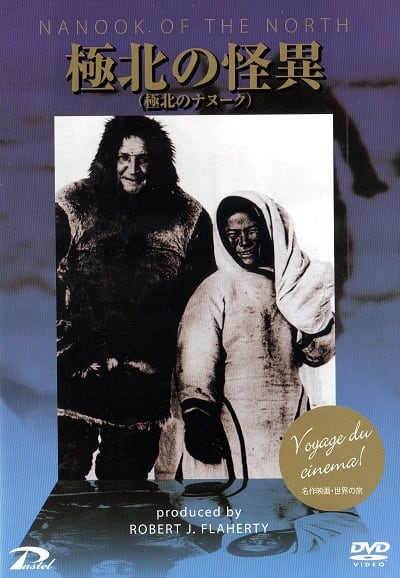『けーし風』第72号(2011.9、新沖縄フォーラム刊行会議)の読者会に参加した。今回は編集者のSさん、Oさんのご尽力により、元「ひめゆり学徒」の上江田千代さんの講演会になった。

上江田さんは1929年、現在の那覇空港あたり、小禄村の生まれ。沖縄師範学校に入学、1年生ながら動員され、戦火のもと奇跡的に生き延びて、戦後は平和教育を行っている。なお、上江田さんの上の学年の子たちが看護要員として陸軍病院に動員され、のちに映画などになっている。
ヴィデオで『1フィート映像でつづるドキュメント沖縄戦』(1995年)の抜粋版を観たあと、上江田さんが話をした。
○5歳のころ、小禄に沖縄ではじめての飛行場ができた。接収は収穫前の農地を無造作に扱うなどひどいやり方だった。この飛行場は、次第に軍部が使うようになった。近くに予科練(海軍の練習設備)ができた。そのため、小さいころから予科練の歌を歌って育った。
○皇民化教育を受け、軍国少女になった。教育勅語では、いざという時には死んで国に尽くせと教わった。
○教師になりたくて師範学校に入った。ここは国がオカネを潤沢に支給するところで、それが裏目に出て、「看護要員を出せ」ということになったのだ。
○戦時中、食糧は配給制、衣類は切符制であり、米軍の攻撃により沖縄まで物資が届かなかったこともあって非常に辛かった。後で、国家予算の75-80%が軍備のためだったと知った。
○セーラー服は敵国の服であるから許可されず、そもそも衣類が足りないため、父親の着物をリフォームして着た。壕の中では白い服はご法度だった。戦時中のもので残っているのはその服だけ、もうぼろぼろだが、父親の肌のぬくもりを感じられるようで宝物だ。

上江田さんは父親の着物をリフォームして作った服を持ってきた
○動員され、学校のある首里から小禄飛行場まで8kmの道のりを2時間弱かけて毎日歩いた。そこでは堀を掘り整地する作業をさせられ、その後、高射砲の陣地造りなどもやった。食事は芋一切れと牛蒡、塩汁(「太平洋汁」と称した)。倒れる人がいなかったのは、消灯になると絶対に寝なければならず、睡眠を十分に取っていたからだろう。
○1944年10月10日の「10・10空襲」では、那覇の街が真っ赤に燃えるのが見えた。文字通り那覇は焦土になり、コンクリだけ残った。米軍は、飛行場、那覇軍港、那覇の街の3箇所を狙ったのだった。
○豊見城村名嘉地で両親の無事を確認、その後、イトコのいる豊見城村渡嘉敷に移動した。壕のいい場所は軍隊が使っていた。ここで師範学校生だとわかるや働けということになった。
○ところで、壕には2種類がある。南部に多い天然のガマと、斜面に横穴を掘った手作りのもの。戦時中、ガマは見たことがなかった。横穴式は非常に危険なつくりだった。この壕に入った瞬間に、尿と血と膿の臭いが押し寄せてきたが、じきに慣れた。
○食糧は塩むすびを1日に1個。
○負傷した兵隊に水を飲ませると、「ありがとう」の声が数日後に「あ、り、が、と、う」になり、次第に唇の動きだけになり、余命がわかった。生き地獄だった。
○壕の中では生理が止まる。恐怖や食糧状態のためだ。ひめゆり学徒の映画では生理のため女学生がおなかを押さえるシーンがあったが、まったくの誤認だ。許されない白衣を着ているシーンさえあった。
○ある日寝ていると、中年の将校が「家族のことが気になる」と話すのが聞こえた。そんな私的なことは話さなかった筈で奇異に思っていると、翌日、撤退命令が出た。要は歩ける者だけが南部に退くわけであり、そうでない者は殺すということだった。そして手榴弾が配られた。
○日本軍の兵隊たちの中には、逃げて生き延びろと言ってくれる者もいた。
○食糧の中では、栄養価の高い黒砂糖がもっとも役に立った。女性に必要な鉄分も含まれていた。
○夜中に逃げていて米軍の照明弾が上がると、道の周りにバラバラ死体が数多く見えた。死にかけた者が訴える「お水~」という声を忘れることはできない。そして、気がつくと死体の上を歩いていた。
○途中で伯父さんが脊髄をやられて草の上で亡くなった。イトコたちは泣かなかった。極限状態だった。
○すでにその頃、肉眼で米兵が見えるような距離に近付いてきた。彼らは民家に火を放っていた。
○「生きて虜囚の辱めを受けず」との教育を受けていたので、自決しようと救急鞄を開けたところ、あるはずの手榴弾がなかった。どうやら、自決しないよう父が無断で捨てていたのだった。沖縄には「命どぅ宝」という言葉がある。
○6月20日、父が壕を探していたところ銃で撃たれ即死した。母は見ていなかった。夜中のことであり(米軍は奇襲を恐れ昼間に行動)、また1発のみを発射する方法であったことから、日本兵が撃ったものだとわかった。直後に逃げる日本兵が見えた。
○実はこのことを戦後50年間誰にも言わなかったため、日本兵が民間人を殺した統計には入っていない。この統計は申告に基づくものだから、このようなケースや、一家全員が殺された場合などは含まれていない。
○壕の代わりに亀甲墓の中に隠れた。既にいた負傷兵たちは傷口をウジに食われ、痛がっていた。取ってやると感謝された。6月20日はウジとのたたかいの日だった。
○弾が来なくなり、それは近くに米兵が迫っている証拠であるから怖れていると、「抵抗しないで出てこい」との拡声器の声が聞こえた。そして爆弾が投げられ、中のほとんどが死んだ。自分は小さな穴に入っていて、母がかばってくれたので助かった。
○他の助かった女性が先に出て、外から「アメリカ兵は殺さないようだから出てきなさいよ」と叫んできた。もう3ヶ月も夜中だけ行動していたため、外に出るとまぶしくて目が開けられなかった。そこにまるで赤鬼のような米兵が立っていて、水をくれた。そして集められ、そこで殺されるのかと思っていると毛布をくれた。
○翌6月21日、トラックで知念村山里に移動させられた。ここには木々も水もあった。その後、那覇の宇栄原(ウエバル)に移った。
○まったくみじめではなかった。何しろもう弾が降ってこないうえ、青空のもとを堂々と歩けるのだ。たったそれだけで幸せだった。
○日本は変な方向にまた動いているとはいえ、まだそれほど怖ろしい状態ではない。いまの平和を大事にしてほしい。いっしょに平和を護りましょう。
ところで戦後、上江田さんは糸満高校に入っている。そこで、米兵の服の生地に米兵の靴紐を刺繍して、校章を作ったのだという。上江田さんが持参した実物を見せていただいた。「IHS」(イトマン・ハイ・スクールの略)が刺繍されたそれは、丁寧に作られていた。上江田さんは、もう作れませんと繰り返した。

講演後、ごく短い時間ながら、全員でいつものように話をした。辺野古のことで気になる公有水面埋立特措法が本当に作られることはないのか、一坪反戦地主会のYさんに訊ねた。一応は全国を対象にしている駐留軍用地特措法と異なり、今度はあからさまに沖縄に特定した特措法になるわけであり、それはあり得ないだろうとの見解。まずはアセスの「評価書」を出さないよう防衛省に、受け取らないよう沖縄県知事に働きかけることが大事だとのことだった。
●ひめゆり
○今井正『ひめゆりの塔』
○舛田利雄『あゝひめゆりの塔』
○森口豁『ひめゆり戦史』、『空白の戦史』
○仲宗根政善『ひめゆりの塔をめぐる人々の手記』、川満信一『カオスの貌』
○『ひめゆり』 「人」という単位
○大田昌秀講演会「戦争体験から沖縄のいま・未来を語る」(上江田千代さん)
○沖縄「集団自決」問題(9) 教科書検定意見撤回を求める総決起集会(上江田千代さん)
●けーし風
○『けーし風』読者の集い(14) 放射能汚染時代に向き合う
○『けーし風』読者の集い(13) 東アジアをむすぶ・つなぐ
○『けーし風』読者の集い(12) 県知事選挙をふりかえる
○『けーし風』2010.9 元海兵隊員の言葉から考える
○『けーし風』読者の集い(11) 国連勧告をめぐって
○『けーし風』読者の集い(10) 名護市民の選択、県民大会
○『けーし風』読者の集い(9) 新政権下で<抵抗>を考える
○『けーし風』読者の集い(8) 辺野古・環境アセスはいま
○『けーし風』2009.3 オバマ政権と沖縄
○『けーし風』読者の集い(7) 戦争と軍隊を問う/環境破壊とたたかう人びと、読者の集い
○『けーし風』2008.9 歴史を語る磁場
○『けーし風』読者の集い(6) 沖縄の18歳、<当事者>のまなざし、依存型経済
○『けーし風』2008.6 沖縄の18歳に伝えたいオキナワ
○『けーし風』読者の集い(5) 米兵の存在、環境破壊
○『けーし風』2008.3 米兵の存在、環境破壊
○『けーし風』読者の集い(4) ここからすすめる民主主義
○『けーし風』2007.12 ここからすすめる民主主義、佐喜真美術館
○『けーし風』読者の集い(3) 沖縄戦特集
○『けーし風』2007.9 沖縄戦教育特集
○『けーし風』読者の集い(2) 沖縄がつながる
○『けーし風』2007.6 特集・沖縄がつながる
○『けーし風』読者の集い(1) 検証・SACO 10年の沖縄
○『けーし風』2007.3 特集・検証・SACO 10年の沖縄