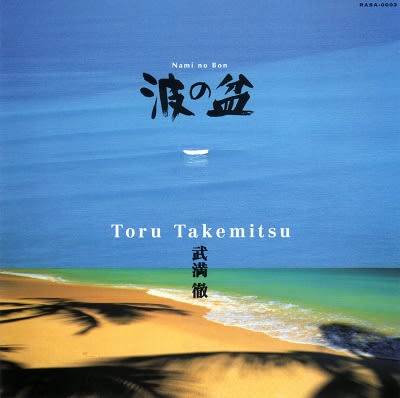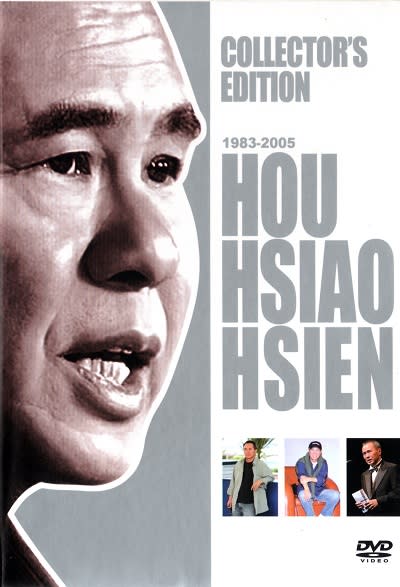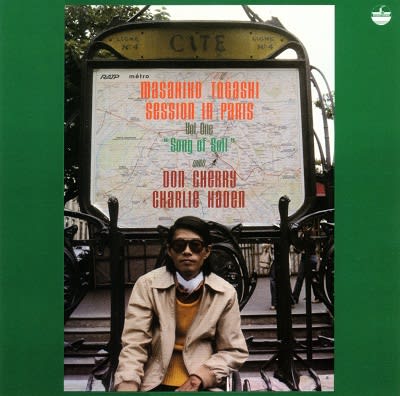いまさらではあるが、ヴィジェイ・アイヤー。インド・タミル人を出自に持つ米国のピアニストである。
ピアノソロ作『solo』(ACT、2010年)と、ピアノトリオ作『accelerando』(ACT、2012年)を聴いている。

Vijay Iyer (p)

Vijay Iyer (p)
Stephan Crump (b)
Marcus Gilmore (ds)
ひたすら硬いという印象。ブルージーな要素はない(ハービー・ニコルスの曲ではさすがに出てくる)。
硬い氷の欠片を投げつけられているような気分だ。かと言って、イメージの奔流のようなものがあるわけでもない。このように中庸で、かつ尖がったピアノは、スタイリッシュだということはわかっても、あまり好みではない。
それでも工夫が凝らしてあり、何度も繰り返し聴いている。
両盤に共通する曲が、マイケル・ジャクソンが歌い、マイルス・デイヴィスもカバーした「Human Nature」である。ソロは清新な感覚で、トリオでは前半にジャンピーなフレーズを押しだしていたベースが、後半ではアルコに転じ、はらはらして聴かせる。
珍しいことに、トリオ作では、ヘンリー・スレッギルの「Little Pocket Size Damons」が演奏されている。スレッギルの『Too Much Sugar for a Dime』の初っ端に演奏されている曲であり、こちらは「ヴェリー・ヴェリー・サーカス」グループならではの重層的なアンサンブルを示しているのに対し、アイヤーのトリオでは、ベースもドラムスも変則的でトリッキーなリズムを刻むことで対抗しようとしているようだ。悪くない。
スレッギルの曲を、スレッギル不在の場所で演奏するのは、例えば、チコ・フリーマンが演奏した「The Traveler」があったが、ちょっと珍しいのではないか。
●参照
○ワダダ・レオ・スミス『Spiritual Dimensions』(アイヤー参加)
○ヘンリー・スレッギル(5) サーカス音楽の躁と鬱(「Little Pocket Size Damons」)