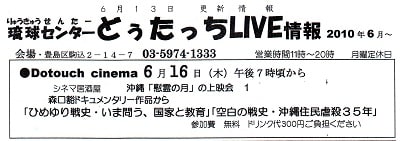駒込の「琉球センター・どぅたっち」にはじめて足を運んだ。琉球独立を是とする場であり、これまで気軽に行かなかったわけなのだが、何のことはない、とても居心地の良い空間だった。いつも『けーし風』の読者会に参加しているAさんと遭うことができた。
目当ては、ジャーナリストの森口豁さんがかつて「NNNドキュメント」枠で制作したテレビドキュメンタリー、『ひめゆり戦史・いま問う、国家と教育』(1979年)および『空白の戦史・沖縄住民虐殺35年』(1980年)の上映である。12名ほど集まり、森口さんご本人も現れた。
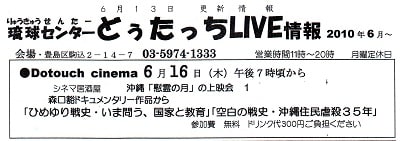
●『ひめゆり戦史・いま問う、国家と教育』(1979年)
年に数回あったという拡大版の55分。いわゆる「ひめゆり部隊」の生き残り5名を訪ね、彼女たちの生の声から、軍事国家社会と皇民化教育の実状を示していくつくりとなっている。
敗戦から34年、皆50歳を超えたときになって、改めて卒業証書が授与された場面からはじまる。そして、那覇、本部町、国頭村、長野、さまざまな場所に住む彼女たちが口を開き始める。突然解散命令が出て、米軍捕虜になったら恥であり酷い目にあわされるから、手榴弾で殺してほしいと思っていた。沖縄本島南端の喜屋武岬では、女性・子どもに対する米軍の投降勧告の声が死ぬよりも恐ろしく、それに応じた者の背中には日本軍が銃弾を浴びせ、海が赤く染まった。学校では疎開者を非国民呼ばわりした。疎開するなら4年支払った給料を全て返せと言われた。―――と。
ある女性は、このような皇民化教育を「魔の力」だと表現する。ある女性は、生き残ったことが後ろめたいと言う。ある女性は、もう戦争やだ、もう戦争やだ、と繰り返す。亡くなった娘の母親は、いつか帰ってくると信じて毎日鍵をかけずに寝ている。そして、取材には決して応じない生き残りの女性もいる。彼女は、仲宗根政善『沖縄の悲劇』において、日本軍兵士の獣性を語っている。取り返しのつかない傷口はあまりにも生生しい。
数々の証言のなかから、沖縄女子師範学校の西岡一義校長の存在が浮かび上がってくる。ひめゆり部隊の行動を命令し、それに異を唱えた人物を「洗脳者」と罵り、そして生徒たちと行動を共にせず安全と信じられていた日本軍本部に身を寄せた人物である。戦後、彼は一度も沖縄を訪ねることもなく杉並区に住み、東京学芸大学で定年退職まで教鞭と取っている。取材に対し、あれは軍の命令だったから仕方がない、「俺も戦争の犠牲者だ」と居直る声が捉えられている。当時沖縄でもこのドキュが放送され、大きな怒りとともに受けとめられたという。
一方、八原博通陸軍大佐(高級参謀)は取材に対し、自分はひめゆり部隊の徴用に反対したのだが結果的に役に立った、あれは県庁の考えだった、と答える。矛盾するようだが、実際には、県と軍との折衝によって決められたものであった。森口さんの話では、ドキュ放送後、八原氏本人から、「花も実もある番組だった」との謝意を示す葉書が届いたのだという。それがどのような意味だったのか、もはや確認できない。
このドキュに投じられた費用は、通常の300万円(当時)を遥かに超える1000万円だったとのことだ。「お国のため」と主張した沖縄の教師も確かにいたというが、まだ沖縄に対する関心が深化していない時代にあって、ヤマトゥの戦争犯罪を免罪する可能性があると判断し、そのような場面は使わなかった、今なら使うかな、と、森口さんは上映後に語った。
●『空白の戦史・沖縄住民虐殺35年』(1980年)
大宜味村の渡野喜屋(いまの白浜)において、南部から疎開していた住民たち約30人が日本軍に虐殺された事件があった。塩屋湾の近くであり、浜に立たせておいて、兵隊が1、2の3で手榴弾を投げて殺した。すべてスパイ容疑、その前に、3人が山中でやはり日本軍に殺された。
このドキュの主人公は、その宇土部隊に通信兵として同行し、虐殺を止めることができずすべてを目撃した森杉多さんである。直接手を下したのではないが、罪をわがものとして負い、現地を訪ねて遺族に謝罪する姿が捉えられている。それは、『ひめゆり戦史』において、自分も犠牲者だと自らの罪を勝手に免責する醜い姿とは正反対の場所にある。森さんは戦後、東京の高校で社会科を教えながら、『戦争と教育』という本をものし、また、頻繁に集会に出席して発言し、熾烈な批判を浴びたこともあったのだという。
ドキュの中で、軍の機密文書が示される。宇土部隊のミッションのひとつは容疑者の監視であったこと、そして標準語を喋らない者(沖縄の言葉を喋る者)はスパイと見なし処分することが、はっきりと定められている。
森口さんは、沖縄差別が底流にあったことは間違いない、しかし、仮に米軍が九州や房総に上陸したとしても同じようなことが起きただろう、それが軍というものの本質だ、と語った。
上映が終わったあと、飲み食いしながらいろいろな人たちと話した。森口さんがご自身のブログで、このブログのことも紹介してくださっていたことがあった(>> 〈沖縄〉が分かる! 森口豁のお薦めブログ No,1)ので自己紹介すると、60歳くらいの人かと思っていたよ、と言われてしまった。また褒められてしまい恐縮した。
●参照
○森口カフェ 沖縄の十八歳
○罪は誰が負うのか― 森口豁『最後の学徒兵』
○『子乞い』 鳩間島の凄絶な記録
○『沖縄・43年目のクラス会』、『OKINAWA 1948-49』、『南北の塔 沖縄のアイヌ兵士』
○『“集団自決”62年目の証言~沖縄からの報告~』、『沖縄 よみがえる戦場 ~読谷村民2500人が語る地上戦~』(渡野喜屋事件を取りあげている)
○『兵士たちの戦争』、『未決・沖縄戦』、『証言 集団自決』(宇土部隊を取りあげている)
○『けーし風』2008.6 沖縄の18歳に伝えたいオキナワ
○仲宗根政善『ひめゆりの塔をめぐる人々の手記』、川満信一『カオスの貌』
○『ひめゆり』 「人」という単位
○沖縄「集団自決」問題(記事多数)