大江・岩波沖縄戦裁判を支援し沖縄の真実を広める首都圏の会(沖縄戦首都圏の会)による連続講座第3回、
大城将保氏による「
沖縄戦の真実と歪曲」に参加してきた(2007/10/25、岩波セミナールーム)。


会場はほぼ満員、たぶん40~50人くらいは集まった。また石山久男氏など教科書関係者も何人もおられたようだ。
大城氏は、
嶋津与志のペンネームで、幕末の琉球を描いた
『琉球王国衰亡史』(平凡社ライブラリー)、沖縄戦を描いた
『かんからさんしん物語』(理論社)などいくつもの小説を書いている。
最初に、その小説を原作にし、大城氏(嶋氏)が脚本も書いたアニメ映画
『かんからさんしん』(1989年)(→
リンク 予告編を見ることができる)の最後の部分が上映された。
そこでは、旧日本軍(友軍)が住民の食糧や水を奪い、デマを嘘だと見破るハワイからの移民をスパイ扱いし「処刑」しようとし、「集団自決」、そして投降に至る様が描かれている。なかでも圧巻なのが、手榴弾で「集団自決」しようとすると、幼児が死に際して着せられた晴れ着を自分でびりびりと破り、嫌だと泣き叫ぶ場面だ。泣く子どもは米軍にばれるので殺すという恐ろしい軍の慣習があるので、皆が子どもをなだめようとすると、おばあが「子どもは童神だ。神さまが何かを言おうとしているのだ」と、皆に「集団自決」を思いとどまるよう呼びかける。
一旦は我に帰る住民だが、また兵隊が捨て身で米軍に攻撃を仕掛けると、米軍からの集中砲火がある。そして住民のひとりが手榴弾を自ら爆発させると、他の住民もそれに続き始める。その「集団自決」の連鎖に歯止めをかけたのが、既に白旗を掲げた女の子が歌う民謡「いったーあんまーまーかいが」(お前のお母さんはどこに行ったの)だった。
これはフィクションではあるが、大城氏によれば、実際に沖縄戦においてあった話をもとにしている(津堅島、伊江島)。「死」に向かって心がフリーズしているのを元に戻させるための「間」、そして「生きたい」という心の奥底に辿りつく力をもつ歌。
大城氏の講演は、以下のようなものだった。
●9月の県民大会では、意思が島ぐるみとなり、11万人が集まった。
●旧日本軍の直接的な関与により「集団自決」が起きたのは紛れもない史実であり、多くの体験談がそれを裏付けている。
●軍による残虐行為は慶良間諸島だけではなく、至るところであった。それを慶良間の座間味島・渡嘉敷島の、しかも隊長命令があったかどうかだけに絞って裁判をおこしていることは、そもそも意図した問題の矮小化だ。ここには騙されやすい落とし穴がある。「曖昧なら裁判が決着してから判断」「両論併記」という陥りがちな考え方は、実は、史実を隠蔽しようとする策略に組み入れられているに過ぎない。
●「沖縄の人々は戦争で苦労した。それなのに政府は冷淡だ。だから耳を傾けるべきだ」とする意見にも落とし穴がある。問題は「可哀想だから」ではない。
●「集団自決」は、旧日本軍による住民虐殺(見せしめ、処刑)が住民に恐怖感をうえつけ、パニックに至りやすくしたという構造がある。「集団自決」と住民虐殺は表裏一体のものだった。
●(大城氏は「集団自決」や住民虐殺の事例のリストを用意したが)実際にはリスト以外にまだまだある。死んだ人はそもそも証言などできない。かろうじて生き残った人(沖縄で4人のうち3人、本島では3人のうち2人)も、死のうとしたり家族を先に殺そうとしたりといった生々しい体験を、なかなか自ら口にできなかった。そのような、語られない「隙」を狙って、「集団自決」を「神話」化することは許されない。
●軍の命令は、戦時中、とくに戦争末期にあっては、上から下への口頭での伝令であって、命令文書などなかった。それを軍命有無に悪用するのは、当時の常識に反している。
●『かんからさんしん』は、アニメだからといってオーバーではなく、むしろ逆だ。別の作品では、ある体験者の方から、「現実はもっとひどかった。ガマはもっと暗かった。」と言われた。乳飲み子を餓死させてしまった母親は、暗くて死んだ子の顔を見ることができず、顔を手のひらで覚えようと1週間なでていた。
●生き残った者には、後ろめたさ、加害者意識もある。大城氏自身も5歳のときに本土に疎開したことがいまだ後ろめたい。
●沖縄の本土復帰前後に「沖縄県史」を残し始め、その後も各地において歴史をしっかりと記しておこうとする動きはずっと続いている。戦争体験はまだ風化していない。これは、裁判の原告側がたった2日間の慶良間島取材によって「集団自決」の反証を得たとし、さらにはもう戦争体験は風化しただろうからそろそろ「美しい国」を作り上げようとする誤った流れに対抗しうるものだ。
●「美しい国」、あるいは戦争できる国、を目指して、「戦争の史実が風化したに違いない」沖縄をターゲットにして史実をゆがめ、さらに裁判を起こし、そして教科書検定がなされた。その意味で、訴訟も検定もすべてつながっている。裁判が終わってから検定の是非を判断するというのは、中立的なようでいて、実はそうではない。
●『かんからさんしん』では、「集団自決」は一部の住民にとどまり、多くの住民は助かることになっている。本島では3分の2が生き残ったのだ。死ぬことを描くより、如何にして生き残っていたかが大事なことだろうと考えてのことだ。「死から生」への転換の象徴化こそが、この作品の価値だと思っている。それに、住民が死んでいった記録は、「1フィート運動」などの素晴らしい動きもある。
●読谷村の米軍上陸地点に近いチビチリガマでは「集団自決」があったが、その近くのシムクガマではなかった。旧日本軍がいて、義勇隊も含め、竹槍での最後の斬り込みを行うといった状況も同じだったが、この違いは、実に微妙なところにあった。チビチリガマでは誰かの手榴弾が爆発し、つぎつぎに衝動的に死の方向へ引きずられていった。一方シムクガマでは、ハワイ移民二人(おじいさん)が、なぜか、手榴弾を捨てろと叫び、ガマ中に響いた。そこで住民は立ちすくみ、死の方向への暴走がストップした。そして二人は出て行って米国と交渉した(そのフィルムがある)。生と死を分けたものはこれだけ、「軍隊の論理」を「住民の論理」に引き戻した出来事だった。
●シムクガマのことは、戦後何年もまったく語られることがなかった。千人もの生き残った住民が、チビチリガマの人達に遠慮し、だれ言うことなくタブー化したのだ。生き残っただけでも申し訳ない、という気持ちであった。それを、黙っているのを良いことに、なかったことにしようという動きに利用されている。
●裁判の原告は、大城氏が、自ら執筆した「沖縄県史」において隊長命令のことを覆したと主張している。そんなことはありえない。単に主張だけなら自由だから、「研究紀要」に掲載されただけだった。
●裁判で決着がつかないうちでも、検定を通じて、教科書を書き換えることはできる、それが原告とその背後のねらいだった。隊長の名誉がポイントではない。
●しかし、やってみると、人事ではなくなった一般県民が敏感になり、地元紙にぞくぞく体験の投書をはじめた。それで、歴史自体の隠蔽と歪曲は無理だと悟り、隊長命令の有無だけに争点を絞った。その意味で、この実に矮小化されたことだけを云々するのは、そもそも歴史修正の流れに乗っかっていることになる。
●旧防衛庁の戦史には、「軍の煩累を絶つため、崇高な犠牲的精神で自ら死を選んだ」と書いてある。これが旧防衛庁の公式文書だった。軍隊と戦争と「集団自決」を美化する「軍隊の論理」だ。実際には、「崇高な精神」などといった格好良い言葉では人間は死ねないものだ。心をフリーズさせなければ無理だ。
●チビチリガマとシムクガマとの結果の違いを分けたこと。津堅島で子供が晴れ着を破り、おばあの呼びかけによって間ができて我に帰り、もう死ねなくなったこと。阿嘉島では最初の手榴弾が不発でばかばかしくなり、目が覚めたこと。このように死と生との転換は微妙だった。誰にも心の奥底には生きたいという心がある。しかし、言えばスパイ扱いされることもあり、しまいこんだ。これが何かの拍子に浮かび上がる。
●沖縄市美里では、隊長から、義勇隊(青年と老人)に、家族を殺してこいとの軍命があった。逃げるのに足手まといになるからだ。手榴弾がもったいないので閉じ込めて家を燃やし、30人が焼死した。こんなことは、なかなかひとに語ることができないものだった。このような体験があちこちにある。
●軍隊は国民を守らない、米軍より日本兵のほうが怖かった、命どぅ宝、この3つは体験者がみんな言うことだ。
●軍事を維持するためには、軍隊を美化しない歴史は邪魔な存在だ。このようなデマ宣伝は、ファシズムといってもよい。歴史の修正の先には、念頭に徴兵制があるはずだ。このような流れを止めなければ、子どもたちが戦争に巻き込まれてしまう。
●そして慶良間諸島での軍命の有無についても、なかったとする隊長の証言を裏付けるものはまったくない。
「「いまだ。全員、玉砕だ!いいか、家族はひとかたまりになれ。合図するまでまて!」
合図をまたずに、手りゅう弾はあちこちで炸裂していた。
―――まだか、まだか。
心があせる、取り残されるのが怖い。
「マサ、どうするね、どうするね」
「まて、合図があるまでまつんだ」
正吉はぶるぶるふるえる手でようやく安全ピンを引きぬいた。信管をたたいてしまえばいっぺんに楽になる。
「イヤだ!イヤだ!ならん!」
いきなり、フミが叫び出した。
(略)
全員がマラリア患者のようにガタガタふるえ、手りゅう弾をもっておれなくなった。正吉は鉄のかたまりをなげだし、両手で頭をかかえこんでしまった。」
『かんからさんしん物語』(嶋津与志、理論社)より














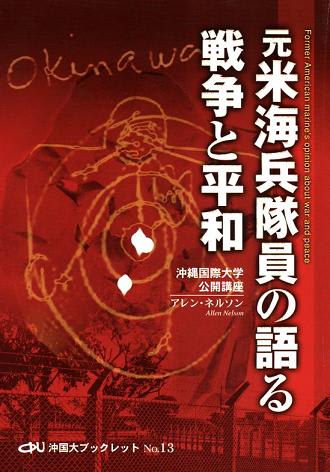












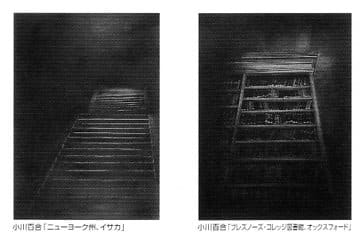


 =====
=====































