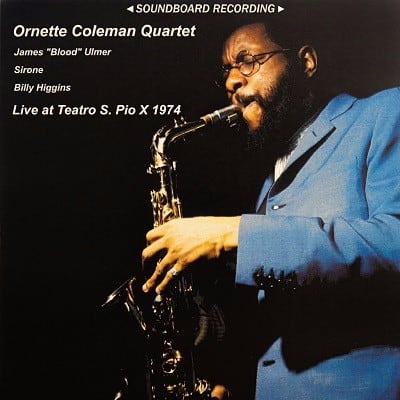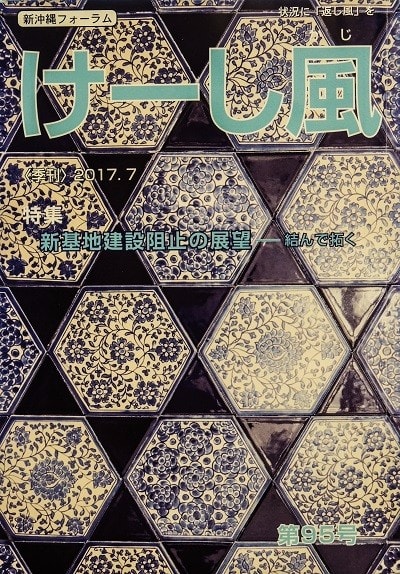大田区沼部駅の近くにある「いずるば」。今年の3月の「第ゼロ回」を皮切りに、齋藤徹さんを中心にしたワークショップが行われている。わたしも「第ゼロ回」を覗いただけだったが、久しぶりに足を運んだ(2017/7/23)。
意気込み過ぎて1時間早く着いた。勘違いに気が付いてカフェを探したのだが閉まっている。道の向い側には「花の湯」という銭湯があり、おばあさま方が開くのを待っている。これも何かの運命なので番台でタオルを買って風呂に入り、湯上りにガリ子ちゃんを食べた。すっかり血色が良くなり不自然な感じになった。

Tetsu Saitoh 齋藤徹 (ワークショップ進行)
Le Quan Ninh (応答)
Michel Doneda (応答)
ワークショップは全員参加型のものではなく、テツさんが問いかけ、それに対してニンさんとドネダさんが答える形となった。
―――テツさんの不参加について。
(ニン)ショックだったがそれが最良。音楽で大事なのは自分自身と向き合い演奏することだ。テツさんが居ないことで、新しい人たちと強い関係性を作ることができた。
(ドネダ)テツさんを通じて知り理解した日本。今回共演できないとしても来た。
―――初日の竹林での演奏(ミシェル・ドネダ+レ・クアン・ニン+今井和雄@東松戸・旧齋藤邸、2017/7/9)。ニンさんは擦ることで音程を作り、ドネダさんは音程を外れて風になる。それによる匿名性。「人とは違う」ことをベースとする音楽ではない。貨幣社会への批判でもあるのでは。
(ニン)楽器との接触により自分がなくなる感覚はある。表現のためではなく知覚のために演奏する。表現の欲求が出る前に音の性質を見つける。音とはミステリアスなものであり、囚われないようにしている。「なぜ」を追究するのではない、目の前の音が大事なのだ。その場において必要なことを見つけるのだ。匿名性よりも消滅。
(ドネダ)存在とは音を出すことだ。音を発すると相手も返してきて、それにより存在がわかる。モノではなく知覚を作る、それが投影にもなる。即興とは形を作るのではなくその場に現象を作ることだ。観る者は各々の背景に基づき知覚する。消滅とは動きでもある。
―――ポレポレ座における、雅楽の若い音楽家たちとの共演について(2017/7/10)。
(ドネダ)良い即興ができた。驚くべきことだ。世代は関係ない。「先生」が崇められる伝統があるかもしれないが、「先生」と共演しても犬と共演しても大した違いはない。
(ニン)即興も伝統音楽も「聴く」ことにおいては共通している。ドネダもアフリカの音楽家たちと共演した(『OGOOUE-OGOWAY』のことか)。「聴く」ことは文化的行為であり、その中には「無」も含まれる。手と手を重ねるのではなく、指の間を広げて無を作りだせば、衝突はない。
(ドネダ)即興にはヒエラルキーはない。
―――エアジンにおけるふたりのダンサー(庄﨑隆志、矢萩竜太郎)について(2017/7/12)。庄崎さんは聾だが、かれはニンさんのバスドラムの下に潜った。
(ドネダ)驚きとともに始まったが、常識との対立は一瞬で消えた。それがなぜだかは答えられない。ダンサーは表現によって自分たちと共演したいという歓びに満ちていた。
(ニン)「聴く」ということは聴覚だけのものではない。その場にいることを知覚することだ。ダンサーたちの存在感は強かった。
―――即興の対義語とは作曲ではなく、自分自身なのではないか。自分自身に拘っていては良い即興ができないのではないか。
(ニン)たとえば飛行機や自動車や電車で移動する日常の違い。その違いが即興の本番で消えていることが大事だ。そのためには身体の鍛錬も必要。順番やプログラムを忘れて即興に入ることも良い。プログラムに沿うのではなく、みんなとひとつになったと思える瞬間は良い即興だ。生きるという体験では何でも起こりうる。理論や経験だけではなく、どのようにうまく回るか。
(ドネダ)即興にヒエラルキーがないということは、責任も自由も生じることを意味する。他の人が被るリスクもある。「先生」が居ないほうが大変な道だろう。しかし、仮に自由が損なわれたら、他の道を探すのだ。政治的な芸術はどの世界にもはびこっている。



ワークショップが終わり、1時間の休憩を挟みライヴ。テツさんは前日のホール・エッグファームでの演奏で疲労してしまったようで、不参加となった。ニンさんが準備中に試すように叩いていると、矢萩竜太郎さんが出てきて踊る時間もあった。
Le Quan Ninh (perc)
Michel Doneda (ss)
Natsumi Sasou 佐草夏美 (舞い)
蹲り拝む佐草さん。ドネダの音には間が大きく、先の話の雅楽を思い出したのだろうか。ニンは周縁を弓で擦り、金属板を使ってするどいタッピング、棒。空を飛翔するようである。ドネダの倍音も増えてゆく。
静寂、ニンのたんたんたんと刻むリズムだけが聴こえる。佐草さんは立ち上がった。ドネダのサックスによる急旋回、ニンの音にシンクロするような金属音。ニンの石、ドネダの息。ふたりのシンクロは振幅を大きくしてゆき、ニンは助走を付けるように指の腹で太鼓を擦り、地震を起こし、ドネダは魅力的な倍音をみせる。
またしても静寂。佐草さんの円環と横移動。ニンは掌底で強く叩き、ドネダは倍音を集約させてクラスター化する。かれらの高まりにより何かが起き、佐草さんは再び蹲る。
ニンが作りだす残響。ドネダは循環呼吸により応え、佐草さんは足の音を立てる。やがてニンもドネダも軋みを生じ始める。ドネダは何者に化けたのか、甲高いホーン音、まるで蜂の音、まるで電子音。人がドラムに片方を置いた棒を弓で擦り、ドネダがそうであるように風になった。
最初から最後まで緊張感が支配した、素晴らしい共演だった。










終了後に打ち上げがあった(ごちそうさまでした)。ドネダさんに、ジャズとのかかわりを訊いた。
―――エルヴィン・ジョーンズとの共演は「ジャズ」だったのでは。
「最初にエルヴィンに、自分はジャズではないがと問うと、エルヴィンは、我々がやるのはジャズじゃない、音楽だ、と肩を強く叩いてくれた。そして録音前に1時間セッションをやったんだよ!」
―――でも、最近の『Everybody Digs Michel Doneda』のジャケットは、『Everybody Digs Bill Evans』のパロディですよね。
「プロデューサーがやったんだよ。ビックリしたよ(笑)。即興の方で手一杯で、ジャズに手を出す余裕はない。でもジャケットに書いてあるデイヴ・リーブマンも、エヴァン・パーカーも良い友達だよ。デイヴとはアメリカでセッションもやった。」
―――スティーヴ・レイシーは。あなたのソプラノとはだいぶ違い、ベンドして音を作っている。
「素晴らしいプレイヤーだった。もちろんベンド、それだけでなくあらゆる技法に通暁していた。70年代はかなり実験的で、その後ジャズの方に行ったけれど」
―――ロル・コクスヒルは。
「かれも素晴らしいプレイヤーだった。共演もしたんだよ(『Sitting on Your Stairs』)。」
Fuji X-E2、XF35mmF1.4、XF60mmF2.4
●ミシェル・ドネダ
ミシェル・ドネダ+レ・クアン・ニン+今井和雄@東松戸・旧齋藤邸(2017年)
ミシェル・ドネダ『Everybody Digs Michel Doneda』(2013年)
ミシェル・ドネダ+レ・クアン・ニン+齋藤徹@ポレポレ坐(2011年)
ロル・コクスヒル+ミシェル・ドネダ『Sitting on Your Stairs』(2011年)
ドネダ+ラッセル+ターナー『The Cigar That Talks』(2009年)
ミシェル・ドネダと齋藤徹、ペンタックス43mm(2007年)
齋藤徹+今井和雄+ミシェル・ドネダ『Orbit 1』(2006年)
ミシェル・ドネダ+レ・クアン・ニン+齋藤徹+今井和雄+沢井一恵『Une Chance Pour L'Ombre』(2003年)
齋藤徹+ミシェル・ドネダ『交感』(1999年)
齋藤徹+ミシェル・ドネダ+チョン・チュルギ+坪井紀子+ザイ・クーニン『ペイガン・ヒム』(1999年)
ミシェル・ドネダ+アラン・ジュール+齋藤徹『M'UOAZ』(1995年)
ミシェル・ドネダ『OGOOUE-OGOWAY』(1994年)
バール・フィリップス(Barre's Trio)『no pieces』(1992年)
ミシェル・ドネダ+エルヴィン・ジョーンズ(1991-92年)
●レ・クアン・ニン
ミシェル・ドネダ+レ・クアン・ニン+今井和雄@東松戸・旧齋藤邸(2017年)
ミシェル・ドネダ+レ・クアン・ニン+齋藤徹@ポレポレ坐(2011年)
ミシェル・ドネダ+レ・クアン・ニン+齋藤徹+今井和雄+沢井一恵『Une Chance Pour L'Ombre』(2003年)
●齋藤徹
齋藤徹+喜多直毅@巣鴨レソノサウンド(2017年)
齋藤徹@バーバー富士(2017年)
齋藤徹+今井和雄@稲毛Candy(2017年)
齋藤徹 plays JAZZ@横濱エアジン(JazzTokyo)(2017年)
齋藤徹ワークショップ「寄港」第ゼロ回@いずるば(2017年)
りら@七針(2017年)
広瀬淳二+今井和雄+齋藤徹+ジャック・ディミエール@Ftarri(2016年)
齋藤徹『TRAVESSIA』(2016年)
齋藤徹の世界・還暦記念コントラバスリサイタル@永福町ソノリウム(2016年)
かみむら泰一+齋藤徹@キッド・アイラック・アート・ホール(2016年)
齋藤徹+かみむら泰一、+喜多直毅、+矢萩竜太郎(JazzTokyo)(2015-16年)
齋藤徹・バッハ無伴奏チェロ組曲@横濱エアジン(2016年)
うたをさがして@ギャラリー悠玄(2015年)
齋藤徹+類家心平@sound cafe dzumi(2015年)
齋藤徹+喜多直毅+黒田京子@横濱エアジン(2015年)
映像『ユーラシアンエコーズII』(2013年)
ユーラシアンエコーズ第2章(2013年)
バール・フィリップス+Bass Ensemble GEN311『Live at Space Who』(2012年)
ミシェル・ドネダ+レ・クアン・ニン+齋藤徹@ポレポレ坐(2011年)
齋藤徹による「bass ensemble "弦" gamma/ut」(2011年)
『うたをさがして live at Pole Pole za』(2011年)
齋藤徹『Contrabass Solo at ORT』(2010年)
齋藤徹+今井和雄『ORBIT ZERO』(2009年)
齋藤徹、2009年5月、東中野(2009年)
ミシェル・ドネダと齋藤徹、ペンタックス43mm(2007年)
齋藤徹+今井和雄+ミシェル・ドネダ『Orbit 1』(2006年)
明田川荘之+齋藤徹『LIFE TIME』(2005年)
ミシェル・ドネダ+レ・クアン・ニン+齋藤徹+今井和雄+沢井一恵『Une Chance Pour L'Ombre』(2003年)
往来トリオの2作品、『往来』と『雲は行く』(1999、2000年)
齋藤徹+ミシェル・ドネダ+チョン・チュルギ+坪井紀子+ザイ・クーニン『ペイガン・ヒム』(1999年)
齋藤徹+ミシェル・ドネダ『交感』(1999年)
久高島で記録された嘉手苅林昌『沖縄の魂の行方』、池澤夏樹『眠る女』、齋藤徹『パナリ』(1996年)
ミシェル・ドネダ+アラン・ジュール+齋藤徹『M'UOAZ』(1995年)
ユーラシアン・エコーズ、金石出(1993、1994年)
ジョゼフ・ジャーマン