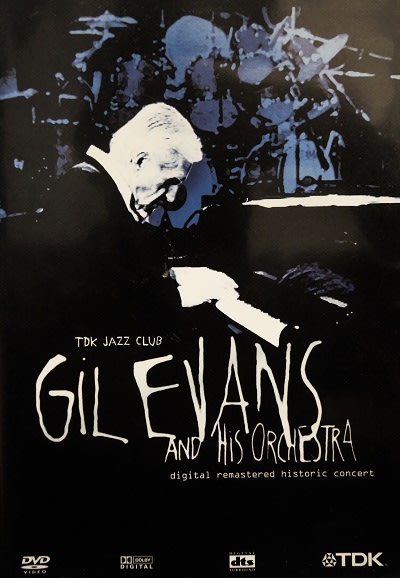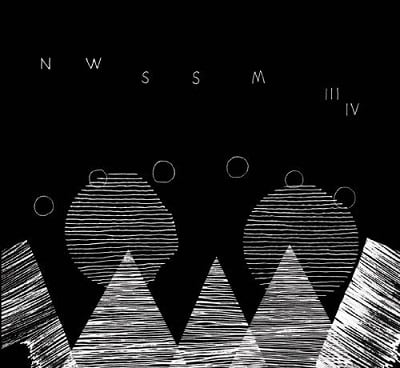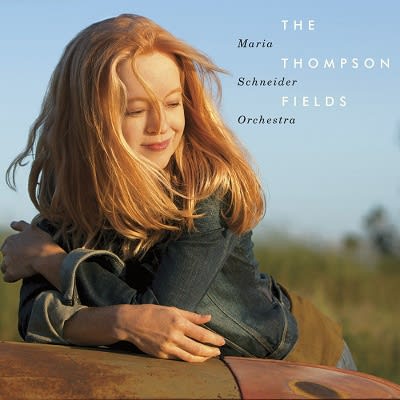デイヴィッド・マレイ+ジェリ・アレン+テリ・リン・キャリントン『Perfection』(Motema、録音2015年?)を聴く。

David Murray (ts, bcl)
Geri Allen (p)
Terri Lyne Carrington (ds)
guests:
Charnett Moffett (b)
Craig Harris (tb)
Wallace Roney, Jr. (tp)
これはまた、意表を突くグループを組んだものだ。驚いて早速レコード店に行き、さあ買うべきかと悩んでいたところ、この盤がかかり始めた。もはや驚くこともないデイヴィッド・マレイのブロウなのだが、やはりツボにはまってしまう。
そんなわけで昨晩から何度も繰り返し聴いている。最初からわかっていたことだが、すべて想定の範囲内である。マレイのテナーは十年一日のごとく手癖乱発クリシェ乱発、突破力が消えて味だけが残っている。ちょっとずれたトーンでヴィブラートをかけて朗々と吹いたり、フラジオで高音に駆け上がっては戻ってきたり。最初の「Mirror of Youth」では、「All the Things You Are」になりかけて慌ててそらしているような雰囲気があって、乱暴に言えば、「All the ・・・」を吹いた『Children』(1984年)がデジャヴとして思い出されるくらいの変わらなさなのだ。
それでもマレイの音が聴ければわたしは満たされるのであります。ええ、何か。
テリ・リン・キャリントンのドラムスは軽くて高速で、そのうえ何かがあって、ずっと聴いていられる魅力がある。この人もステキで好きなのだ。
アルバムのなかでは、オーネット・コールマンの「Perfection」のみ、チャーネット・モフェット、クレイグ・ハリス、ウォレス・ルーニーが参加している。ここでチャーネットの速弾きベースの見せ場があって、やはり偏愛対象。マレイもオーネット流になで肩の無手勝流で斬り込んできて素晴らしいソロを取る。このトリオもいいが、ぜひマレイとチャーネットとがずっと組んで作品を吹き込んでほしい。
●参照
デイヴィッド・マレイ・ビッグ・バンド featuring メイシー・グレイ@ブルーノート東京(2013年)
デイヴィッド・マレイ『Be My Monster Love』、『Rendezvous Suite』(2012、2009年)
ブッチ・モリス『Possible Universe / Conduction 192』(2010年)
ワールド・サキソフォン・カルテット『Yes We Can』(2009年)
デイヴィッド・マレイの映像『Saxophone Man』(2008、2010年)
デイヴィッド・マレイ『Live at the Edinburgh Jazz Festival』(2008年)
デイヴィッド・マレイの映像『Live in Berlin』(2007年)
マル・ウォルドロン最後の録音 デイヴィッド・マレイとのデュオ『Silence』(2001年)
デイヴィッド・マレイのグレイトフル・デッド集(1996年)
デイヴィッド・マレイの映像『Live at the Village Vanguard』(1996年)
ジョルジュ・アルヴァニタス+デイヴィッド・マレイ『Tea for Two』(1990年)
デイヴィッド・マレイ『Special Quartet』(1990年)
テリ・リン・キャリントン『The Mosaic Project: Love and Soul』(2015年)
ジェリ・アレン、テリ・リン・キャリントン、イングリッド・ジェンセン、カーメン・ランディ@The Stone(2014年)
デューク・エリントンとテリ・リン・キャリントンの『Money Jungle』(1962、2013年)
ジェリ・アレン+チャーリー・ヘイデン+ポール・モチアン『Segments』(1989年)