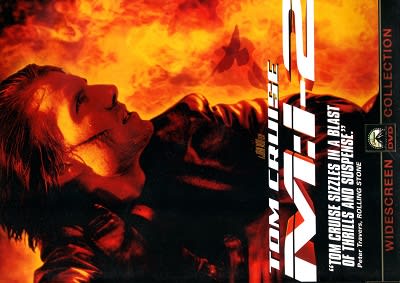ジョン・マグレガー『This isn't the sort of thing that happens to someone like you』(Bloomsbury、原著2012年)を読む。『これは、あなたみたいな人に起きるたぐいの事件ではない』とでも訳すのかな。
ジョン・マグレガー(Jon McGregor)は、1976年、英国領バミューダ諸島生まれの若い小説家である。作品を読むのははじめてだ。

裏表紙の謳い文句に、「洪水を心配する余りに、川沿いの樹の上に家を建てた男・・・」などとあって、てっきり、イタロ・カルヴィーノ『木のぼり男爵』のような奇想天外な長編小説だと勘違いして、買ってしまった。実際には、奇妙な物語を集めた短編集だった。
奇妙さは、ただのおかしなプロットによるものではない。ひとつひとつの物語に登場する人物たちは、決して論理ではなく、慢性的な偏執や、おそらく自分自身にも説明がつかぬような緩やかな衝動といったようなものによって、動かされている。ただひたすらに、徹底的に、屈折しているのである。彼ら・彼女たちの行動や思考につきあっていると、こちらの無駄な人生の時間や懊悩にも、仲間がいるのだなという気にさえさせられてしまうのだ。
樹上生活者は、毎朝、家の前で放尿し、川を往来する人々がなぜ手を振るのかを考える(とは言えないように、考える)。思春期、深夜、女性との逢瀬のあとに人を轢き殺してしまった男は、死体を埋めた場所の近くに老いるまで住み続ける。ある男は、卵から、ありえないほど低い確率で、生育した鶏が出てくる可能性が頭にこびりついて離れない。ある女性は、自動車の運転中に、突然、甜菜が窓ガラスに激突し、おかしな男たちにつきまとわれる。
そのようなプロットは、それぞれの短編を紹介したことにはならない。なぜなら、その状況下での登場人物たちの言動と思考回路こそが、説明できないほど奇怪であるから。
もうどうでもいいだろうと言いたくなるほどの屈折ぶりは、英国人作家のひとつのアイデンティティか。ジュリアン・バーンズだって・・・。
短編によっては1行だけだったり、空白だらけだったり(筒井康隆『虚人たち』のように)、伏字があったりと、実験精神というか、何かヘンなことをやってやろうという意欲が溢れている。しかもそれらが上滑りしており、それすら平気の平左という感覚である。何なんだ、この人は。