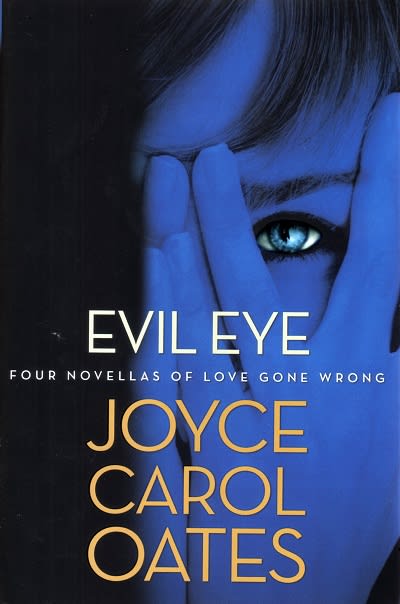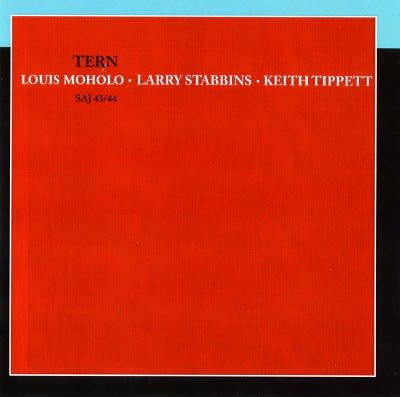テッサ・モーリス=スズキ『北朝鮮へのエクソダス 「帰国事業」の影をたどる』(朝日文庫、原著2007年)を読む。

在日コリアンの「大量帰国事業」は、1959年に始まった。もっと正確には、93,340人(うち86,603人の朝鮮人と、その親戚縁者である日本人6,730人と中国人7人)が、高度経済成長期に入ろうとしていた時期に、「自発的な移住」として、北朝鮮へと渡った。その97パーセントは朝鮮半島南半分の出身であり、行き先は故郷でもなんでもなかった。
すなわち、祖国への帰国という表現は一面的なものに過ぎない。ほとんどの人が、長く暮らした土地を去り、新たな生活を希求したのだった。
強い牽引力として、金日成の意向による北朝鮮側からのキャンペーンがあった。情報がほとんど入手できない時代にあって、宣伝において展開される世界は夢の生活でもあった。菊池嘉晃『北朝鮮帰国事業 「壮大な拉致」か「追放」か』(中公新書、2009年)においても、最大の原因を、送り出した日本側にではなく、呼んだ北朝鮮側に見ている。
しかし、著者が赤十字に残された資料を丹念に読み解いた結果は、1955年頃からの、日本赤十字社と日本政府との緊密な連携による「追い出し活動」こそが実を結んだというものであった。
植民地朝鮮から移住した(あるいは実質的に強制連行された)人びとは、解放を迎えたところで、そう簡単に生活を棄て、住む土地を離れることができるわけもない。やがて済州島四・三事件(1948年)があり、朝鮮戦争(1950年-)があり、少なくない者にとって韓国への渡航は死を意味した。そして日本の再独立(1952年-)に伴い、日本政府は、一方的に在日コリアンの国籍を剥奪した。かれらは「国民」に与えられる権利を持たず、また社会からの差別もあって、貧困に苦しむこととなった。その結果、政府の生活保護費がふくれあがった。
すなわち、「大量帰国事業」とは、日本側の経済的負担と、不満から予想された政治的不安とを解決するための、「排除」に他ならなかった―――「慈善」という衣をまとっての。メディアもこれに加担した。さまざまな側面において、現在のレイシズム的な言説と地続きの歴史であるということができる。
一方、北朝鮮側は、この事業を通じて、日米韓の間に楔を打ち込みたかった。また、朝鮮戦争において出兵してきた中国軍が撤退して、不安を抱えていたという事情もあった。そして、「帰国」後、キャンペーンに展開されていた豊かな生活を送ることができたのはごく一部の者だけで、ある者はスパイとして処され、ある者は鉱山など厳しい労働に就くことを余儀なくされた。何という皮肉であったのか。
●参照
○菊池嘉晃『北朝鮮帰国事業』、50年近く前のピースの空箱と色褪せた写真
○和田春樹『北朝鮮現代史』
○近藤大介さん講演「急展開する中国と北朝鮮」
○高崎宗司『検証 日朝検証』 猿芝居の防衛、政府の御用広報機関となったメディア
○支配のためでない、パラレルな歴史観 保苅実『ラディカル・オーラル・ヒストリー』(本書で紹介)