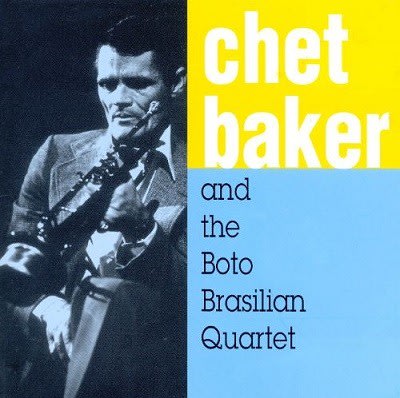サックスのフローリアン・ヴァルターがダンスと共演するというので、ボンのSchauspielに足を運んだ(2019/5/29)。

"Zwischenspiel"
Choreografie: Bärbel Stenzenberger
Tanz: Giovannina Sequeira, Vincent Wodrich
"Quotenfrau"
Choreografie & Tanz: Elisabeth Kindler-Abali
"Silente"
Choreografie: Lucia Piquero
Tanz: Melanie López López
"bo komplex"
Ein Tanz mit dem Saxophonisten und Komponisten Florian Walter
"ANDY - SUPERSTAR!"
Choreografie: Jutta Ebnother / Orkan Dann
"Paint It Black"
Musik: The Rolling Stones
Tanz: Fem Rosa Has, Gisela de Paz Solvas, Vasco Ventura, Tommaso Bucciero
"Knockin’ on Heaven’s Door"
Musik: Bob Dylan
Tanz: Vasco Ventura, Tommaso Bucciero Choreografie: Jutta Ebnother
開演前にフローリアンとあれこれ話していると、かれはそのまま余裕で客席に座り、サックスを練習し始めた。そのうち観客も入ってくるからと言われて何のことかと思っていると、確かに、フローリアンのアルトが鳴る中で人びとが客席に着いている。やがてステージ上でダンスが始まり、静かな踊りの中でのアルトの響きがマッチした。音発生器が単独で成立するのも、間違いなく、フローリアンの卓越した技術があってこそだ。フローリアンは吹きながらステージに登る。
男女の奇妙な社交をカリカチュア化したような動き、それは幕が半分閉じられてもその合間で続く。虚実あい混じった雰囲気が面白い。
虚実といえば、ものすごい勢いで服を脱ぎ続けるダンスも、またがんじがらめの制約の中で身体のバランスを取るようなダンスも、また都市生活の中で崩壊する男のダンスも、その狭間にあって苦しみ生きる者の表現のようにみえた。
飽きずに解釈を愉しめるオムニバス的なエンタテインメント。
終わってから一杯やって、ダンサーのひとりと、フローリアンと、かれにユニークな楽器を持ってきた友人と、一緒に電車に乗って帰った。齋藤徹さんのこと、ピーター・エヴァンスやアクセル・ドゥナーのトランペット技術、奇怪な形のトランペットにクラのマウスピースを付けた楽器、7月の日本でのギグ、他の楽器とアルトとの相性、クリス・ピッツィオコスとのデュオ録音(もうすぐ出るそうだ)、ジャズドラマーの弟のことなど、もろもろ話しているうちに駅に着いた。









Fuji X-E2、XF60mmF2.4
●フローリアン・ヴァルター
Ten meeting vol.2@阿佐ヶ谷天(フローリアン・ヴァルター)(2018年)
フローリアン・ヴァルター+直江実樹+橋本孝之+川島誠@東北沢OTOOTO(2018年)
フローリアン・ヴァルター+照内央晴+方波見智子+加藤綾子+田中奈美@なってるハウス(2017年)
フローリアン・ヴァルター『Bruit / Botanik』(2016年)
アキム・ツェペツァウアー+フローリアン・ヴァルター『Hell // Bruit』(2015年)