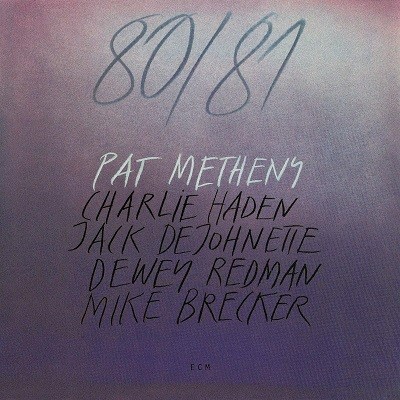座・高円寺にて、シュリッペンバッハ・トリオ+高瀬アキ「冬の旅:日本編」(2018/11/23)。

(写真撮影は許可を得ています)
Alexander von Schloppenbach (p)
Evan Parker (ts)
Paul Lytton (ds)
Aki Takase 高瀬アキ (p)
何しろヨーロッパの生きる伝説シュリッペンバッハ・トリオである。1997年の来日時には六本木のロマーニッシェス・カフェと新宿ピットインに観に行ったが、その際は、エヴァン・パーカーの急な事情で、ルディ・マハールが代役に入った。当時新鋭のマハールは前年のベルリン・コンテンポラリー・ジャズ・オーケストラで観ており(エヴァン・パーカーの横にいた)、もの凄くユニークなプレイで印象的だったから、それはそれで嬉しかったのだけれど、やはり、エヴァンが吹くトリオを観たかった。今回の企画に奔走なさった横井一江さん曰く「21年目のリベンジ」(だったかな)。
ただ、ドラマーはオリジナルメンバーのパウル・ローフェンスではなくポール・リットン。ローフェンスには長時間のフライトが厳しいというのだが、最近、喜多直毅さんもドイツでそのプレイを観て良かったと書いており、元気ではあるみたいだ。ローフェンスはいつもワイシャツにネクタイのトレードマーク、21年前にサインをもらったらジャケットの表から裏にまではみ出させる素敵な人だった。ともかく、リットンだってたいへんなドラマーであり、かれが目玉であってもおかしくはない。
第1部はシュリッペンバッハと高瀬アキの連弾とそれぞれのソロ。冒頭は「Steinblock」、いきなりふたりの違いが明らかになる。アレックスは細かな音を執拗に並べるスタイルであり、アキさんは強弱を物語的に付ける。アレックスがこれをキープし、肘も使って嬉しくなった。21年前の印象に強い怒涛のエネルギーは弱まっているが、コアは変わらない。
次に「Zankapfel」、これも先の曲と同様にデュオ盤『Iron Wedding』に収録されている。何か林檎のひとつだろうと思っていたのだが、アキさんの解説によると「喧嘩の種」とでもいった意味。そうか「zank」は「喧嘩」か。演奏もそれをイメージさせるように、互いに介入干渉しあうように進められ、アキさんの内部奏法もあり、そのうちリズムが狂ってブギウギのようになったりもした。
3曲目はアキさんのソロでオリジナル「Cherry-Sakura」。デイヴィッド・マレイとの共演盤があり聴いてみたい。坂田明さんとも共演しているという。これが素晴らしい演奏で、力強く抒情的でもあり、高瀬アキというピアニストの特徴が表出しているように聴こえた。アキさんのブルースといってもいいのではないかと思えた。終演後ロビーでたまたま隣にいた女性と話していたら、この曲が本当に良かったと強調していた。
変わってアレックスのソロ。リズムも選び出される音も発散し、その細かな差異に美のようなものが隠しようもなく出てくる。インプロからふと間を置いてセロニアス・モンクの「Light Blue」、「Smoke」とつなぎ、そして、ハービー・ニコルスの「Every Cloud」。ニコルス!いや驚くことはない。最近の作品『Jazz Now! - Live at Theater Gütersloh』でも演奏している。いい曲だな。
そしてまた連弾に戻った(曲名はわからない。アキさんは「砂漠の船」と言っていた)。アキさんの手拍子、アレックスの低音からはじめ、オリエンタルなコードを使った。アレックスは揺れ動き、アキさんは太くブルージーに攻めた。続く曲では、アキさんはピアノ内部の弦にあれこれを挟んだようで、それによる異音と力強さとを共存させ、空間をアレックスが埋めていった。
第2部は待ってました、シュリッペンバッハ・トリオ。
エヴァン・パーカーはこの日、テナーだけを使った。ソプラノとなると空を飛ぶ小鳥のごとき独特の循環呼吸によるエヴァン・サウンドを聴けるのに対し、テナーだと太くうねるような、ときにブルージーでもあるという、これまでエヴァンを観てきた印象。ここでは、もっと表現力が豊かだった。
また、ポール・リットンの音はドライであり、サンドバックを思わせるデッドな感覚もあった。スティックの素材感が出ているとも言えた。多数の叩き物を横に置き、ブラシではタテにヨコに音の手を伸ばし、実に幅広い音を出し、知的にトリオのサウンドを覆い尽くした。(わたしとしては絶賛)
アレックスの介入、エヴァンのうねり、ポールの破裂。アレックスのグルーヴ、エヴァンのゆったりさ、ポールの滋味あるカラフルさ。3人が別種のノリで音楽を相互に駆動し続けた。これを快楽と言わずして何と言おう。
ポール・リットンはここではじめて擦りを披露。スティックでシンバルの周囲を円環を描く技をみせた。また、細いスティックを取り、それに見合った音を出した。アレックスの再介入、エヴァンの循環、ポールの響き。アレックスの弾いたフレーズに間髪を入れず呼応し、エヴァンが同じフレーズを吹く場面もあった。演奏は激化してきて、ポールはドラムの上に円盤を置いて跳躍させもした。そして潮目が変わり、アレックスの轟音と弦のしなり、エヴァンの重音、ポールのノイズ。
ここでアキさんが加わり、アレックスとの連弾で、実に愉しそうに弾く。呼応して全員がまるで空を飛翔しているように感じる。
アンコールは連弾のピアノデュオ。アレックスは小唄のように弾き始め、アキさんは手拍子。ラグタイムのようだった。






Fuji X-E2、XF60mmF2.4、7artisans12mmF2.8
●アレクサンダー・フォン・シュリッペンバッハ
アレクサンダー・フォン・シュリッペンバッハ『Jazz Now! - Live at Theater Gütersloh』(2015年)
アレクサンダー・フォン・シュリッペンバッハ『ライヴ・イン・ベルリン』(2008年)
シュリッペンバッハ・トリオ『Gold is Where You Find It』(2008年)
アレクサンダー・フォン・シュリッペンバッハ+高瀬アキ『Live at Cafe Amores』(JazzTokyo)(1995年)
シュリッペンバッハ・トリオ『Detto Fra Di Noi / Live in Pisa 1981』(1981年)
シュリッペンバッハ・トリオ『First Recordings』(1972年)
ギュンター・ハンペル『Heartplants』(1965年)
●エヴァン・パーカー
デイヴ・ホランド『Uncharted Territories』(2018年)
エヴァン・パーカー@稲毛Candy(2016年)
エヴァン・パーカー+高橋悠治@ホール・エッグファーム(2016年)
エヴァン・パーカー@スーパーデラックス(2016年)
エヴァン・パーカー、イクエ・モリ、シルヴィー・クルボアジェ、マーク・フェルドマン@Roulette(2015年)
Rocket Science変形版@The Stone(2015年)
エヴァン・パーカー US Electro-Acoustic Ensemble@The Stone(2015年)
シルヴィー・クルボアジェ+マーク・フェルドマン+エヴァン・パーカー+イクエ・モリ『Miller's Tale』、エヴァン・パーカー+シルヴィー・クルボアジェ『Either Or End』(2015年)
エヴァン・パーカー+土取利行+ウィリアム・パーカー『The Flow of Spirit』(2015年)
エヴァン・パーカー+土取利行+ウィリアム・パーカー(超フリージャズコンサートツアー)@草月ホール(2015年)
マット・マネリ+エヴァン・パーカー+ルシアン・バン『Sounding Tears』(2014年)
エヴァン・パーカー ElectroAcoustic Septet『Seven』(2014年)
エヴァン・パーカー+ジョン・エドワーズ+クリス・コルサーノ『The Hurrah』(2014年)
ジョン・エスクリート『Sound, Space and Structures』(2013年)
『Rocket Science』(2012年)
ペーター・ブロッツマンの映像『Soldier of the Road』(2011年)
ブッチ・モリス『Possible Universe / Conduction 192』(2010年)
エヴァン・パーカー+オッキュン・リー+ピーター・エヴァンス『The Bleeding Edge』(2010年)
ハン・ベニンク『Hazentijd』(2009年)
アレクサンダー・フォン・シュリッペンバッハ『ライヴ・イン・ベルリン』(2008年)
シュリッペンバッハ・トリオ『Gold is Where You Find It』(2008年)
エヴァン・パーカー+ノエル・アクショテ+ポール・ロジャース+マーク・サンダース『Somewhere Bi-Lingual』、『Paris 1997』(1997年)
エヴァン・パーカー+ネッド・ローゼンバーグ『Monkey Puzzle』(1997年)
エヴァン・パーカー+吉沢元治『Two Chaps』(1996年)
サインホ・ナムチラックとサックスとのデュオ(1992-96年)
ペーター・コヴァルトのソロ、デュオ(1981-98年)
スティーヴ・レイシー+エヴァン・パーカー『Chirps』(1985年)
エヴァン・パーカー『残像』(1982年)
シュリッペンバッハ・トリオ『Detto Fra Di Noi / Live in Pisa 1981』(1981年)
カンパニー『Fables』(1980年)
シュリッペンバッハ・トリオ『First Recordings』(1972年)
●ポール・リットン
ガイ+クリスペル+リットン『Deep Memory』(2015年)
ヨアヒム・バーデンホルスト+ジョン・ブッチャー+ポール・リットン『Nachitigall』(2013年)
ネイト・ウーリー『Seven Storey Mountain III and IV』(2011、13年)
●高瀬アキ
高瀬アキ+佐藤允彦@渋谷・公園通りクラシックス(2016年)
アンサンブル・ゾネ『飛ぶ教室は 今』(2015年)
高瀬アキ『St. Louis Blues』(2001年)
アレクサンダー・フォン・シュリッペンバッハ+高瀬アキ『Live at Cafe Amores』(JazzTokyo)(1995年)
高瀬アキ『Oriental Express』(1994年)