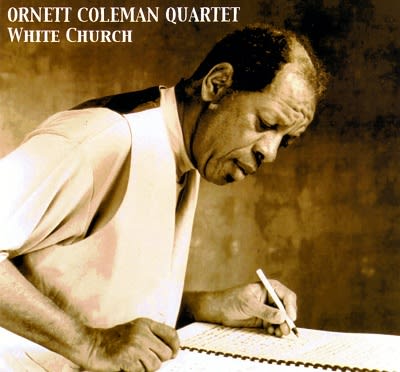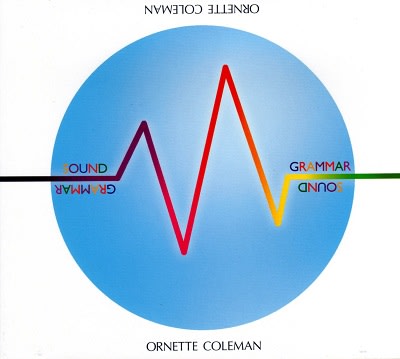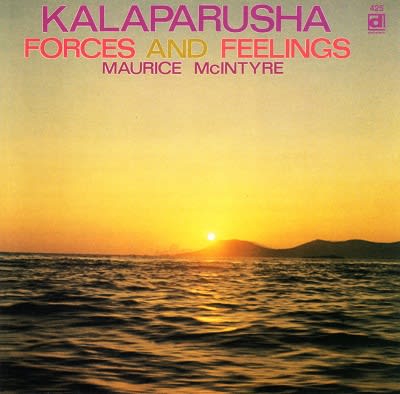「6.15沖縄意見広告運動報告集会」(2012/6/15、連合会館)に足を運んだ。
沖縄意見広告という形で米軍基地撤去を訴え、世論を喚起する運動であり、現在は第三期。この5月には沖縄の2紙(琉球新報、沖縄タイムス)、朝日新聞全国版に掲載されている。また、その対象に原子力をも含めるようになっている。
広い会場はかなりの人で埋まっていた。同時に行われた官邸前アピールとずれていれば、さらに多かったのだろう。年齢層は相変わらず相当に高い。若い層は、デモには多くても、このようなイベント性のない場には少ないということだ。
司会は上原公子さん(元国立市長)。脱原発の盛り上がりに伴い平和集会が減ったと指摘しつつも、基地も原発も基本的人権の侵害という点で共通しているのだと述べた。
次に挨拶に立った上原成信さん(沖縄・一坪反戦地主)。『那覇軍港に沈んだふるさと』(>> リンク)の著書がある。上原さんは相変わらず飄々としてユーモラスである。特に、「2プラス2」でも、オバマ・野田共同声明でも、同じことを繰り返すばかりであり、両政府ともどうすればいいかわからない状況なのだとした。それゆえ、辺野古や高江同様に、普天間も人間の鎖で反対すれば、日本政府を変えられると強調した。

この後登場した各氏の発言は以下のようなもの。
■ 山内徳信(参議院議員)
○今年の1月に沖縄市民訪米団の団長として参加した。米国では、多くの上下院議員らと会った。
○ダニエル・イノウエ議員(民主党のNo.3)は、日本政府が「6月の沖縄県議会選挙を待て。必ず日本政府の望む方向に決まる」と言ってきたが本当か、と訊ねた。それに対し、野党多数となるのは間違いないと応えた。それは実現した。
○県議選の結果を受けて、仲井真知事はうつむいていた。日本政府に新法をつくらせ、満額回答に近い振興予算も得ていたから、あまりにも意外だったのだろう。
○ガンジーやキング牧師の例を挙げるまでもなく、闘いは民衆が立ちあがって行うものだ。非民主的な政治はもはや通らないということをわからせてやりたい。
○これは憲法を実践させていく闘いである。それにより、多くの国が手本とする国をつくりたい。
退席するとき、鎌田慧さんが立ちあがって握手したのが印象的だった。

■ 伊波洋一(元宜野湾市長)
司会の上原さんは、「この前の知事選で伊波さんが勝っていればどんなに沖縄は変わっただろうと思うと、残念でならない」と紹介した。
○旧安保条約から60年あまり、沖縄「返還」から40年。まだ、沖縄は米軍占領下にある。
○日米安保は日本を守るためではなく、米国の世界戦略のためにある。日本を攻める国はないにも関わらず、虚構をつくりだしている。
○米軍は基地の自由使用権を持ち、米兵が問題を起こしても、地位協定によってほとんど裁かれない。これほど住みやすいところはない。
○米軍は日本の上のどこであっても、いつ飛んでもよい。日本の空は米国のものである。
○日本の安全政策に関しては、日本政府は米国の傀儡政権となっている。
○あまり知られていないことだが、日米首脳会談(2012/4/30)を前に、普天間の固定化、辺野古とグアム移転の分離を「2プラス2」の合意として日米政府が発表しようとしたところ(2012/4/25)、3ヶ月かけて準備されたものにも関わらず、直前に突然キャンセルされた。辺野古移設に反対する米国上院議員レビン、マケイン、ウェブ各氏の反対のためであり、この3名は、国務長官に対し、議会を無視するなと圧力をかけたのだった。それは急遽文言に反映された。
○普天間飛行場は、日本の航空法上では飛行場ではない。何ら周辺の安全対策をしていないからだ。米軍は、フェンスの内部は米国法の規制を厳に運用し、危険を除去するが、フェンスの外はまったく関知しない。
○例えば、米国のミラマー基地は、普天間の20倍、宜野湾市の5倍の面積を持ち、旋回訓練コースはすべて基地内に含まれている。一方、普天間の飛行ルートの下は住宅ばかりである。ここに、さらに危険なオスプレイが配備されたらどうなるのか。
○従って、日米安保そのものが日本の安全を守るものではないし、沖縄はいまだ占領下だということがいえる。
○2030年には、中国の経済は米国の1.5倍、日本の4倍にもなる。その時代にも、日本は中国と対峙するのか。それが国益なのか。

■ 安次冨浩(名護・ヘリ基地反対協議会共同代表)
常に辺野古のテント内にいる安次冨さんである。
○辺野古での座り込みは2980日を数え、この7月5日には3000日を迎えるという。いまでは平和学習の場にもなっている。それだけ日本・米国と対峙し、辺野古の新基地を止めているのだと自負している。
○沖縄の2紙の一面に「オスプレイが沖縄全域を飛行」と報じられた翌日に、オスプレイがフロリダで墜落した。皮肉なものだ。
○フロリダでの墜落も、その下が米軍基地であったから、被害が最小限で済んだのだ。これが沖縄ならばどこに落ちるか。
○普天間では、オスプレイは輸送機CH46Eの後継機として位置づけられている(軍によって呼び名も用途も異なる)。CH46Eは墜落しないがオスプレイは墜落事故多数。しかし、まやかしの計算により、日米政府とも「事故率は少ない」と言っている。
○フロリダの事故により、7月の岩国、8月の普天間というオスプレイ配備計画は当面見送られる可能性が高くなった。しかし、森本敏大臣は、配備計画は続けるなどと発言している。
○那覇市長は、那覇軍港への搬入と組み立ては許されないとしている。一方の岩国では、基地の軍民共用化に伴い、民間の飛行場の予算を了解させるための条件(アメ)として、オスプレイ受け入れを呑んだ。しかし事故によって、一転拒否に至っている。
○沖縄県議選は、野党が過半数を占めるという結果になった。民主党が大きく議席を減らしたのは、県民の不信感による。
○県議会は6月26日から開かれる。そのときから要請をはじめ、7月一杯にはオスプレイの全会一致での反対決議を実現させたい。さらに、知事を含める形での県民大会を開きたい。
○仲井真知事と宜野湾市長とは、直接防衛省に赴き、オスプレイ受け入れはムリだと伝えるだろう。
○これまで、日本政府の存在が、米国との交渉を分断し、邪魔するという機能しか果たしてこなかった。これからは、日本政府をあてにせず、米国との直接交渉が望ましい。その意味で、1月の訪米は意義深いものだった。外交も自己決定権の原則のもと行わないと、沖縄問題は解決しない。
○オスプレイは月に2-3回は「本土」に飛ぶという。決して沖縄だけの問題ではない。

■ 鎌田慧(さようなら原発1000万人署名活動)
わたしも深く敬愛するジャーナリストである。
○この日の午前中、740万筆の署名を藤村官房長官に届けた。 この中には、原発に直接は関連しないにも関わらず、島民の半分近くが署名した竹富島の約150筆も含まれている。この国を変え、圧倒的な力の下から人々を解放し、国民主権を実現したいという力である。
○大飯原発の再稼働が、たかだか4人程度により、密室内で決定されそうになっている。議会でもない。政治決定は国民が行うものであり、決して認められない。
○いまではどこにも責任がない状況だ。藤村官房長官も、横路議長も、輿石議員も、「重みはよくわかる」と言う。しかし、誰も決定をしない。誰が主権を持っているのだろうか。私たちが「イヤだ」と言うべきなのだ。その意味で、7月16日の10万人集会を必ず成功させたい。
○東日本大震災の原発事故から、原子力安全保安院にせよ、電力の供給・経営体制にせよ、安全装置の設置にせよ、何一つ状況が変わっていないのに、もう一度稼働しようということだ。何の反省もみられない。
○原発も沖縄基地も危険にも関わらず、政府は安全だと言い続けてきた。例えば、2年前、高江の公民館における説明会では、住民が訊ねても、防衛局はオスプレイ配備計画があることをいっさい認めなかった。民主主義どころでない、住民無視である。
○原発を再稼働させてほしいとする地方の声もある。これは原発というモノカルチャーを押し付けられてきたことによるわけであり、彼らも犠牲者なのである。原発に依存しない国をつくりたい。
○電力不足や安全神話など、ウソに立脚した政治が行われてきた。これを、真っ当な、人間の声が反映された政治にしたい。

■ 椎名千恵子(原発いらない福島の女たちの会)
○日本には、原子力ムラがあるどころか、原子力帝国になっている。
○辺野古では、現地のオバアに、「福島と沖縄は同じだよねえ」と声をかけられた。シンプルで核心をついた言葉だと思った。
○原発は「犠牲のシステム」(高橋哲哉)(>> リンク)である。犠牲なしには生み出されないし、維持もされない。しかし、今や、その犠牲さえ壊れてしまう状況である。
○福島原発を廃炉にしない動きがある。また、福島県民を福島に居させ続けたい力が働いている。
○闇の中から光をつかみとるべく頑張っている。責任を取らない日本の体質を変える国民運動にしていきたい。
○診療所の建設運動にも協力してほしい。

以上、各氏の報告と問題提起のあと、さまざまな立場からの連帯挨拶があった。
藤本泰成さん(原水禁・平和フォーラム事務局長)は、「合意なき国策」の異常さを主張した。
渕上太郎さん(経産省前テントひろば)は、 この同じ時間に、官邸前アピールのため1万人以上が集まっているとの速報とともに、組織上の動員ではないという点で画期的だとした。
吉田正司さんの代役(沖縄・一坪反戦地主会関東ブロック)は、意見広告をヤマトゥの新聞すべてに掲載してほしいと主張した。
吉沢弘久さん(伊達判決を生かす会)は、基地そのものが違憲だとする伊達判決(東京地裁、1959年)のあと、立川基地が撤去されたことの意義を述べた。
野平晋作さん(JUCON/沖縄のための日米市民ネットワーク)は、現在、3mものオスプレイが子供たちの上に墜落する模型をつくっており、これを多くの人に撮ってもらい、twitterやfacebookで拡散させることによって、「本土」の世論を喚起する計画だと述べた。(一方、会場からは、なぜ子供の上に落とすのか、やりすぎだとの声があがった。わたしは地獄絵のヴィジュアライゼーションという意義で賛成である)
広告運動の発起人からは、これから「第四期」に入り、今後は米国やその他米軍基地で苦しむ国々にも働き掛けること、安保を運動の中心に据えることなどの報告があった。



●参照
○オスプレイの模型
○60年目の「沖縄デー」に植民地支配と日米安保を問う
○金城実+鎌田慧+辛淑玉+石川文洋「差別の構造―沖縄という現場」
○辺野古の似非アセスにおいて評価書強行提出
○前泊博盛『沖縄と米軍基地』
○屋良朝博『砂上の同盟 米軍再編が明かすウソ』
○渡辺豪『「アメとムチ」の構図』
○シンポジウム 普天間―いま日本の選択を考える(1)(2)(3)(4)(5)(6)
○押しつけられた常識を覆す
○『世界』の「普天間移設問題の真実」特集
○大田昌秀『こんな沖縄に誰がした 普天間移設問題―最善・最短の解決策』
○鎌田慧『沖縄 抵抗と希望の島』
○アラン・ネルソン『元米海兵隊員の語る戦争と平和』
○二度目の辺野古
○2010年8月、高江
○高江・辺野古訪問記(2) 辺野古、ジュゴンの見える丘
○高江・辺野古訪問記(1) 高江
○沖縄・高江へのヘリパッド建設反対!緊急集会
○ヘリパッドいらない東京集会
○今こそ沖縄の基地強化をとめよう!11・28集会(1)
○今こそ沖縄の基地強化をとめよう!11・28集会(2)
○ゆんたく高江、『ゆんたんざ沖縄』
○終戦の日に、『基地815』
○『基地はいらない、どこにも』
○「やんばるの森を守ろう!米軍ヘリパッド建設を止めよう!!」集会(5年前、すでにオスプレイは大問題として認識されている)
○『核分裂過程』、六ヶ所村関連の講演(菊川慶子、鎌田慧、鎌仲ひとみ)