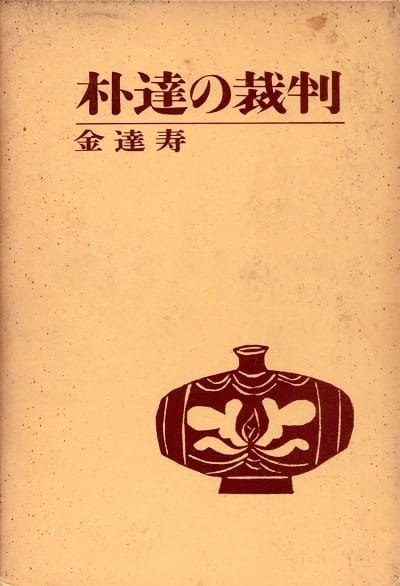デイビッド・ウォルトナー=テーブス『排泄物と文明』(築地書館、原著2013年)を読む。

要するに、ウンコの本である。原題は『The Origin of Feces』(『糞便の起源』)、つまりチャールズ・ダーウィン『The Origin of Species』をパロッている。
人はウンコが嫌いで好きである。認めてはいるが視ていない。有用であり有害である。ヘンにタブーだからヘンなことになる。
所詮は、消化しきれなかった食べ物と、水と、バクテリアの塊である。それが、生態系の主役のひとつでもある。すなわち、ウンコを真っ当に評価して扱わないことには、食糧問題も公衆衛生も解決できない。著者がユーモラスにたくさんのネタとともに迫るのは、まさにそのことである。
読みながら思い出したこと。
わたしは腹が弱い。真っ青になって必死に走ったのは、日本ばかりではない。バンコクのスーパーマーケット(綺麗なトイレだった)。ハノイの空港(タクシーで冷房に当たりすぎた)。インドネシアの離島の空港(あまりにも汚く、水も出なかった)。ネパール・ポカラの街(買い物をしている途中だったので、支払う前に預けてまた戻った)。紹興(間に合って出ていくと、仲間に万歳三唱をされた)。・・・思い出せばまだありそうだ。
これがあまりにも酷い("OPP")と、トイレに通い詰めることになる。イエメン・サヌアの宿では、本来使ってはならない紙をたくさん使ってしまったために、トイレが詰まったようで、掃除をしていた男に、お前だろう、わかっているぞと言わんばかりの形相で睨まれてしまった。用を足したあとに紙でなくバケツの水を使う文化は多いのである。そんなわけで、本書にもイエメンについての言及があってドキリとした。イエメンが「近代化」されると水洗トイレが増え、サヌアでは水不足と地下水位の低下が起きているのだという。まるで「近代化」の先兵としてトラブルを起こしたような気がしてくる。申し訳ない。
そのあとも下痢は止まらず、紅海へと向かう車のなかで「ハンマーム!」と言って止めてもらっては、サボテンの陰に隠れた。そのサボテンは他よりも大きくなっただろうか。まるで生態系に悪影響を与えたような・・・それはないか。(ちなみに、「ハンマーム」という言葉は、英語の「バスルーム」と同様に、風呂のことも指す。)
もうひとつ思い出したこと。
インド・ムンバイは海辺の街。早朝に散歩して海に着いたところ、たくさんの男たちが佇んでいる。みんな、しゃがんでいる。仰天した。ここまで多ければ生態系の一部として評価すべきものだろう(どちらの影響かわからないが)。本書でムンバイの話として示しているのは、映画『スラムドッグ$ミリオネア』の中で、突然あらわれた映画スターのサインが欲しいがために、肥溜めに飛び込んだくだり。そのことだって、ウンコの管理や処理という問題を垣間見せてくれるものなのである。
もうひとつ・・・。キリがない。このように恥ずかしい話のネタとして扱われることが、ウンコの置かれた状況を示すものでもあるだろう。ウンコを直視すべし。