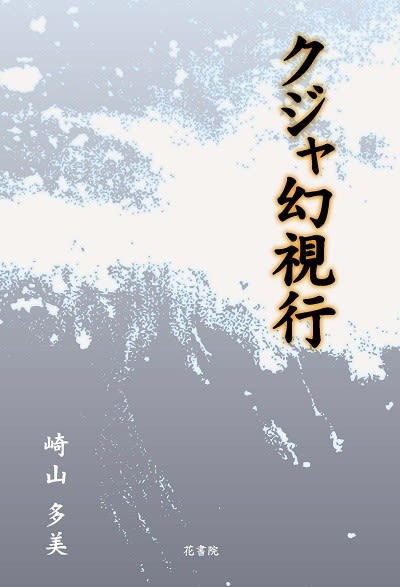向島ゆり子+関島岳郎+中尾勘二『星空音楽會 Musica En Compostela』(off note、2010年)。入手したのは割と最近だが、大好きな盤なのだ。気持ちを落ち着かせるためにクアラルンプールのホテルでも聴いていた。
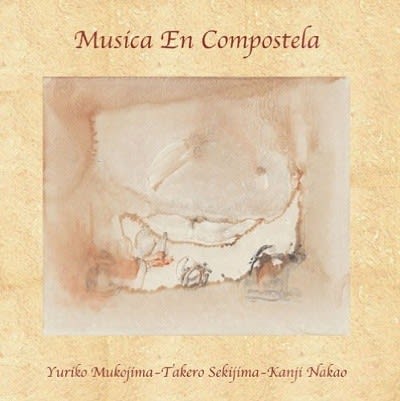
Yuriko Mukojima 向島ゆり子 (vln)
Takero Sekijima 関島岳郎 (tuba, recorder)
Kanji Nakao 中尾勘二 (ss, cl, tb)
渋いというのか音楽そのものというのか、そのような3人による音楽。言うまでもなく関島、中尾の両氏はコンポステラや、コンポステラを想ってのフォトンのメンバーでもあった。そしてもうひとりは、もちろん故・篠田昌已でも、林栄一でもなく、向島ゆり子。
コンポステラが演奏した「同志は倒れぬ」、林栄一の名曲「ナーダム」を聴いていると、あああ、泣きそうになる。なんて素晴らしい音楽だろう。こういうものに接すると妙にロマンチックになって大言壮語しそうになってしまう。
途中の「煙」で、観客か演奏者か、くしゃみや咳が拾われていることにも親しみを覚える。(ところで、「くつやのマルチン」はメロディのせいかチューバの効果か、『ウルトラセブン』の映像が浮かんできてしかたがない。)
大工哲弘一人唄会@浅草木馬亭(2017年)
唖蝉坊と沖縄@韓国YMCA(2017年)
向島ゆり子@裏窓(2016年)
ジャスト・オフ『The House of Wasps』(2015年)
川下直広『漂浪者の肖像』(2005年)
●関島岳郎
渋谷毅エッセンシャル・エリントン@新宿ピットイン(2015年)
ふいご(2008年)
川下直広『漂浪者の肖像』(2005年)
船戸博史『Low Fish』(2004年)
『週刊金曜日』の高田渡特集(『貘』、1998年)
嘉手苅林次『My Sweet Home Koza』(1997年)
大島保克+オルケスタ・ボレ『今どぅ別り』 移民、棄民、基地(1997年)
●中尾勘二
グンジョーガクレヨン、INCAPACITANTS、.es@スーパーデラックス(2016年)
中尾勘二@裏窓(2015年)
ふいご(2008年)
川下直広『漂浪者の肖像』(2005年)
船戸博史『Low Fish』(2004年)
嘉手苅林次『My Sweet Home Koza』(1997年)
大島保克+オルケスタ・ボレ『今どぅ別り』 移民、棄民、基地(1997年)