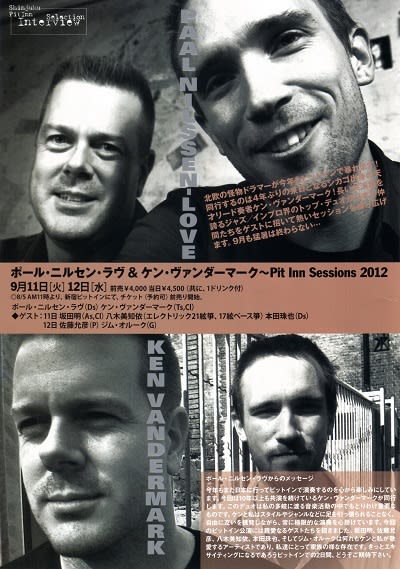ポール・オースター『Man in the Dark』(2008年)を、kobo touchで読む。
操作性にやや難があるkobo touchだが、英語ならばそれほどでもない。何より辞書機能が使いやすいのが良い。

突然、若い男ブリックが目覚めてみると、深い穴の中にいた。現れた男に、兵士として、ブリルというピューリッツァー賞も取った作家を殺せと命じられる。世界は別のアメリカであり、内戦の真っただ中なのだった。空腹で辿りついた街で、ブリックはようやく状況を把握する。彼が殺人を犯すのは、内戦を引き起こす原因を絶つためだという。拒めば、ブリックの家族は殺されてしまう。しばらくしてもとの家に戻ったブリックは、妻にことの次第を話すが、2日間も家を空けた男のたわごととして相手にしてもらえない。しかし、ネット検索すると、そのピューリッツァー作家は実在することがわかる。そして、殺人を命じた男たちが、早く義務を果たさないと殺すぞと現れる。
老いたブリルは、離婚した娘ミリアム、イラクで恋人を失った孫娘カティアと一緒に暮らしていた。自らも、離婚して何年かののちに再び同じ女性と再婚した過去を持っていた。ミリアムは、両親と同じく勢いで結婚し、失敗していた。カティアは、心の傷を癒すかのように、祖父ブリルと一緒にDVDの映画を観て感想を述べ合う毎日を送っていた。やがて、ブリルは、自分の過去について、明け透けに、カティアに話しはじめる。
これは、「別のアメリカ」があるというパラレルワールド小説である。それは理不尽で、極めて個人的な感情の集合からなる。ブリルの悔恨に満ちた告白に耳を傾けていると、何だか身につまされてしまう。
しかし、すべては謎のままだ。なぜこのような事態が起きたのかの説明はほとんどなされず、ふたつの話の流れは収斂しないままに終わる。最後のページを読み終えたあと、ええっ、これでおしまいなのかと吃驚させられた。いくらなんでも、読者を放り投げすぎだ。快感も悦楽もない。「9・11」以降の米国が、間違った世界へと突き進んでいることへの怒りは、嫌というほど伝わってくるのではあるが。
最近のオースター作品を読むたびに、彼の世界の特徴である後味の悪さだけがいびつに残る。もう、オースターを追いかけることもないだろう。
腹立たしいので、せめて気の効いたフレーズを抜きだしてみる。これも電子書籍のメリットだ。(英語学習のエッセイみたいだな。)
"Betty died of a broken heart. Some people laugh when they hear that phrase, but that's because they don't know anything about the world. People die of broken hearts."
「ベティは絶望によって死んだ。こう言うと笑う人もいるが、それは世界のことを何にも知らないからだ。人は絶望で死ぬんだ。」
(小津安二郎『東京物語』における原節子の台詞をもとに)
"Yes, Miriam, life is disappointing. But I also want you to be happy."
「そうだよ、ミリアム、人生はつまらないものだよ。だけど、君には幸せになってほしい」
(パラレルワールドからブリックを追ってきた同級生は、昔、憧れの的だった。妻を逃がしたブリックは、彼女との逢瀬を愉しむ)
"Let the man and the woman who met as children take mutual pleasure in their adult bodies. Let them climb into bed together and do what they will. Let them eat. Let them drink. Let them return to the bed and do what they will to every inch and orifice of their grown-up bodies. Life goes on, after all, even under the most painful circumstances, goes on until the end, and then it stops."
「子どもとして出会った男女に、大人の身体をもってお互いに悦ばせよ。ふたりにはベッドに入らせ、やりたいことをさせよ。食べさせよ。飲ませよ。そしてまたベッドに戻り、発育した身体のどんなところに対しても、やりたいようにさせよ。人生は続く。どんなに痛ましい状況でも、最後まで人生は続き、そして終わる。」
(ブリルが孫娘に対して述べる回想。若いころ、モラルをどのように扱っていたか)
"That was the fifties. Sex everywhere, but people closed their eyes and made believe it wasn't happening. In America anyway."
「それが50年代。セックスはいたるところにあって、しかし、人々は目を閉じてまるでそれがないかのように信じていた。アメリカのどこでもだ。」
(カティアの若い恋人がイラクに行くと聞いて、ブリルは思いとどまるよう説得する)
"... but the last time you were here, I remember you said that Bush should be thrown in jail --- along with Cheney, Rumsfeld, and the whole gang of fascist crooks who were running the country."
「・・・でも君はこのまえ、ブッシュを監獄に入れるべきだと言っていたじゃないか。チェイニーも、ラムズフェルドも、この国を動かしているファシストの犯罪者たち皆も。」
(ブリルやカティアは、カティアの恋人がテロリストに殺される映像を視てしまう。)
"Sleep is such a rare commodity in this house, ..."
「睡眠はこの家では稀少な商品となり、・・・」
"But there's one line ... one great line. I think it's as good as anything I've ever read.
Which one? She asks, turning to look at me.
As the weird world rolls on.
Miriam breaks into another big smile. I knew it, she says."
「でもあの一言が・・・偉大な一言がある。いままで読んだもののなかで一番良いものだと思う。
どの一言? 彼女は訊いて、わたしを見た。
”ひどい世界は過ぎ去っていく”
ミリアムはにっこり笑って言った。知ってるよ。」
●ポール・オースターの主要な小説のレビュー
○『Sunset Park』(2010年)
○『Invisible』(2009年)
○『Man in the Dark』(2008年)(本書)
○『Travels in the Scriptorium』(2007年)
○『ブルックリン・フォリーズ』(2005年)
○『オラクル・ナイト』(2003年)
○『幻影の書』(2002年)
○『ティンブクトゥ』(1999年)
○『ルル・オン・ザ・ブリッジ』(1998年)
○『スモーク&ブルー・イン・ザ・フェイス』(1995年)
○『ミスター・ヴァーティゴ』(1994年)
○『リヴァイアサン』(1992年)
○『偶然の音楽』(1990年)
○『ムーン・パレス』(1989年)
○『最後の物たちの国で』(1987年)
○『鍵のかかった部屋』(1986年)
○『幽霊たち』(1986年)
○『ガラスの街』(1985年)
○『孤独の発明』(1982年)