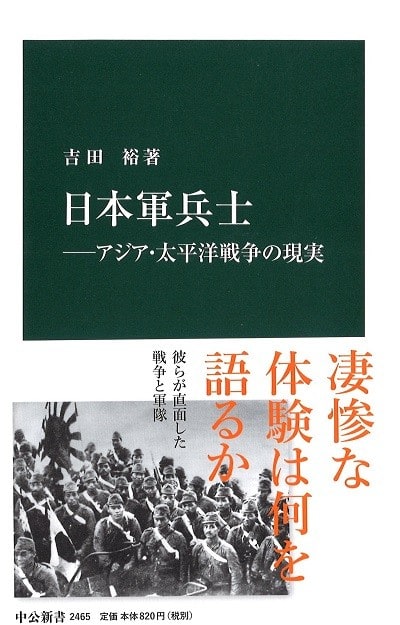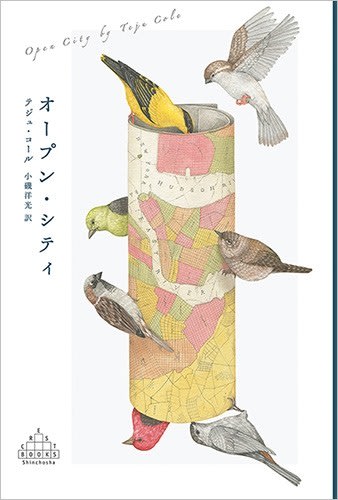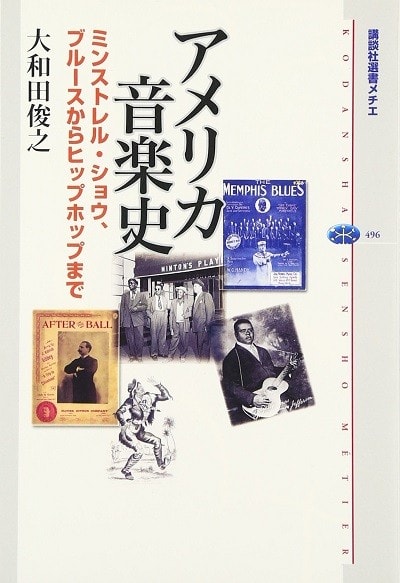『別冊ele-king カマシ・ワシントン/UKジャズの逆襲』に、もうひとつの特集として「変容するニューヨーク、ジャズの自由(フリー)」が組まれている。
つねに動き続ける先端ということもあってか、これまで、『JazzTokyo』の「Jazz Right Now」などネット媒体でその動きを見出すことが中心だった。あるいは、先端というフラグメンツとしては、ライヴ会場、音源の共有区間、ミュージシャンやリスナーが発信するSNSなどが重要となっている。今回紙媒体でこのような形になったことはとてもわくわくすることである。そしてこれも現在の断面ということがまた面白い。

まだ流し読みしただけだが、執筆各氏の論考や発言がどれも興味深く、あらたな視点をいちいち提示してくれている。中でも、時間軸でも音楽領域でも特定することが困難であり、越境性や並行性を無視することの困難さが、各氏の共通した指摘であるように読めた。
今回、細田成嗣さんを中心に、根田恵多さん、定淳志さん、それから不肖わたし(齊藤聡)で、上記「Jazz Right Now」を大きく意識しつつ、NYフリー・即興シーンの重要人物のマッピングを試み、あわせて全員で合計30枚のディスクレビューを行った。
越境性と並行性がある以上、このマッピングは非常に難しく、恣意的な思い入れをベースにした四者の「ああでもない」、「こうしたらどうか」、「この視点が大事なんだ!」、「この人がいない!」、「ずらそうぜ?」といった解のない議論を続けることとなった。つまりとても面白かった。そんなわけで、おそらくツッコミどころが少なくないが、そこに価値があるのであり、今後聴いていくときにも何かのきっかけとなるのではないかと話している。NYか東京ででも、登場人物に「これどう思う?」と見せてみるのが楽しみである。
なおわたしが書いたディスクレビューは、ジャック・デジョネット、ジョナサン・フィンレイソン、Mostly Other People Do The Killing、ブランドン・シーブルック、ジェイミー・ブランチ、Farmers by Nature、アイヴィン・オプスヴィーク、ドレ・ホチェヴァーの8枚。
実は「青田買い」枠で新進気鋭の期待できるミュージシャンが参加した盤を各人1枚入れようということになり、わたしは中国出身のブライアン・キューをホチェヴァーの盤参加ということで入れた(本人曰く、リーダー作の予定もある)。定さんはウィル・メイソン、根田さんはジェレマイア・サイマーマン、細田さんはラファエル・マルフリート。