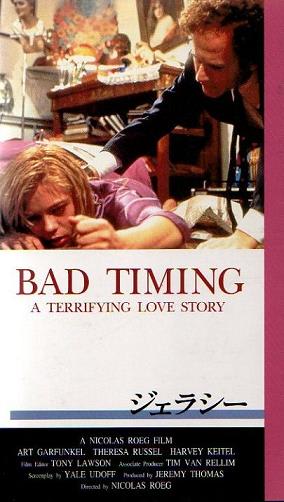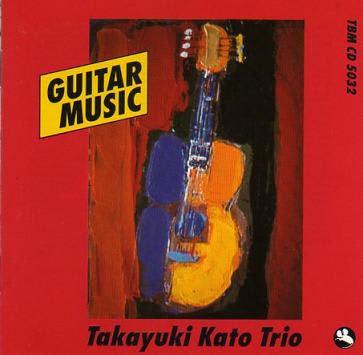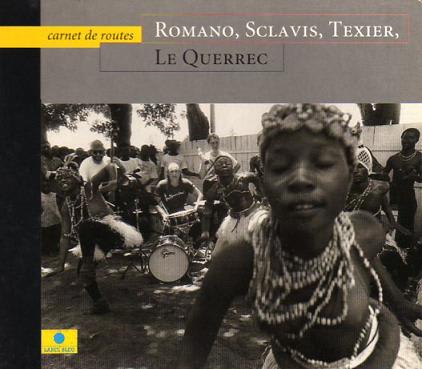魚住昭『野中広務 差別と権力』(講談社文庫、2006年)が、麻生首相就任の前後から取り沙汰されている。

問題となっているのは、以下のくだりだ。
「永田町ほど差別意識の強い世界はない。彼が政界の出世階段を上がるたびに、それを妬む者たちは陰で野中の出自を問題にした。総裁選の最中にある有力代議士は私に言った。
「野中というのは総理になれるような種類の人間じゃないんだ」
自民党代議士の証言によると、総裁選に立候補した元経企庁長官の麻生太郎は党大会の前日に開かれた大勇会(河野グループ)の会合で野中の名前を挙げながら、
「あんな出身者を日本の総理にはできないわなあ」
と言い放った。」
そして、小泉首相の出現により辞任する野中は、最後の自民党総務会で発言する。
「「総務大臣に予定されておる麻生政調会長。あなたは大勇会の会合で「野中のような出身者を日本の総理にはできないわなあ」とおっしゃった。そのことを、私は大勇会の三人のメンバーに確認しました。君のような人間がわが党の政策をやり、これから大臣ポストについていく。こんなことで人権啓発なんてできようはずがないんだ。私は絶対に許さん!」
野中の激しい言葉に総務会の空気は凍りついた。麻生は何も答えず、顔を真っ赤にしてうつむいたままだった。」
このことは、最近の『東京新聞』(2008/10/24)における野中インタビューでも触れられている。
「僕はどう言われようと構わない。ただ、政治家として問題の経緯を知らずに人権をゆがめて見ているとは、悲しいことだ」
本書は、野中本人からも難詰されたという、被差別のことについてのみ触れているわけではない。また、(そのような側面はひときわ強かったにせよ)差別撤廃に向けて闘った政治家として描いているのでもない。むしろ、権力争いの中で陰に陽に動き続けた、妖怪的な政治家として描いているものである。その行動には一貫性がおよそなく、受苦の体験からくるのであろう、差別へのまなざしは持ち続けていたとしても、国家がかくあるべきという大きなビジョンもなかったのだとする。もちろん、小さな声がかき消されてしまう小選挙区制導入に反対していたことは、前者の面につながっているのだろう。
マイナスの面はいくつも見つけることができる。橋本首相時のSACO合意後、沖縄・普天間基地の返還に伴う辺野古基地建設には拘泥し続けた。名護市の住民投票の際にも、基地賛成票を集めるべく、カネ(振興策)を提示し、地元建設業や防衛施設局(当時)の戸別訪問を現地入りまでしてプッシュしている。住民投票では「基地ノー」が示されたものの、野中の推した自公連携などが奏功し、その後沖縄では自民政権寄りの政治体制が力を持つようになる。
一方では、次のような発言もしている。沖縄で米軍用地を強制使用する改正沖縄特措法(1997年)の採決時のことだ。
「那覇からタクシーで宜野湾に入ったところ、運転手が急にブレーキをかけ、「あの田んぼの畦道で私の妹は殺された。アメリカ軍にじゃないんです」と言って泣き叫んで、車を動かすことができませんでした。その光景が忘れられません。どうぞこの法律が沖縄県民を軍靴で踏みにじるような結果にならないよう、そして今回の審議が再び大政翼賛会のような形にならないよう若い皆さんにお願いしたい」
戦争の悲惨さを肌身で知る野中の心中から思わず漏れ出た言葉である。」
この大いなる矛盾が同居した政治家であったということか。ただ、引退のきっかけとなった小泉政権の成立より、いい意味でも悪い意味でも、利権温存型、利益再分配型のような旧来の自民党政治は姿を変えてしまっている。そして、受苦の存在に無自覚な者が、「小泉以降」の新自由主義・新保守主義的な側面を受け継いでいるのは確かにおもえる。