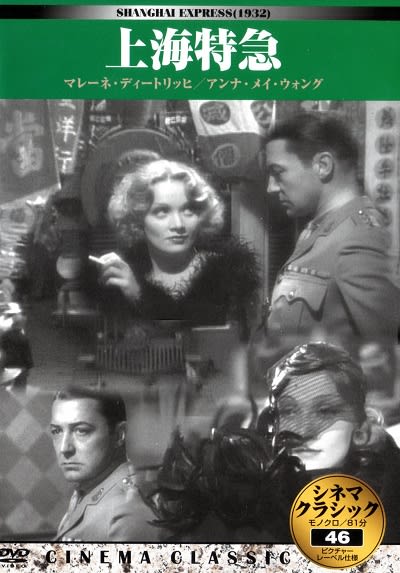中野聡『東南アジア占領と日本人 帝国・日本の解体』(岩波書店、2012年)を読む。

本書は、軍人や、宣伝のために駆り出された作家たちの「語り」を通じて、日本の「南進論」の根本的な矛盾や実相を浮き彫りにしている。なかには、検閲を意識してか実状を避ける者もある。回想において偏った記憶のみを綴る者もある。それらを含め、ひとつの歴史が形作られている。
後藤乾一『近代日本と東南アジア 南進の「衝撃」と「遺産」』(>> リンク)が説いているように、「南方占領」は、第一義には資源の獲得(石油、鉄、稀少資源、ゴム、米など)が目的であり、「大東亜共栄圏」構想など欺瞞にほかならなかった。しかし、本書によれば、それは中長期的な戦略を練った上での方針ではなく、日本の対外政策に対する米国の予想を超える反発や、ヨーロッパにおけるドイツ軍の優勢という好機を受けての結果に過ぎなかった。政府や日本軍のなかに批判的な意見も多くあったが、その声は押しつぶされていく。
欺瞞とは、国家自存のため資源獲得に動くのであり覇権のためではないとアピールすること、それは秩序安定のためでもあると言うこと、やがて、資源獲得のためであるにも関わらず「聖戦」「大東亜共栄圏」を謳うこと、すなわち本質を大義で糊塗すること。しかしその大義とは、他者、すなわち占領される者との相互理解や共感を前提としない、独りよがりなものであった。
他者と解り合おうとしないばかりでなく、日本の東南アジア支配は、在来農業を歪め、物流を機能不全に陥らせ、当然、日常生活を破壊した。いまだ神話のように残る、日本は結果的に東南アジアの独立に手を貸し、経済発展にも貢献したのだというクリシェは、実態に基づかないものであることがわかる。
「宿主と中長期的に共生できる見通しがなく、宿主を死に至らしめる寄生者は宿主から見れば排除すべき病原体でしかない。そのような意味において、日本の軍事支配は、東南アジアを数年で飢餓と死に至らしめる存在でしかなかった。そして日本帝国にできたことは、占領地の経営ではなく、暴力と武威による、帝国の最も古代的な形態としての戦利品の略奪に過ぎなかったのである。」
日本政府は、「独立」という言葉を出し入れした。すなわち、西欧支配からの解放など方便であった。ビルマやフィリピンには傀儡政権を、仏印のベトナム・カンボジア・ラオスにも敗戦直前に傀儡政権を打ち立て、インドネシアには最後まで形だけでも独立を与えなかった。東條英機は、傀儡政権を日本の「弟」であるかのように見なす「満州国モデル」を信奉していたという。しかし、当の東南アジアの側は、決して日本の言うがままに従っていたわけではなかった。
やがて、この独りよがりで暴力的な国家経営は破綻する。著者は、このときはじめて日本人が他者としての東南アジアと接したのだとする。中には、インドネシア・ナショナリズムという「他者の正義」に魅了され、独立運動に自らを同一化させた日本人も現れたのだという。勿論、それは日本の支配という歴史とはまったく別のものとして見るべきである。
それが現在の日本において実をならし続けているのか。わたしには、国境問題を巡り、他者には国境問題など存在しないとして議論を拒否し、その逆の行動に遭うや極めてヒステリックな反応を示す日本が、他者との相互の応答を身に付けているとは思えない。
●参照
○後藤乾一『近代日本と東南アジア』
○波多野澄雄『国家と歴史』
○高橋哲哉『戦後責任論』