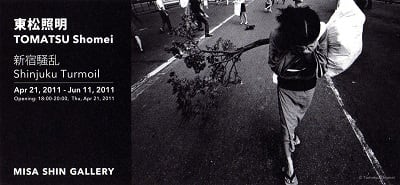デイヴィッド・マレイの映像作品、『Saxophone Man』(ジャック・ゴールドスタイン)を観る。実際には、ドキュメンタリー『David Murray, I'm a Jazzman』(2008年)、ライヴ『David Murray and the Gwo Ka Masters / Live in Sainte Lucie』(2008年)と『David Murray Black Saint Quartet / Live at Banlieues Bleues Festival』(2010年)の3本の作品が、2枚のDVDに収録されている。

『David Murray, I'm a Jazzman』は、マレイの八面六臂の活動を捉えた映像だ。ジャズ史に残りたいのだというマレイは、「Oh, I have heard Albert Ayler」、「Oh, I have heard John Coltrane」、「Oh, I have heard Archie Shepp」と言われるような存在になりたいのだと呟く。ニューヨークでは、「シェップが向こうに住んでいた」、「ここでアイラーが吹いたときに壁にヒビが入ったという噂がある」などと、まさに黒人ジャズ・サックス奏者の伝承の中で話すのだ。そしてアミリ・バラカ(かつてのリロイ・ジョーンズ)と部屋で語りあい、ブルースとジャズの歴史へのリスペクトを全身で示すかと思えば、ブラックパンサー党の創始者のひとり、ボビー・シールも登場する。
ジャズ評論家スタンリー・クロウチは二度ばかり出てきて、なんだかもごもごとした英語で、マレイの音楽の多様性や、原始性や、リラクゼイションについて何やら褒めているが、クロウチはこういう人なんだっけ。
演奏の映像は凄い。コルトレーンの「A Love Supreme」やオリジナル曲「Murray's Steps」を吹くかと思えば、エレキベースやヴォーカルの中で、ジェームス・ブラウンの「Sex Machine」をぶりぶりと吹きまくる。黒人作家イシュマエル・リードの詩にインスパイアされてカサンドラ・ウィルソンやアンドリュー・シリル、レイ・ドラモンドと共演。昔のミルフォード・グレイヴスとのデュオ映像もある(狂喜!)。
また、プライヴェートな映像も散りばめられている。「With me, sounds began in my house...」と語るマレイ、その通りに、教会でのコーラスとの共演。父ウォルター・マレイのギターとの家でのセッション。ベッドに座ってのバスクラ・ソロ。何と、幼少時代のマレイの8mmフィルムさえもある。
この映像作品は、マレイによる黒人音楽のルーツに対する全身でのアピールを捉えたものだ。それはジャズだけではない。カリブ海のグアドループに立ち(背番号44、レジー・ジャクソンのシャツを着ている!)、「black diaspora」に想いを馳せ、現地グアドループの音楽「Gwo ka」の音楽家たちと果敢に共演する姿がある。「Gwo ka」は素手でパーカッションを叩いての即興音楽のようであり、そこにマレイがテナーサックスやバスクラで融合する様はちょっと感動的だ。そして、黒人奴隷の孫であるアレクサンドル・プーシキンに捧げるステージ。気が付かない間に、マレイの世界が恐ろしく拡大していた。
『David Murray and the Gwo Ka Masters / Live in Sainte Lucie』は、『David Murray, I'm a Jazzman』とかなり共通するフッテージを使ってはいるものの、あくまで演奏を中心としている。パーカッションのシンプルなメロディの中に全世界があるのだと語るマレイ、そしてコルトレーンのような「selflessness」を目指し、音楽が自分をどこに連れていくのかわからないとする意識。凄まじく格好いい演奏である。これらを観たあとでは、『David Murray Black Saint Quartet / Live at Banlieues Bleues Festival』が普通に見えて仕方がない。ジャリブ・シャヒド(ベース)、ハミッド・ドレイク(ドラムス)のプレイも見ものではあるのだが。
●参照
○デイヴィッド・マレイのグレイトフル・デッド集
○マル・ウォルドロン最後の録音 デイヴィッド・マレイとのデュオ『Silence』
○マッコイ・タイナーのサックス・カルテット
○ワールド・サキソフォン・カルテット『Yes We Can』
○リロイ・ジョーンズ(アミリ・バラカ)『ブルース・ピープル』
○リロイ・ジョーンズ(アミリ・バラカ)『根拠地』 その現代性