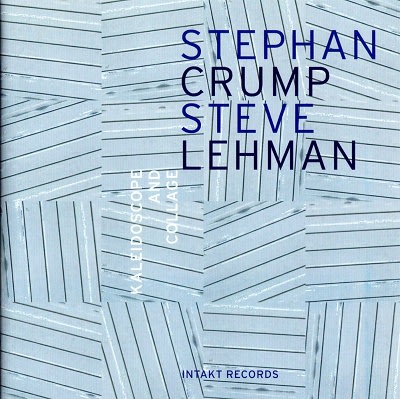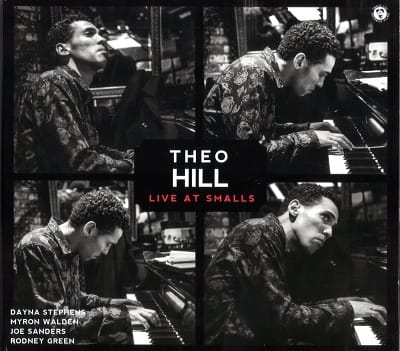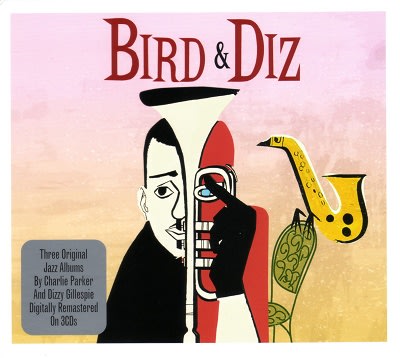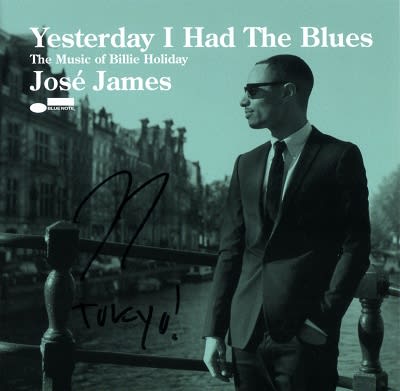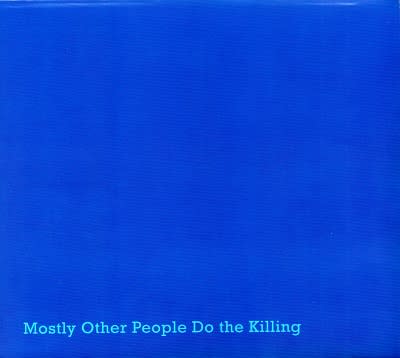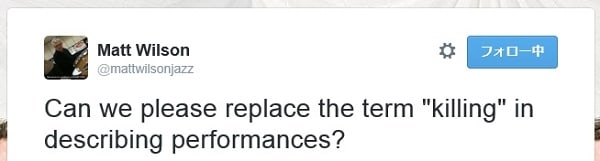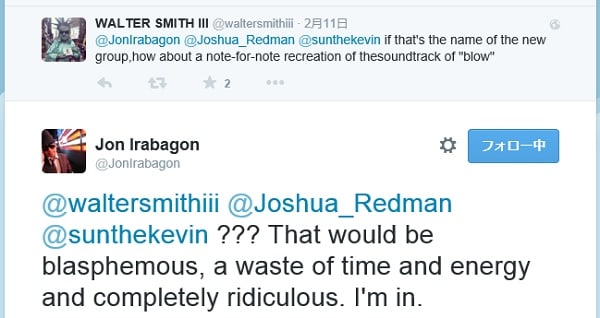服部龍二『外交ドキュメント 歴史認識』(岩波新書、2015年)を読む。

「歴史認識」を巡る問題は、戦後ずっと解決せずに存在し続けている。もとより、「歴史認識」という奇妙な言葉自体が、問題そのもののおかしさを象徴している。
敗戦後、少なくとも政治の場においては、歴史的な事実をすべて受け止めて総括する機会を喪失してしまったことは確かだ。そのために、戦争責任も平和憲法も「押し付けられたもの」であり、やむを得ない判断だとする意識が残ってしまった。そして、日本政府の立場は、「大東亜戦争」を侵略戦争であるとする国際的批判を受容しつつ、その一方で、自ら侵略戦争として認めることはない、という矛盾したものであり続けた(波多野澄雄『国家と歴史』)。
とはいえ、自民党を中心とする保守政治家たちにも、かつては多かれ少なかれバランス感があったのだということが、本書を読むとよくわかる。歴史に対しても、国際関係に対してもである。あの中曽根然り、宮澤然り、そして河野然り。それを見事なまでに失い、歪んだ二次情報・三次情報に依拠して判断する現在の惨状は、言うまでもないことだ。
日本社会は記憶の共有に失敗し、中国社会・韓国社会・沖縄社会は記憶の再確認を続けている。そして両者の噛み合わせが負のスパイラルを生み出している。
●参照
波多野澄雄『国家と歴史』
高橋哲哉『記憶のエチカ』
高橋哲哉『戦後責任論』
外村大『朝鮮人強制連行』
植民地文化学会・フォーラム『「在日」とは何か』
中野聡『東南アジア占領と日本人』
後藤乾一『近代日本と東南アジア』
玉居子精宏『大川周明 アジア独立の夢』