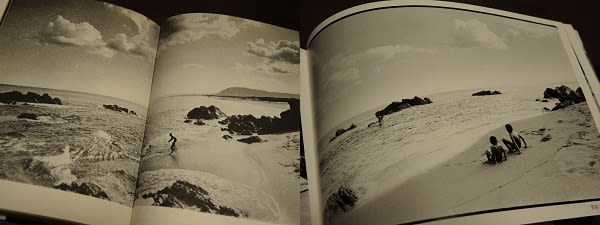先日久しぶりに亀戸を歩いたらまた行きたくなって、平日のランチを亀戸でとることにした。
■ 菜苑
錦糸町と亀戸との間あたりにあって、12時前に着くと既にほとんど満席。「純レバ丼」が有名であり、お店の人や通は単に「レバ丼」と呼んでいる。甘辛味のレバーがどろりとご飯の上に盛ってあり、さらに大量の葱。厨房ではひたすら葱をタンタンタンと刻んでいる。
さほど辛くはないが、混ぜて食べているうちに顔が温まってくる。何で味付けしているのだろう、確かに癖になりそうな。

■ 亀戸餃子
昔何度も食べたのだが、亀戸に用事がない今となってはなかなか寄りづらい。しかも、夜は18時半で暖簾をおろしてしまうため、帰り道に食べに行くことが難しい。そんなわけで久しぶりである。
入ると自動的に一皿目が出てくる。座る人は必ず二皿を食べなければならないルールである。とは言え、ビール瓶の横に皿を積み上げている人が多い。(わたしは愚かにも上の店からランチハシゴをしたので二皿のみ。)
厨房では餃子を焼く音と、ときどき最後に水を差して激しいジュワーという音。これを何年も何年も繰り返していて、旨くないわけがないのだ。サイズは大きすぎず小さすぎず。片面が揚げに近いほど焦んがりと焼けていて、キャベツやニラや挽肉からなる普通の具が詰まっている。これが固まるでもばらけるでもなく絶妙である。思い出しただけでまた一皿追加してもらいたくなる。
ところで今の亀戸には、ホルモン屋と同じように、餃子屋もいくつもある。別の店を含め、亀戸カラーとなっているのかどうか、これからの研究対象である。あっ、蒲田にもまた行って羽根つき餃子を食べないと。

●参照
亀戸事件と伊勢元酒場