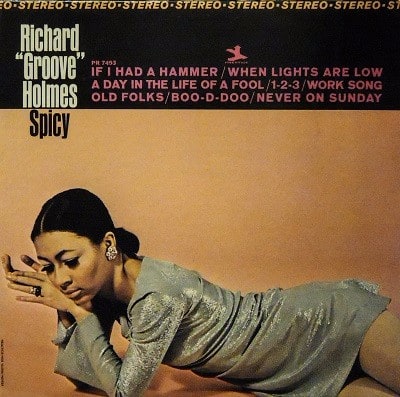T. 美川&.es『September 2012』(Re-Records、2012年)を聴く。

T. Mikawa T. 美川 (electronics)
.es:
Takayuki Hashimoto 橋本孝之 (as, g, hca)
sara (p,cajon)
大阪のギャラリーノマルと難波ベアーズにおける演奏の記録が1曲ずつ。
1曲目は、.esの演奏から始まる。苦悶するように暴れる橋本孝之のアルト。かれが掌の上の人間に感じられてしまうように、サウンドを包み込むsaraのピアノ。やがてT. 美川のエレクトロニクスが入ってきてもその構図は変わらないような印象である。
2曲目は最初からエレクトロニクスとアルトとが吐き出すサウンドが緩衝材となり、プラットフォームになるような感覚。saraさんのカホンもピアノも、モノクロのアルトとエレクトロニクスに色を付けるようであり、ふと気づくと、依然としてアルトが苦悶し生き延びている。
それにしても凄い組み合わせだ。ハコの響きなのかサウンドの質なのか、2曲の肌触りがまるで異なることも面白い。
●参照
RUINS、MELT-BANANA、MN @小岩bushbash(2017年)
第三回天下一Buzz音会 -披露”演”- @大久保ひかりのうま(2017年)
内田静男+橋本孝之、中村としまる+沼田順@神保町試聴室(2017年)
橋本孝之『ASIA』(JazzTokyo)(2016年)
グンジョーガクレヨン、INCAPACITANTS、.es@スーパーデラックス(2016年)
.es『曖昧の海』(2015年)
鳥の会議#4~riunione dell'uccello~@西麻布BULLET'S(2015年)
橋本孝之『Colourful』、.es『Senses Complex』、sara+『Tinctura』(2013-15年)