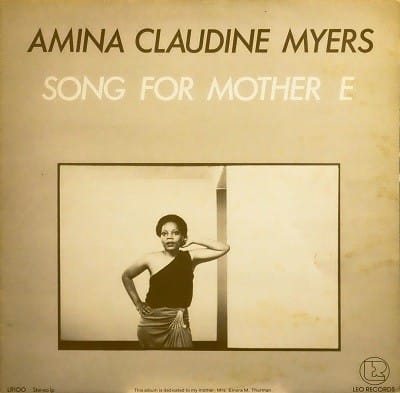渋谷の公園通りクラシックス(2019/6/27)。

Frode Gjerstad (as, cl, fl)
Jon Rune Strøm (b)
Øyvind Storesund (b)
Paal Nilssen-Love (ds)
初来日から5年くらい経つがタイミングが悪くて、今回はじめてフローデ・イェシュタを観ることができた。
かれはヨーロッパ・フリーの猛者たちと比べるとどうしても分が悪い。どちらかと言えば、ロル・コクスヒルにも通じるような、なで肩で脱力した音を出す人である。それなのに、重たいコントラバスふたりと、ウルトラスーパードラマーのポール・ニルセン・ラヴと組むのがとても面白い。拮抗の力学ではない。イェシュタはスポンジと化して周囲の音を吸い取り、スライムと化して周囲のスポンジに浸透する。アルトでもクラでもそうであり愉快になってくる。
そしてやはり凄い、ポールのドラミング。強いバネの叩きが群れと化し、歌っているかのような集合体となる。かと言って、スティックやブラシの先で創り出す高音はあくまで繊細。作家の田中啓文さんが何日か前の演奏についてツイッターに書いていたが、確かにでんでん太鼓も使って叩いている。それはポールのドラミングの一部であり、違うそうじゃないと言う余地がない。
ちょうどひと月前にベルギーのオーステンデで話をしたばかりであり、ベルギービールは度数が高いから3杯も飲むとヤバいと思うよな、と笑っていた。やっぱりね(わたしは記憶を失った)。10月にはそのときのトリオ(デイヴィッド・マレイ、インゲブリグト・ホーケル・フラーテン)でスタジオ録音をするそうである。それからもうひとつのビッグニュース。

イェシュタ氏に、デレク・ベイリーとのデュオ盤にサインを頂いた
●ポール・ニルセン・ラヴ
デイヴィッド・マレイ+ポール・ニルセン・ラヴ+インゲブリグト・ホーケル・フラーテン@オーステンデKAAP(2019年)
Arashi@稲毛Candy(2019年)
ボーンシェイカー『Fake Music』(2017年)
ペーター・ブロッツマン+スティーヴ・スウェル+ポール・ニルセン・ラヴ『Live in Copenhagen』(2016年)
ザ・シング@稲毛Candy(2013年)
ジョー・マクフィー+ポール・ニルセン・ラヴ@稲毛Candy(2013年)
ポール・ニルセン・ラヴ+ケン・ヴァンダーマーク@新宿ピットイン(2011年)
ペーター・ブロッツマン@新宿ピットイン(2011年)
ペーター・ブロッツマンの映像『Concert for Fukushima / Wels 2011』(2011年)
ジョー・マクフィーとポール・ニルセン-ラヴとのデュオ、『明日が今日来た』(2008年)
4 Corners『Alive in Lisbon』(2007年)
ピーター・ヤンソン+ヨナス・カルハマー+ポール・ニルセン・ラヴ『Live at Glenn Miller Cafe vol.1』(2001年)
スクール・デイズ『In Our Times』(2001年)