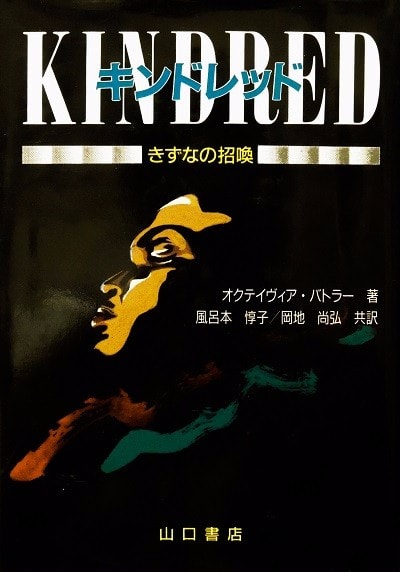デレク・ベイリー+ルインズ『Saisoro』(Tzadik、1994年)を聴く。

Derek Bailey (g)
Ruins:
Tatsuya Yoshida 吉田達也 (ds)
Ryuichi Masuda 増田隆一 (b)
ずっと気にかかってはいたものの聴くのははじめてだ。つまりこのようなサプライズは聴きたくもあり聴くのが怖くもあり。
しかし、デレク・ベイリーは往年のひりひりするような緊張感を失っている。ルインズもなんだか大人しい。異種格闘技戦を期待したのに蓋を開けてみたら凡戦だったという印象。近所迷惑な大音量にすればまた迫力も違うのだが、それはルインズの魅力でありベイリーの魅力ではない。
●デレク・ベイリー
今井和雄 デレク・ベイリーを語る@sound cafe dzumi(2015年)
デレク・ベイリー晩年のソロ映像『Live at G's Club』、『All Thumbs』(2003年)
デレク・ベイリー『Standards』(2002年)
ウィレム・ブロイカーが亡くなったので、デレク・ベイリー『Playing for Friends on 5th Street』を観る(2001年)
デレク・ベイリー+ジョン・ブッチャー+ジノ・ロベール『Scrutables』(2000年)
デレク・ベイリーvs.サンプリング音源(1996、98年)
田中泯+デレク・ベイリー『Mountain Stage』(1993年)
1988年、ベルリンのセシル・テイラー(1988年)
『Improvised Music New York 1981』(1981年)
ペーター・コヴァルトのソロ、デュオ(1981、91、98年)
デレク・ベイリー『New Sights, Old Sounds』、『Aida』(1978、80年)
『Derek Bailey Plus One Music Ensemble』(1973、74年)
ジャズ的写真集(6) 五海裕治『自由の意思』
トニー・ウィリアムスのメモ
●ルインズ
RUINS、MELT-BANANA、MN @小岩bushbash(2017年)