
もっとも敬愛する映画作家、ジョナス・メカスによる、2000年に完成した4時間48分の大作である。2002年に、御茶ノ水のアテネ・フランセで観た。
長いとはいえ、ボレックスの16ミリカメラで日常を淡々と撮り、時間を置いてから編集し、自分の訥々と話す声をかぶせる映画のあり方は、これまでの作品とまったく変わらない(もっとも、『グリーンポイントからの手紙』など最近の作品はDVを使っているようだが)。
1996年に六本木のシネ・ヴィヴァン(今はもうない)でのリバイバル上映で観た、『リトアニアへの旅の追憶』(1972年)に揺さぶられてから、メカスのことがずっと好きである。故郷への旅という非日常でありながら、日常的な視線と心象を撮った、揺れるカメラ、瞬き、情緒的な自身の声、により、酔ったような気持ちになった。その<瞬き>は、実は、ボレックスが壊れて露出がおかしくなっていたからでもあるが、小型映画独特の、フリッカーの明滅からこぼれるような光と<染み>があってこその効果だ。吉増剛造が言う、8ミリの画面についての、「脈動を感じます。それはたぶん8ミリのもっているにごり、にじみから来るのでしょう」(『8ミリ映画制作マニュアル2001』、ムエン通信)とする感覚にも共感をおぼえる。
『歩みつつ垣間見た美しい時の数々』は、自分の妻や子どもたち、友達などのシークエンスを、個々にタイトルを出しては展開するという手法で作られている。採録シナリオを読んでも、それしかない。これで5時間弱も語り続けるのは過激ですらある。
メカスが過去の映像を利用しつつ語る、編集時点での気持ち。観客に対して、これは日常に過ぎないのだと開き直るのも、『リトアニア・・・』と同じだ。しかし、メカス自身が歳をとった所為なのか、とても感傷的だ。ゆらぐ映像とともに聴かされると、胸がしめつけられる。甘いといえばその通りなのだろうが。
「長い時を費やして、ようやくわたしはひとを石、木々、雨と隔てるのは愛であること、その愛は愛することによって育まれると気づいた、そう、わたしにはどうすればよいのか、まったくわからない、なにひとつ、わからない―。」
「きみの眼に歓喜と苦痛を、失われ、取り戻され、再び失われた楽園の残影を、あのひどい寂しさと幸せを見た、そして夜明けに独りこうして坐り、思いをめぐらせ、きみを想う、冷たい宇宙を往くふたりの寂しい飛行士のようなわたしたち、そうしたひとつひとつに思いを馳せる―。」
「わたしたちの暮らしは、みなじつによく似ている。ブレイクの言うとおり、ひと雫の水にすぎぬ。わたしたちはみなそのなかにあり、きみとわたしの間に大きなちがい、本質的なちがいなどありはしない。」
「どれもこれも、日々くりかえされるなんでもない情景、そのひとだけのささやかな楽しみや歓びばかり。重要なものはどこにも見当たらない。しかしそう見えるとすれば、そのひとは生まれて初めて歩いたこどもの感じる有頂天の歓びを知らないのだ。その瞬間の、こどもが生まれて初めて踏み出す一歩が、たとえようもなくたいせつなことを知らない。春、木々が一斉に花を咲かせる、そのたいせつさ、途方もないたいせつさ。奇蹟、日々の奇蹟、今、ここにある楽園のささやかな瞬間、またたきひとつするうちに、過ぎ去って、もう戻らないかもしれない一時。まったくたわいもなく(笑い) しかし、すばらしい・・・・・・」
「撮影するこころよさ、身近なものをただ撮ること、眼に映るもの、そこにあると気づいてわたしが反応するもの、指が、眼が反応を起こすもの、この瞬間、今、すべてが起こりつつあるこの瞬間を撮影することの、ああ、そのなんというこころよさ―」
「今わたしはきみたちに話しかけているのだよ、ウーナ、セバスチャン、そしてホリス。今、わたしはきみたちに話しかけている。これはわたしの思い出だ。きみたちにも記憶があったとしても、きみたちの思い出はずいぶんわたしのとはちがっているのだろう。これはわたしの思い出だ。」
最後の引用は、映画でも4時間を過ぎて終わりそうな頃に、自分の子供たちと妻に向けて話された台詞だ。しかし、私には、妻への愛情表現がいちばんの気持ちであって、メカスの照れ隠しではないかと感じられた。もっと言えば、これはメカスが妻にささげた愛情映画だ。映画のフラグメントひとつひとつが「なんでもない」ものであっても、観るものは、想いさえ共振すれば、長い映画でもメカスの心象に引き込まれるし、これは実は自分のなかで反射し続ける体験にもなるのだった。
メカスは2005年、青山の画廊「ときの忘れもの」での個展にあわせて再来日した。自身の映画フィルム3コマくらいを大伸ばしにした作品だ。レセプションパーティーでメカスに逢えるというので出かけて、メカスに映画のことではなくごく私的なことについてだけ話をした。夢のような心地だった。

ジョナス・メカス Leica M3、ズミクロン50mmF2.0、Tri-X(+2)、フジブロ2号

ジョナス・メカス Leica M3、ズミクロン50mmF2.0、Tri-X(+2)、フジブロ2号










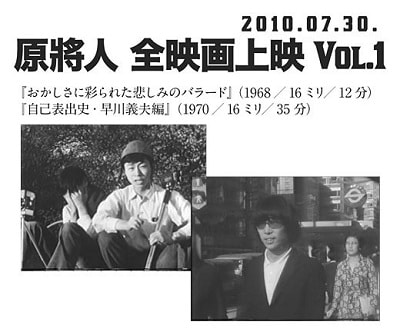
























 =====
=====











