
こういう映画が製作されるだけでも日本ってまだまだ行けると思います。恐らく動員数は多くはならないだろうけれど、それは見るまでに躊躇してしまう時間がある映画でもあるからなのです。
でもそんな不安はすぐなくなった。出演者が子供たちというのはどんな映画でも心を明るくさせる。広くさせる。勇気をもらう。清浄感がいっぱいになる。元気が出る。つまり素晴らしくいい時間をもらうということなのだ。
先生は初授業の時に出勤を取る。28名の子供たち全員をあらかじめ覚えているからフルネームで出勤を取る。一人一人顔を見る。驚く子供たち。手・脚のない普通でない人間を見た驚きより、子供たちは違う驚きを感じてしまう。いい導入部だ。
満開の桜の下で授業。いいなあ。僕もそんな授業を受けてみたかったなあ。でも問題ありと、それっきりになる。まあ当然かな。
運動会。遠足。子供たちとの熱い交流が続く。この先生の存在そのものが人間との交流を考えるいい授業材料になるのだ。教育とは何か。否が応でも考えてしまう。
ちょっと映画的で小細工が過ぎるシーンも多々見られたけれど、ぼくはこの映画の存在自体に深く共鳴しているのでそれについては触れない。(例えばハイライトシーンの少女が靴を盗んでしまっていたことを告白するシーンは少々あざとい。)
「人間、違っていて当たり前なんだよ。違っていていいんだよ。」は感動的である。その違っていることそのものからいじめが始まっているらしいと聞く。
子供も大人も政治家もいろんな人が見るべき映画である。こういう映画がメジャーで製作されるのは本当にうれしい限りである。本当に汚いぼくが清浄感に包まれている。










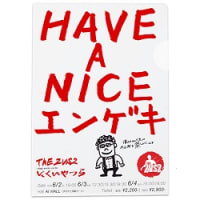






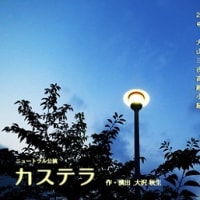







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます