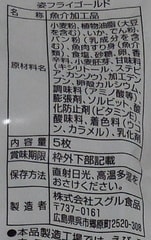JR木見駅は昭和63年(1988)3月20日の開業。無人の改札を抜け広場を通り宝篋印塔(ほうきょういんとう)のある方へ向かった。宝篋印塔とは供養塔の一種で墓のかわりに建立される場合もあった。福山では同様の石造物が千田大峠の頂付近に存在する。


木見の宝篋印塔は天明期の作である。建立目的はフェンスの内側に建つ標柱「波止岡の首切り地蔵 血洗いの池」を見て理解した。どうやら宝篋印塔の横に首切り地蔵が祀られているようだった。




木見の宝篋印塔は天明期の作である。建立目的はフェンスの内側に建つ標柱「波止岡の首切り地蔵 血洗いの池」を見て理解した。どうやら宝篋印塔の横に首切り地蔵が祀られているようだった。

見慣れていた物が急に消え失せるとやはり寂しいものである。私は西公民館の建設現場から国道2号線へ向かう途中、廃寺となって久しい臨済宗・龍淵寺(西町1丁目11‐8)が解体撤去されたことに気付き愕然とした。

敷地の西端に墓と六地蔵のみが残されている。平成24年(2012)10月初旬に同じ場所を撮影した写真を比較対象としてご覧にいれよう。


寺の背後(東方)にはロッツ(現りむ)のロゴが見える。かつて入口脇には龍淵寺と大きく刻まれた石柱が建っていたのである。


入口正面に道場とでもいうべき平屋があり、墓地よりに小宇が経ち、六地蔵も屋根付きのお堂に祀られていた。私は『三四郎(明治41年に連載が始まった夏目漱石の小説)』を読むために久し振りに漱石全集第五巻を開いた。そして次の有名な一節に目を通し苦笑したのである。
三四郎が東京で驚ろいたものは沢山ある。第一電車のちん〱鳴るので驚ろいた。それから其ちん〱鳴る間に、非常に多くの人間が乗つたり降りたりするので驚ろいた。次に丸のうちで驚ろいた。尤も驚ろいたのは、何処迄行つても東京が無くならないと云う事であつた。しかも何処をどう歩るいても、材木が放り出してある、石が積んである、新らしい家が往来から二三間引っ込んでゐる、古い蔵が半分取り崩されて心細く前の方に残つてゐる。凡ての物が破壊されつゝある様に見える。さうして凡ての物が又同時に建設されつつある様に見える。大変な動き方である。
三四郎は全く驚ろいた。要するに普通の田舎者が始めて都の真中に立つて驚ろくと同じ程度に、又同じ性質に於て大いに驚ろいて仕舞つた。今迄の学問は此驚ろきを預防する上に於て、売薬程の効能もなかつた。三四郎の自信は此驚ろきと共に四割方減却した。…
約100年前の東京と今の福山の状況に似たようなものを感じるのは私だけであろうか。街の発展(景観向上)のために消滅してゆく物は非常に多い。一市民として後生のために出来るのは記録として残しておくことぐらいなのだ。


敷地の西端に墓と六地蔵のみが残されている。平成24年(2012)10月初旬に同じ場所を撮影した写真を比較対象としてご覧にいれよう。


寺の背後(東方)にはロッツ(現りむ)のロゴが見える。かつて入口脇には龍淵寺と大きく刻まれた石柱が建っていたのである。


入口正面に道場とでもいうべき平屋があり、墓地よりに小宇が経ち、六地蔵も屋根付きのお堂に祀られていた。私は『三四郎(明治41年に連載が始まった夏目漱石の小説)』を読むために久し振りに漱石全集第五巻を開いた。そして次の有名な一節に目を通し苦笑したのである。
三四郎が東京で驚ろいたものは沢山ある。第一電車のちん〱鳴るので驚ろいた。それから其ちん〱鳴る間に、非常に多くの人間が乗つたり降りたりするので驚ろいた。次に丸のうちで驚ろいた。尤も驚ろいたのは、何処迄行つても東京が無くならないと云う事であつた。しかも何処をどう歩るいても、材木が放り出してある、石が積んである、新らしい家が往来から二三間引っ込んでゐる、古い蔵が半分取り崩されて心細く前の方に残つてゐる。凡ての物が破壊されつゝある様に見える。さうして凡ての物が又同時に建設されつつある様に見える。大変な動き方である。
三四郎は全く驚ろいた。要するに普通の田舎者が始めて都の真中に立つて驚ろくと同じ程度に、又同じ性質に於て大いに驚ろいて仕舞つた。今迄の学問は此驚ろきを預防する上に於て、売薬程の効能もなかつた。三四郎の自信は此驚ろきと共に四割方減却した。…
約100年前の東京と今の福山の状況に似たようなものを感じるのは私だけであろうか。街の発展(景観向上)のために消滅してゆく物は非常に多い。一市民として後生のために出来るのは記録として残しておくことぐらいなのだ。