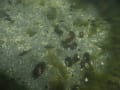 今期の繁殖期を前にして飼育していた繁殖可能なタナゴが全て失われてしまった。兆候は昨秋からあって魚体の大きいオスから絶命していったのだ。今春、越冬明けから姿を見せるようになってからも一匹二匹と死ぬ個体が続き、最終的には繁殖適齢期に達しない個体だけが残ったのだ。
今期の繁殖期を前にして飼育していた繁殖可能なタナゴが全て失われてしまった。兆候は昨秋からあって魚体の大きいオスから絶命していったのだ。今春、越冬明けから姿を見せるようになってからも一匹二匹と死ぬ個体が続き、最終的には繁殖適齢期に達しない個体だけが残ったのだ。失ったタナゴは飼育開始して5年目に突入し、それ以前に成体だった群れだから寿命と思ってあきらめた。それでも未練は捨てられず、成体に達しないタナゴを相手に二枚貝は産卵籠に移し管理していたけれど、産卵管の出ていない群れから産卵する訳もなく、ついには産卵籠から池の砂地に戻したのだ。
習性なのかどうか、産卵管が出ていなくても二枚貝に興味深々の行動をみせるから、ついつい「もしや・・・」や「ひょっとしたら・・・」と期待してしまう。
今期の池の環境は、いわゆる緑藻類が繁茂せず、茶色の藻が繁殖してきた。珪藻なのかどうなのか不明なのだが、緑藻類とは異なり池の低層にモヤモヤと増え続け砂地も覆ってしまう勢いがある。時折は排除しているけれど、簡単にバラける感じで綺麗にするのは至難だ。いわゆる「茶藻」と言われる珪藻類なら水中に拡散してくれれば貝の餌になるから大歓迎なのだが、餌にならない可能性もありうるから自前の混合人工餌を給餌している。
産卵母貝とならなければ、後は肥培するだけなので来季に向けしっかりと管理せねばなるまい。万が一、産卵された可能性も排除せず水草の繁る一角を設定してあるので稚魚はこの中に逃げ込めるだろうが、使わなくなった庭の隅に用意してある浮揚水槽は、住民も無く夏を迎えるのだ。
蚊の発生を防ぐためにメダカでも入れておこう。














 「常食ム・カ・デ…」
「常食ム・カ・デ…」










 「蒸し蒸し蒸すわい!無視したい…」
「蒸し蒸し蒸すわい!無視したい…」







 「やっぱ、視線感じるわぁ」
「やっぱ、視線感じるわぁ」



 「たんたんタヌキの…じゃあなくて!」
「たんたんタヌキの…じゃあなくて!」






