いよいよ習皇帝体制は終わりなのでしょうか。それにしても、もしこれで終わりとすると、絶頂期が余りにも短かったようです。
どうやら、石平さんもその側近政治から終わりを予感しているようです。となると、後は誰が継ぐのでしょうか。それとも内乱になるなんてこともあるのでしょうか。
願わくば、内乱から崩壊へと順調に行ってもらいたいものです。
産経ニュースより 2018.7.26
【石平のChina Watch】側近政治」の失敗と限界
昨年秋の中国共産党第19回全国代表大会(19大)で確立された習近平・個人独裁体制は、縁故主義に基づく「側近政治」を 特徴のひとつとしている。
19大で誕生した新しい共産党政治局25人のメンバーのうち、習氏の幼なじみ、同級生、元部下であった人々は9人に上っ た。
その中で習氏の中学校の同級生の劉鶴氏、大学時代のクラスメートの陳希氏、福建省・浙江省地方勤務時代の部下である蔡奇氏 などは、能力や人望とは関係なく、習氏個人との縁故によって政治局委員に抜擢(ばってき)され、側近として党と政府の要所要 所に配置された。
それ以来、習氏は一貫して側近たちを使ってトップダウンの独断政治を行っているが、最近、このような政治手法が壁にぶつ かって大きくつまずき始めている。
その一例が米中貿易戦争における政権の失敗である。本来、アメリカから仕掛けられた貿易戦争において中国は圧倒的に不利な 立場にあり、いかにして、それを回避するのかが中国の至上命令である。習氏自身もある程度は、「戦争回避」の重要性を認識し ていたはずだ。
そのために、習氏は国務院副総理である前述の劉氏を中国側の代表に任命し、今年5月から3回にわたって米国側との通商協議 を行った。だが劉氏の代表任命自体がそもそもの失敗であった。
劉氏は経済畑の幹部で、アメリカ留学の経験もあるが、今まで責任を持って対米外交交渉や貿易交渉に携わったことは一度もな い。米中通商協議に関しては、まったくの未経験者である。
アメリカを相手とする貿易協議には、うってつけの人材が別にいるはずだ。政治局常務委員で筆頭副総理の汪洋氏である。汪氏 は習政権下の2013年から17年まで連続5回、中国側の筆頭代表として米中戦略経済会議に参加してきた。まさに対米貿易交 渉のベテランである。
問題は、彼が習氏の側近ではなく、別の派閥である共青団派の人間だということだ。
それが原因で、習氏は対米交渉のエキスパートである汪氏を敬遠して、側近の劉氏を起用し、大事な対米貿易協議に当たらせ た。
しかし、貿易戦争の回避を目指した、習・劉両氏主導の対米貿易協議は結局失敗に終わった。今月6日、トランプ政権はとうと う、340億ドル相当の中国からの輸入品に対し25%の制裁的追加関税を発動した。米中貿易戦争は火ぶたが切られた。
それを受け、習政権は直ちに、米国からの輸入品に対する同規模の追加関税を報復措置として発動したが、それに対し、トラン プ政権はさらに、2千億ドル分の中国からの輸入品に10%の関税を上乗せする追加制裁を行うことを発表した。
しかしそれでは、中国はもはや、アメリカに対する同等の報復はできない。中国の毎年の、アメリカからの輸入は1500億ド ル程度だから、「2千億ドル分の輸入品に対する追加関税」を発動できるわけはない。「やられたら報復するぞ」という習氏流の 恫喝(どうかつ)は不発に終わった。
そしてもし、アメリカが上述の2千億ドル分の中国からの輸入品に対する制裁関税を本当に発動してしまえば、輸出頼みの中国 経済に破滅的な打撃を与えかねない。習政権は今、大変な窮地に立たされているのである。
このような結果となったのには、トランプ政権の決意を甘く見過ぎた習氏自身の判断ミスがあった一方、劉氏という対米交渉の 門外漢を起用したことも敗因であろう。
側近しか信用しない、側近しか使いこなせないという、政治家としての習氏の器の小ささがこれで露呈し、同時に、習近平・個 人独裁体制の大いなる限界も見えてきた。
それにしても、これ程の側近政治で今まで順調に来たものですね。敵も習王朝を確立させそうになった途端に、これは危ないと手をうちだしたのでしょうか。
暫くは、目を離せそうもないですね。
どうなることやら!










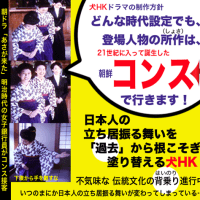
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます