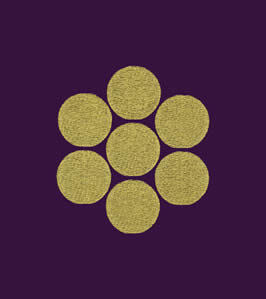☆クロワッサンで朝食を(2012年 フランス、エストニア、ベルギー 95分)
原題 Une Estonienne à Paris
staff 監督/イルマル・ラーグ
脚本/イルマル・ラーグ アニエス・フォーヴル リーズ・マシュブフ
撮影/ローラン・ブリュネ 美術/パスカル・コンシニ
衣裳デザイン/アン・ダンスフォード 音楽/デズ・モナ
cast ジャンヌ・モロー ライネ・マギ パトリック・ピノー フランソワ・ブークラー
☆あの朝、彼女はいくつクロワッサンを買ったのか
ジャンヌ・モローは御年85歳だという。
なのに、あの軽やかさはどうだろう。
身のこなしはとても85歳のそれじゃなく、歩き方もすんごい若い。
もちろん、貫録は恐ろしいほどだし、
声のしわがれぶりは、酒と煙草によるものなんだろうけど、それも迫力のひとつだ。
さらにいえば、
なんとまあ小道具が似合ってること、とおもったら、どうやらみんな私物らしい。
てことは、いつもジャンヌ・モローはごっつい屏風としゃれた家具に囲まれ、
ウェッジ・ウッドの食器を使い、シャネルのネックレスや服を着てるわけだ。
あ、でも、ライネ・マギに「あなたにあげるわ」といって渡しながらも、
ライネが出ていっちゃったときに置いていったバーバリーのコートは、
たぶん、ジャンヌの私物じゃないんだろうね。
だって、まじに若いときに着てたやつならともかく、サイズが全然ちがうもん。
でも、あのコートをまるで赤ん坊を抱くように抱きかかえるジャンヌは、実にうまい。
こういう小道具の使い方は、上手だね。
ライネは最初、やぼったい。
エストニアでは家の中で靴を履かないのか、家履きを用意してるけど、
パリの暮らしはそうじゃないっていうカルチャー・ショックを受けてから、
ちょっとずつだけど綺麗になるし、衣裳も洒落てくる。
家政婦をやめて家出したときには、ミニスカートにハイヒールになった。
もう彼女はエストニアの田舎おばさんじゃなくて、パリジェンヌになってるんだよね。
でも、戻る家を失くしてしまった彼女は、ふたたび、野暮ったい雪靴に履き替える。
寂しい感情がひしひしと訪れてくる。
ジャンヌの話に戻るんだけど、
息子くらい年の離れた愛人ピノーが添い寝してくれたとき、
ジャンヌの手は股間に延びる。
でも、ジッパーを下げることはできないし、
シャツのボタンをはずしても、元愛人の裸の胸に顔をうずめるのが精一杯とはいえ、
85歳になっても女は女なんだっていう感情が辛いくらいによくわかる。
人間はセックスが忘れられないんだっていう業がよく出てるし、
ライネに対して「あなた、最後にセックスしたのはいつなの?」と遠慮なく聞くのも、
「あなたと彼がセックスする関係になっても、わたしは全然かまわないのよ」
と、見栄を切ってみせるところも、
いかに、ジャンヌが性の欲望に正直に生きてきたのかが身にしみてわかる。
富豪か実業家かどっちかわからないけど、
その愛人になって莫大な資産を受け継ぎ、
その資産の一部を若い愛人のピノーに貢いで、
それなりに楽しい暮らしをしていたのに、
結局は、若い愛人から「もう、あんたのわがままは通用しないんだ」と、
冷たく言い放たれてしまう身の辛さも、またわかる。
このあたりの演出は、好いわ~。
ところで、
ライネが家出からピノーと一緒に16区に帰ってきたとき、ジャンヌはこういう。
「ここは、あなたの家なのよ」
でも、その後は、どんな台詞を吐いたんだろう。
「わたしは朝食がまだなの。あなた、クロワッサン、買ってきてくれたんでしょうね」
「まだ、です」
「だったら、すぐに買ってきて。6つ、よ」
とでもいうところだろう。
もちろん、家出したんだから、朝食なんて用意しようとおもってない。
でも、買ってませんじゃダメなんだよね、まだ、でないと。
それに、女主人として厳然とした立場にあれば、クロワッサンは2つなんだけど、
あなたの家だし、ピノーはわたしの愛人だったけど、いまはあなたたちは好きあってる、
だから、ひとり2つずついるのよ、って感じになってないとね。
ま、そのあたりは想像するより仕方ないんだけど、
それにしても、クロワッサンはパン屋で買うものだって断言するジャンヌが好い。
スーパーで買うクロワッサンをプラスチックっていうんなら、
自分で焼くのがいちばん美味しいんじゃないかっておもうんだけど、
「パリの暮らしはちがうのよ。パン屋で買わないといけないの」
っていう職人を認めた考え方が、いかにもパリらしくて好いんだ。
そうそう、書き忘れてたけど、
この話は、どうやら実話らしい。
監督のイルマル・ラーグのお母さんがライネのモデルみたいだ。
その後、家政婦として女主人の最期を看取ったんだろうか?
それとも、家族として看取ったんだろうか?
知りたいわ~。