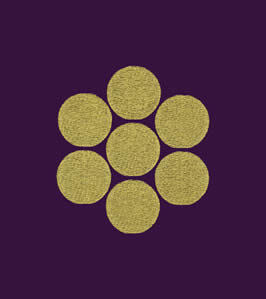◎追憶(1973年 アメリカ 118分)
原題 The Way We Were
staff 原作/アーサー・ローレンツ『The Way We Were』
監督/シドニー・ポラック
脚本/アーサー・ローレンツ デヴィッド・レイフィール
撮影/ハリー・ストラドリング・ジュニア 美術/スティーヴン・B・グライムズ
装飾/ウィリアム・キアーナン タイトル・デザイン/フィル・ノーマン
衣裳/ドロシー・ジーキンズ モス・メイブリー 衣裳監修/バーニー・ポラック
音楽/マーヴィン・ハムリッシュ
主題歌/バーブラ・ストライサンド『The Way We Were』
作詞/アラン・バーグマン マリリン・バーグマン 作曲/マーヴィン・ハムリッシュ
cast ロバート・レッドフォード バーブラ・ストライサンド ジェームズ・ウッズ
◎ハリウッド、レッドパージ
調布市仙川で、とある演劇を観た。
一世紀前の大英帝国で婦人参政権運動が盛り上がりを示した頃、その過激な運動に参加していた弁護士の妻にして女流作家が職工の娘と牢獄で知り合い、やがてレズビアンな関係になり、まあ、紆余曲折あった後に、年若い相手は普通の男と結婚し、自分は夫と別れて、自分の進むべき銀色の狼の道を進んでゆくという筋立てだ。翻訳物のようだったけど、場面展開があまりにも多く、ちょっと戸惑った。
ウーマンリブの走りの姿を描こうとしたというより、レズの話が核になっているような印象だったもんだから、肩透かしを食らった観もないではなかったけど、それについてはいい。政治に興味を持ち、自分の正しさを猛烈に主張して行動する女性は、いつの時代にもいる。
たとえば、この作品がそうだ。
1937年から20年間、共産主義を標榜し、赤狩りに抵抗し、さらには原水爆の反対運動に身を投じてゆくバーブラ・ストライサンドと、脚本家や小説家になることを夢見、政治運動を客観的に見、やがてみずから決めた脚本家への道をたどってゆくロバート・レッドフォードとの恋愛、結婚、出産、離婚、再会、そして追憶によって辿る話だ。
貧乏な家に生まれたバーブラ・ストライサンドは理想に燃え、裕福な家に育ったロバート・レッドフォードは現実を見極めている。ふたりは生まれも育ちも思想も主義も行動も生き方も違うんだけど、そのふたりの結晶は世に生まれ、あらたな時代のひとりとなる。戦前から戦後のある一時期まで、こうした男女は少なからずいただろう。
ふたりの辿った道は、やがて破局になっても、心の中でやはりどこかで求め合ってしまっているのが人間っていうものだ。だからこそ、ふたりの相容れない愛は美しい思い出として追憶される。
そんな映画で、ぼくたちが大学生の頃、かならず春になると早稲田松竹ではこれが掛けられ、毎年、観に行った。大学生にとって、学生運動を経験していてもいなくても、女性の立場に立つか、男性の立場を理解しようとするか、たいがい議論になった。そういうとき、すこし過激な女の子は、バーブラ・ストライサンドみたいに生きたいといい、ロバート・レッドフォードはつまらない男だといいきった。
まあ、それはよくわかるんだけど、いまだにぼくの知り合いの女の子には、そういう火の玉娘がいる。人間にはさまざまな生き方があって、ぼくはどうしてもこの国やこの国の人々のために戦うんだとかいう強い気持ちになることができないもんだから、いまだに、だらだらと怠けたまま、日々、ノンポリ暮らしを続けてる。
そういう意味では、レッドフォードみたいなもんだけど、ことわるまでもなく、生まれも育ちも容姿もレッドフォードには敵わない。当たり前か。ま、それはともかく、この作品を観るたびに、まだ頑張ってるんだろかと思い出すんだよね。あ、恋愛感情はないので、念の為。
(以下、2022年6月3日)
それにしても、ジェイムズ・ウッズ若いな~。こんなに堂々とした青春映画だったんだ~って、いまさらながらびっくりする。でも、なんべん観てもすぐに忘れちゃうのは、それだけぼくが歳を取ってしまったからなんだろう。仙川の劇場で観たロンドンの女性運動家は、投獄されるたびにハンガー・ストライキをして鼻から流動食をいれられて強制摂取っていう拷問を喰らい、仲間の女性たちから鉄格子の勲章を授けられたりしてたんだけど、競馬場で国王の馬の首に婦人参政権をもとめて垂れ幕をかけようとして失敗して死んじゃったらしい。hんとうだとしたら、なんだか身につまされるね。