都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
「クリムト、シーレ ウィーン世紀末展」 日本橋高島屋
高島屋東京店8階 ホール(中央区日本橋2-4-1)
「ウィーン・ミュージアム所蔵 クリムト、シーレ ウィーン世紀末展」
9/16-10/12
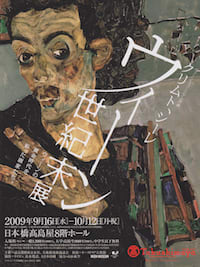
ウィーン・ミュージアム(1887年開館。旧ウィーン市立歴史博物館。)所蔵の、19世紀末から20世紀初頭の世紀末絵画コレクションを概観します。日本橋高島屋で開催中の「ウィーン・ミュージアム所蔵 クリムト、シーレ ウィーン世紀末展」へ行ってきました。
まずは本展の概要、及び見所です。
・ウィーン・ミュージアムのコレクションより、主に1890年から一次大戦の間の30年間にスポットを当てて紹介する。
・出品数は全120点。必ずしも大作メインではなく、小品の他、版画も多い。
・クリムトやシーレなどのいわゆる世紀末絵画の他、平行して発展した自然主義絵画など、多面的に同時代のシーンを追う展覧会でもある。
続いて展覧会の構成です。計5章立てでした。
1「装飾美術と風景画」:ウィーンの都市整備に伴った各種公共建築の装飾絵画。一方でクールベなどの影響下に進展した森や田園の風景絵画など。
2「グスタフ・クリムトとそのサークル」:クリムトとその周辺。代表作「パラス・アテナ」など約10点。
3「エゴン・シーレ」:シーレ。油彩、水彩などあわせて約25点。
4「分離派とウィーン工房」:分離派絵画、「ユーゲント・シュティール」の装飾表現など。
5「自然主義と表現主義」:自然主義絵画、分離派の装飾的表現から一歩、別の方向へと進んだ表現主義作家を紹介。
それでは以下、印象に残った作品を挙げていきます。
フーゴー・ダルナウト「シュトゥーベントーア橋」(1901)
黄昏時の紫の空に下にのびるアーチ橋を描く。橋上を慌ただしく行き交う人々が一日の終わりを告げている。仄かに灯るガスの光が温かい。明かりが川面にまるで舞う蛍のように反射していた。

グスタフ・クリムト「寓話」(1883)
イソップの寓話に基づく画題。中央にはアングル風の美しい白い肌を露出した裸女が立ち、その脇をツルやキツネ、そしてライオンが固めている。これらの動物は多様な民族を表すとのこと。その共存を説いている。クリムトがこのような歴史画風の作品を描いているとは知らなかった。
グスタフ・クリムト「愛」(1895)
両側にパラの花が垂れ下がる金の帯が走り、中央には男女が恍惚とした面持ちで抱擁する姿が描かれている。いかにも愛の美しさを称揚した作品にも思えるが、上部で浮かぶ数名の人物に目がとまった。まるで悪魔のような顔をした老婆などが登場している。その様は二人の脆くて儚い愛をあざ笑うかのようだった。これぞ退廃。

グスタフ・クリムト「パラス・アテナ」(1898)
ちらし表紙にも掲げられた本展のハイライト。自身の結成した分離派の第一回展に出品して賛否を巻き起こした注目作。学問や知恵、そして戦いを示すギリシャの女神が堂々たる姿で描かれている。鱗状になった甲冑はもとより、その絹のような肌をした手で掴む槍など、金を用いて表す装飾はまさにクリムトらなではきらびやかなものだった。中央の魔除けの出す舌を見れば、この作品を見て当時の保守派が怒ったのも無理はないと思う。
エゴン・シーレ「意地悪女」(1910)
シーレの妹がモデルだという人物像。口をつぼめて見る者を罵るかのようにしてこちらを向く女性が描かれている。その大仰なポーズはまるでカリカチュアのようだ。
エゴン・シーレ「ヒマワリ」(1909)
久々に出会った言葉を失うほどに衝撃的な作品。ヒマワリをこのように描いた画家など他にいるのだろうか。白を背景にした縦長の画面の中に、ほとんど無理矢理立たせているかのように干涸らび、また焦げ付き、まさに枯れ果てたヒマワリの姿が描かれている。下に群生する花々はキャプションによれば再生、また未来への希望云々と説明されていたが、私には死人に手向けた花のようにしか見えなかった。
エドゥアルト・シュテラ「踊り子」(1909)
茶碗を手に持ち、つま先立ちで舞を披露するする全裸の踊り子が描かれている。その横向けに露わとなった臀部はことさら卑猥で、正視することすら阻むほどエロチックなムードが漂っていた。
ルートヴィヒ・ハインリヒ・ユングニッケル「マース河畔にて」
スーチンあたりを連想もさせる、やや激しいタッチで描かれた河畔の景色。水面に浮かぶ何隻もの汽船からは、あたかも空を焦がすかのような煙がもうもうと立ち上っている。全体を覆うグレー、もしくは茶色の色調が、近代の到来で痛めつけられた自然の悲哀のようなものを表していた。河はすでに取り返しのつかないほど汚染されている。
マックス・オッペンハイマー「十字架降架」(1913)
出口付近で一際異彩を放っていた作品。まるで心臓を自ら抉り、血にまみれたかのような受難のキリストが描かれている。ちなみにこれはキリスト像と、画家本人を重ね合わせた作品らしい。そのグロテスクな表現が頭に焼き付いた。
世紀末絵画展ということで、シーレらのいかにも耽美的でかつ破滅的な作品ばかりが揃っているのかと思いきや、上でも触れたように同時代の自然主義風景絵画など、一筋縄ではいかないこの時期のウィーンの美術の動向全体を知ることの出来る内容に仕上がっていました。決して単なるクリムト、シーレの「名品展」でないところが、この展覧会のむしろ良い面なのかもしれません。
また音楽ファンにとっては、いくつかこの時代に関連する作曲家、もしくは音楽主題の作品がいくつか紹介されているのも嬉しいところです。シュトラウスがワルツを演奏する様子をまるでルノワール絵画の如く華やかに描いたヴィルダの「ランナーとシュトラウス」(1906)の他、マーラーの横顔を銅版で示したオルリクの「グスタフ・マーラー」(1902)、また表現主義画家としても活躍したシェーンベルク作の油彩(計3点)などが印象に残りました。
 「もっと知りたい 世紀末ウィーンの美術/千足伸行/東京美術」
「もっと知りたい 世紀末ウィーンの美術/千足伸行/東京美術」
なお今回は高島屋としては異例の出品リスト付き(受付で申し出るといただけます。)です。これはメモなどをとるのに非常に助かりました。用意して下さってありがとうございます。
10月12日までの開催です。また本展は終了後、以下のスケジュールで巡回します。
【大阪】サントリーミュージアム(天保山) 10/24~12/23
【福岡】北九州市立美術館 2010/1/2~2/28
「ウィーン・ミュージアム所蔵 クリムト、シーレ ウィーン世紀末展」
9/16-10/12
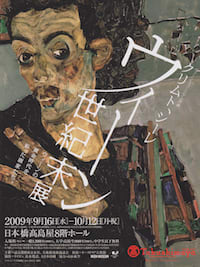
ウィーン・ミュージアム(1887年開館。旧ウィーン市立歴史博物館。)所蔵の、19世紀末から20世紀初頭の世紀末絵画コレクションを概観します。日本橋高島屋で開催中の「ウィーン・ミュージアム所蔵 クリムト、シーレ ウィーン世紀末展」へ行ってきました。
まずは本展の概要、及び見所です。
・ウィーン・ミュージアムのコレクションより、主に1890年から一次大戦の間の30年間にスポットを当てて紹介する。
・出品数は全120点。必ずしも大作メインではなく、小品の他、版画も多い。
・クリムトやシーレなどのいわゆる世紀末絵画の他、平行して発展した自然主義絵画など、多面的に同時代のシーンを追う展覧会でもある。
続いて展覧会の構成です。計5章立てでした。
1「装飾美術と風景画」:ウィーンの都市整備に伴った各種公共建築の装飾絵画。一方でクールベなどの影響下に進展した森や田園の風景絵画など。
2「グスタフ・クリムトとそのサークル」:クリムトとその周辺。代表作「パラス・アテナ」など約10点。
3「エゴン・シーレ」:シーレ。油彩、水彩などあわせて約25点。
4「分離派とウィーン工房」:分離派絵画、「ユーゲント・シュティール」の装飾表現など。
5「自然主義と表現主義」:自然主義絵画、分離派の装飾的表現から一歩、別の方向へと進んだ表現主義作家を紹介。
それでは以下、印象に残った作品を挙げていきます。
フーゴー・ダルナウト「シュトゥーベントーア橋」(1901)
黄昏時の紫の空に下にのびるアーチ橋を描く。橋上を慌ただしく行き交う人々が一日の終わりを告げている。仄かに灯るガスの光が温かい。明かりが川面にまるで舞う蛍のように反射していた。

グスタフ・クリムト「寓話」(1883)
イソップの寓話に基づく画題。中央にはアングル風の美しい白い肌を露出した裸女が立ち、その脇をツルやキツネ、そしてライオンが固めている。これらの動物は多様な民族を表すとのこと。その共存を説いている。クリムトがこのような歴史画風の作品を描いているとは知らなかった。
グスタフ・クリムト「愛」(1895)
両側にパラの花が垂れ下がる金の帯が走り、中央には男女が恍惚とした面持ちで抱擁する姿が描かれている。いかにも愛の美しさを称揚した作品にも思えるが、上部で浮かぶ数名の人物に目がとまった。まるで悪魔のような顔をした老婆などが登場している。その様は二人の脆くて儚い愛をあざ笑うかのようだった。これぞ退廃。

グスタフ・クリムト「パラス・アテナ」(1898)
ちらし表紙にも掲げられた本展のハイライト。自身の結成した分離派の第一回展に出品して賛否を巻き起こした注目作。学問や知恵、そして戦いを示すギリシャの女神が堂々たる姿で描かれている。鱗状になった甲冑はもとより、その絹のような肌をした手で掴む槍など、金を用いて表す装飾はまさにクリムトらなではきらびやかなものだった。中央の魔除けの出す舌を見れば、この作品を見て当時の保守派が怒ったのも無理はないと思う。
エゴン・シーレ「意地悪女」(1910)
シーレの妹がモデルだという人物像。口をつぼめて見る者を罵るかのようにしてこちらを向く女性が描かれている。その大仰なポーズはまるでカリカチュアのようだ。
エゴン・シーレ「ヒマワリ」(1909)
久々に出会った言葉を失うほどに衝撃的な作品。ヒマワリをこのように描いた画家など他にいるのだろうか。白を背景にした縦長の画面の中に、ほとんど無理矢理立たせているかのように干涸らび、また焦げ付き、まさに枯れ果てたヒマワリの姿が描かれている。下に群生する花々はキャプションによれば再生、また未来への希望云々と説明されていたが、私には死人に手向けた花のようにしか見えなかった。
エドゥアルト・シュテラ「踊り子」(1909)
茶碗を手に持ち、つま先立ちで舞を披露するする全裸の踊り子が描かれている。その横向けに露わとなった臀部はことさら卑猥で、正視することすら阻むほどエロチックなムードが漂っていた。
ルートヴィヒ・ハインリヒ・ユングニッケル「マース河畔にて」
スーチンあたりを連想もさせる、やや激しいタッチで描かれた河畔の景色。水面に浮かぶ何隻もの汽船からは、あたかも空を焦がすかのような煙がもうもうと立ち上っている。全体を覆うグレー、もしくは茶色の色調が、近代の到来で痛めつけられた自然の悲哀のようなものを表していた。河はすでに取り返しのつかないほど汚染されている。
マックス・オッペンハイマー「十字架降架」(1913)
出口付近で一際異彩を放っていた作品。まるで心臓を自ら抉り、血にまみれたかのような受難のキリストが描かれている。ちなみにこれはキリスト像と、画家本人を重ね合わせた作品らしい。そのグロテスクな表現が頭に焼き付いた。
世紀末絵画展ということで、シーレらのいかにも耽美的でかつ破滅的な作品ばかりが揃っているのかと思いきや、上でも触れたように同時代の自然主義風景絵画など、一筋縄ではいかないこの時期のウィーンの美術の動向全体を知ることの出来る内容に仕上がっていました。決して単なるクリムト、シーレの「名品展」でないところが、この展覧会のむしろ良い面なのかもしれません。
また音楽ファンにとっては、いくつかこの時代に関連する作曲家、もしくは音楽主題の作品がいくつか紹介されているのも嬉しいところです。シュトラウスがワルツを演奏する様子をまるでルノワール絵画の如く華やかに描いたヴィルダの「ランナーとシュトラウス」(1906)の他、マーラーの横顔を銅版で示したオルリクの「グスタフ・マーラー」(1902)、また表現主義画家としても活躍したシェーンベルク作の油彩(計3点)などが印象に残りました。
 「もっと知りたい 世紀末ウィーンの美術/千足伸行/東京美術」
「もっと知りたい 世紀末ウィーンの美術/千足伸行/東京美術」なお今回は高島屋としては異例の出品リスト付き(受付で申し出るといただけます。)です。これはメモなどをとるのに非常に助かりました。用意して下さってありがとうございます。
10月12日までの開催です。また本展は終了後、以下のスケジュールで巡回します。
【大阪】サントリーミュージアム(天保山) 10/24~12/23
【福岡】北九州市立美術館 2010/1/2~2/28
コメント ( 10 ) | Trackback ( 0 )










