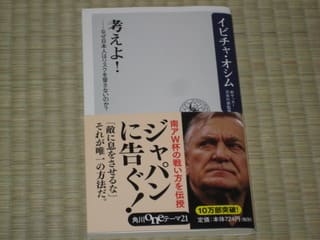副題は「なぜ日本人はリスクを冒さないのか?」
イビチャ・オシム 2010年4月 角川oneテーマ新書
ワールドカップも始まったんで、最近読んだ、日本代表前監督のオシムの本。
日本はワールドカップで勝てるのか勝てないのか、ダメだとしたら、日本のサッカーはどこがダメなのか、何が問題なのか。
そういうことが書いてあって、私はサッカー詳しくないけど、まずまず面白いし、わかりやすく読めた。
いろいろあるんだけど、繰り返し出てくる言葉のひとつが「ディシプリン」。
「ディシプリンが重要」とか「あの選手にはディシプリンがあるとか無いとか」って感じで使われてるんだけど、訳さずにカタカナで「ディシプリン」と表されている。
「discipline」は、私の持っている古い古い辞書(研究社『新英和中辞典』1980年第4版26刷)によれば、「訓練、鍛錬、修養(training)、抑制(control)」って意味だけど、「しつけ、規律(order)、統制」って意味もあるので、訓練のなかでもそういうニュアンスに近いんだと思う。
ちなみに、私の使っている『類語国語辞典』(角川書店)では、>「練習」は、その行為を上達させることを重視し、「訓練」は、教えてすっかり習得させること、「修練」は、「練習」に精神的なものが加わり、抽象的・一般的・総合的に用いられる。「鍛錬」は、もっぱら心身を鍛えることをいう。 ってなってます。
本書では、>すべてのチャレンジに応じられるように、フィジカルとフィットネスを万全に準備し、しっかりとディシプリンを正した状態でいることが肝心だろう。近年のサッカーにおいては、このディシプリンが重要な要素の1つとなっている。2010年1月のアフリカ選手権で優勝したエジプトは、まさに、そのディシプリンで勝利したようなものだ。その戦術に規律正しく沿ったサッカーは、試合としては面白くなかったかもしれないが、日本にとっては参考にしなければならないサッカーだった。 っていうふうに使われてるんで、やっぱ規律ってことなんだと思う。
もうひとつ、あちこちに出てくるのが「コレクティブ」。
「collective」は、辞書では「集合的な、集合性の、集団的な」という意味。
本書では、>戦術的ディシプリンを持ったコレクティブなチームプレー とか、>オランダは、中盤において個の能力だけでなく、コレクティブの面でも日本を上回っている。 とかって使われてるんで、サッカーだし、集団的って意味だと思う。
あと、本書のタイトルにあるとおり、「考えながら走れ!」っていうのも、何かっつーと出てくる。
もっと走れってのは、オシムの重視するスタイルだってことは、私もうすうす知ってるけど。
なんで日本のサッカーは弱いのか、あるいはサッカーに限らずほかのスポーツでも、勝てないのかダメなのかということを、日本人の国民性・国柄みたいなものに引きつけて論じるのは、よくみかける手法だけど、私はあんまり好きぢゃない。
そういうのは、安易な結論ありきのこじつけにすぎないように思うからである。そういう態度は何も生み出さない。
そのへんで、この本は、サッカーに関して具体的なポイントを指摘してるし、日本にもいいところはいっぱいあることも語ってるし、そんな不快な組み立てではないと感じている。
私個人の感じでは、もし日本のサッカーが弱いとしたら、それはボールを置いたところから練習を始めるのが多すぎるからぢゃないかと思っている。
フリーキックの練習するよりも、ボールを動かして運びながら、パスなりシュートなりする時間を増やしたほうがいいんぢゃないかと思う。実際には、ボールは動いてる時間のほうが多いんだから。みんながやりたがる、止まったボールを理想的に蹴る練習なんて、ボールが動いてて目の前には敵がいる状態で役に立たないんぢゃないかと。
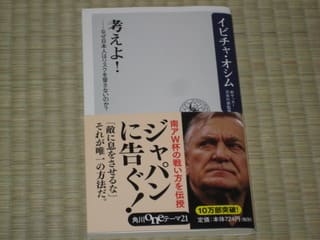
イビチャ・オシム 2010年4月 角川oneテーマ新書
ワールドカップも始まったんで、最近読んだ、日本代表前監督のオシムの本。
日本はワールドカップで勝てるのか勝てないのか、ダメだとしたら、日本のサッカーはどこがダメなのか、何が問題なのか。
そういうことが書いてあって、私はサッカー詳しくないけど、まずまず面白いし、わかりやすく読めた。
いろいろあるんだけど、繰り返し出てくる言葉のひとつが「ディシプリン」。
「ディシプリンが重要」とか「あの選手にはディシプリンがあるとか無いとか」って感じで使われてるんだけど、訳さずにカタカナで「ディシプリン」と表されている。
「discipline」は、私の持っている古い古い辞書(研究社『新英和中辞典』1980年第4版26刷)によれば、「訓練、鍛錬、修養(training)、抑制(control)」って意味だけど、「しつけ、規律(order)、統制」って意味もあるので、訓練のなかでもそういうニュアンスに近いんだと思う。
ちなみに、私の使っている『類語国語辞典』(角川書店)では、>「練習」は、その行為を上達させることを重視し、「訓練」は、教えてすっかり習得させること、「修練」は、「練習」に精神的なものが加わり、抽象的・一般的・総合的に用いられる。「鍛錬」は、もっぱら心身を鍛えることをいう。 ってなってます。
本書では、>すべてのチャレンジに応じられるように、フィジカルとフィットネスを万全に準備し、しっかりとディシプリンを正した状態でいることが肝心だろう。近年のサッカーにおいては、このディシプリンが重要な要素の1つとなっている。2010年1月のアフリカ選手権で優勝したエジプトは、まさに、そのディシプリンで勝利したようなものだ。その戦術に規律正しく沿ったサッカーは、試合としては面白くなかったかもしれないが、日本にとっては参考にしなければならないサッカーだった。 っていうふうに使われてるんで、やっぱ規律ってことなんだと思う。
もうひとつ、あちこちに出てくるのが「コレクティブ」。
「collective」は、辞書では「集合的な、集合性の、集団的な」という意味。
本書では、>戦術的ディシプリンを持ったコレクティブなチームプレー とか、>オランダは、中盤において個の能力だけでなく、コレクティブの面でも日本を上回っている。 とかって使われてるんで、サッカーだし、集団的って意味だと思う。
あと、本書のタイトルにあるとおり、「考えながら走れ!」っていうのも、何かっつーと出てくる。
もっと走れってのは、オシムの重視するスタイルだってことは、私もうすうす知ってるけど。
なんで日本のサッカーは弱いのか、あるいはサッカーに限らずほかのスポーツでも、勝てないのかダメなのかということを、日本人の国民性・国柄みたいなものに引きつけて論じるのは、よくみかける手法だけど、私はあんまり好きぢゃない。
そういうのは、安易な結論ありきのこじつけにすぎないように思うからである。そういう態度は何も生み出さない。
そのへんで、この本は、サッカーに関して具体的なポイントを指摘してるし、日本にもいいところはいっぱいあることも語ってるし、そんな不快な組み立てではないと感じている。
私個人の感じでは、もし日本のサッカーが弱いとしたら、それはボールを置いたところから練習を始めるのが多すぎるからぢゃないかと思っている。
フリーキックの練習するよりも、ボールを動かして運びながら、パスなりシュートなりする時間を増やしたほうがいいんぢゃないかと思う。実際には、ボールは動いてる時間のほうが多いんだから。みんながやりたがる、止まったボールを理想的に蹴る練習なんて、ボールが動いてて目の前には敵がいる状態で役に立たないんぢゃないかと。