今夜は、何ヶ月振りかのプライベート飲み会。
少しづつ増えてくるかな?
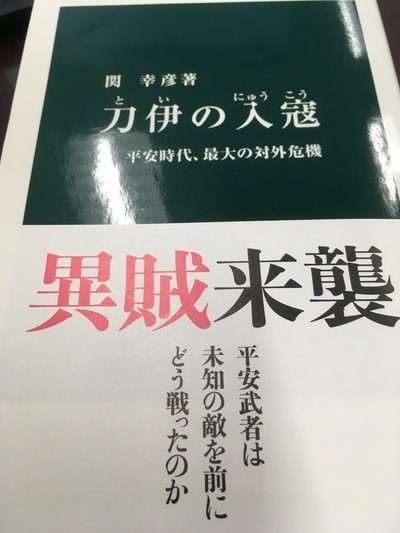
本書は、8月に出たばかり。
刀伊の入寇と言われても、ぴんと来ない人が多いと思われる。
元寇だとわかるが。
私もその内の一人だったが、平安時代の出来事を扱った本ということで読んでみた。
刀伊の入寇は、今からほぼ千年前の1019年に、中国東北部の女真族が攻めてきた事件。
刀伊というのは、東夷のことという。
最初からびっくり。
女真族は、契丹と敵対しており、海賊化し、南の高句麗(元新羅)を経て、日本まで攻め込んできた。
突如として、来たものだから、混乱もあったが、双方大きな被害を出した上で、撃退し、刀伊は、その帰りに、高句麗に撃退されることとなる。
日本からの捕虜の生き残りは、高句麗で保護され、日本に帰国できたものもいた。
貴重な記録も残している。
本書は、その戦いそのものよりも、東アジアの情勢、日本の武家社会への移行過程に関する部分に、より頁がさかれている。
日本は、国を開く時期と、閉じる時期が交互にあり、この時代は、遣唐使も途絶え、閉じていた時期になる。
朝鮮半島では、高句麗が新羅に代わって統一したが、日本とは敵対関係にあった。
中国も唐の後、混乱状態にあり、特に、東北部は、契丹と女真族が争っていた。
秩序が乱れていた時期で、その中で、この侵攻は起こった。
一方日本は、平安時代で、藤原家が、栄えていたが、鎮西と、蝦夷は、紛争地域であり、中央から、やんごとなき武士が派遣されていた。彼らが、武家社会へ移行する核となっていく。
派遣された貴族武士は、事が起こったら、地元住民を巻き込んで、戦い、その様子は、中央にもタイムリーに報告されていたという。
ただ、徴兵的な制度から、傭兵的な制度に移行しつつある時期で、報償なども、単に位を与える程度の、中途半端なものだったと考えられるという。
まさに、貴族社会→武家社会への移行期。
その中で、この刀伊の入寇と、蝦夷における前九年の役は、大きな転機となった。
刀伊の入寇という事件を切り口として、当時の社会の変化を描きだした本だった。
少しづつ増えてくるかな?
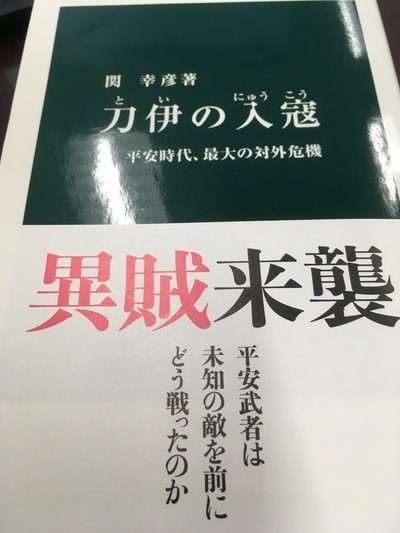
本書は、8月に出たばかり。
刀伊の入寇と言われても、ぴんと来ない人が多いと思われる。
元寇だとわかるが。
私もその内の一人だったが、平安時代の出来事を扱った本ということで読んでみた。
刀伊の入寇は、今からほぼ千年前の1019年に、中国東北部の女真族が攻めてきた事件。
刀伊というのは、東夷のことという。
最初からびっくり。
女真族は、契丹と敵対しており、海賊化し、南の高句麗(元新羅)を経て、日本まで攻め込んできた。
突如として、来たものだから、混乱もあったが、双方大きな被害を出した上で、撃退し、刀伊は、その帰りに、高句麗に撃退されることとなる。
日本からの捕虜の生き残りは、高句麗で保護され、日本に帰国できたものもいた。
貴重な記録も残している。
本書は、その戦いそのものよりも、東アジアの情勢、日本の武家社会への移行過程に関する部分に、より頁がさかれている。
日本は、国を開く時期と、閉じる時期が交互にあり、この時代は、遣唐使も途絶え、閉じていた時期になる。
朝鮮半島では、高句麗が新羅に代わって統一したが、日本とは敵対関係にあった。
中国も唐の後、混乱状態にあり、特に、東北部は、契丹と女真族が争っていた。
秩序が乱れていた時期で、その中で、この侵攻は起こった。
一方日本は、平安時代で、藤原家が、栄えていたが、鎮西と、蝦夷は、紛争地域であり、中央から、やんごとなき武士が派遣されていた。彼らが、武家社会へ移行する核となっていく。
派遣された貴族武士は、事が起こったら、地元住民を巻き込んで、戦い、その様子は、中央にもタイムリーに報告されていたという。
ただ、徴兵的な制度から、傭兵的な制度に移行しつつある時期で、報償なども、単に位を与える程度の、中途半端なものだったと考えられるという。
まさに、貴族社会→武家社会への移行期。
その中で、この刀伊の入寇と、蝦夷における前九年の役は、大きな転機となった。
刀伊の入寇という事件を切り口として、当時の社会の変化を描きだした本だった。















