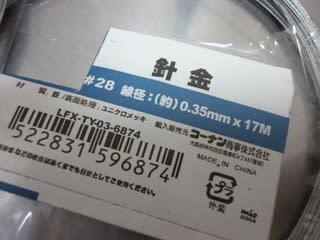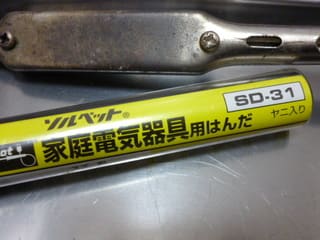自転車のタイヤに空気を入れる時コンプレッサーのホースの先に付いている
先端パーツをタイヤチャックと呼びますが これは自転車屋さんでは良く
見掛けます その多くが英式と米式バルブとの兼用ですが今迄、仏式用が
無く皆が工夫していました

エアーコンプレッサーのホースの先端 これは
良く見掛けるタイプですよね


このパーツの頭は上の英式バルブ用と 下の米式用と
両サイドが使える様になっています

しかしこの先端工具のフレンチバルブ用が中々無く
仏式に使うには色々と工夫をします


上の黒い物はフロアポンプ用のヘッド 下の小さな
物は SILCA シリカのディスク用のアダプターを
コンプレッサーで使える様にしています

ただ前述のポンプヘッドは ホースを繋ぐとエアーが
出っ放しになるので ヘッドの手前にこの様な開閉用の
レバーを工夫する必要も有ります


今回見付けたのがこれ フレンチ用のエアチャックです
発売元は STRAIGHT TOOL ストレートツール この会社は
車関係の工具類が多いのですが 最近自転車関連も少し
扱い始めています
ここは Webショップも充実していて利用される方も
多いと思いますが幸いにも実店舗が近くに有るので
たまに覗くと今回の様な物と出会えます


これも片方が米式 その反対が仏式用になっており
口金にバルブを当て中心部の金色の突起を押し込むと
エアーが出る構造です フレンチ側も内部に同じ機構を
持っています


このエアーチャックも今自分が使ってるホースの
先端に依り必要な物が変わって来ますが それ程
難しい事では有りません 私は 1/4サイズのメネジ
を切ったプラグを装着


それを取り付け コンプレッサー用のホースへ
ワンタッチで取り付け これで直ぐに使う事が
出来ます


米式用と仏式用


バルブコアのネジを緩め エアーチャックを挿入し
奥まで押し込めば O.K しっかりとエアーが充填
出来ました
この口金 ヒラメの様にゴムパッキンの開閉機能が
無いので 多くのポンプヘッドの様に入れる時は良いが
抜く時が固い、この現象が起きます しかしお値段が
880円程度 長く探しても無かったパーツ、むしろ喜ぶ
べきですよね
先端パーツをタイヤチャックと呼びますが これは自転車屋さんでは良く
見掛けます その多くが英式と米式バルブとの兼用ですが今迄、仏式用が
無く皆が工夫していました

エアーコンプレッサーのホースの先端 これは
良く見掛けるタイプですよね


このパーツの頭は上の英式バルブ用と 下の米式用と
両サイドが使える様になっています

しかしこの先端工具のフレンチバルブ用が中々無く
仏式に使うには色々と工夫をします


上の黒い物はフロアポンプ用のヘッド 下の小さな
物は SILCA シリカのディスク用のアダプターを
コンプレッサーで使える様にしています

ただ前述のポンプヘッドは ホースを繋ぐとエアーが
出っ放しになるので ヘッドの手前にこの様な開閉用の
レバーを工夫する必要も有ります


今回見付けたのがこれ フレンチ用のエアチャックです
発売元は STRAIGHT TOOL ストレートツール この会社は
車関係の工具類が多いのですが 最近自転車関連も少し
扱い始めています
ここは Webショップも充実していて利用される方も
多いと思いますが幸いにも実店舗が近くに有るので
たまに覗くと今回の様な物と出会えます


これも片方が米式 その反対が仏式用になっており
口金にバルブを当て中心部の金色の突起を押し込むと
エアーが出る構造です フレンチ側も内部に同じ機構を
持っています


このエアーチャックも今自分が使ってるホースの
先端に依り必要な物が変わって来ますが それ程
難しい事では有りません 私は 1/4サイズのメネジ
を切ったプラグを装着


それを取り付け コンプレッサー用のホースへ
ワンタッチで取り付け これで直ぐに使う事が
出来ます


米式用と仏式用


バルブコアのネジを緩め エアーチャックを挿入し
奥まで押し込めば O.K しっかりとエアーが充填
出来ました
この口金 ヒラメの様にゴムパッキンの開閉機能が
無いので 多くのポンプヘッドの様に入れる時は良いが
抜く時が固い、この現象が起きます しかしお値段が
880円程度 長く探しても無かったパーツ、むしろ喜ぶ
べきですよね