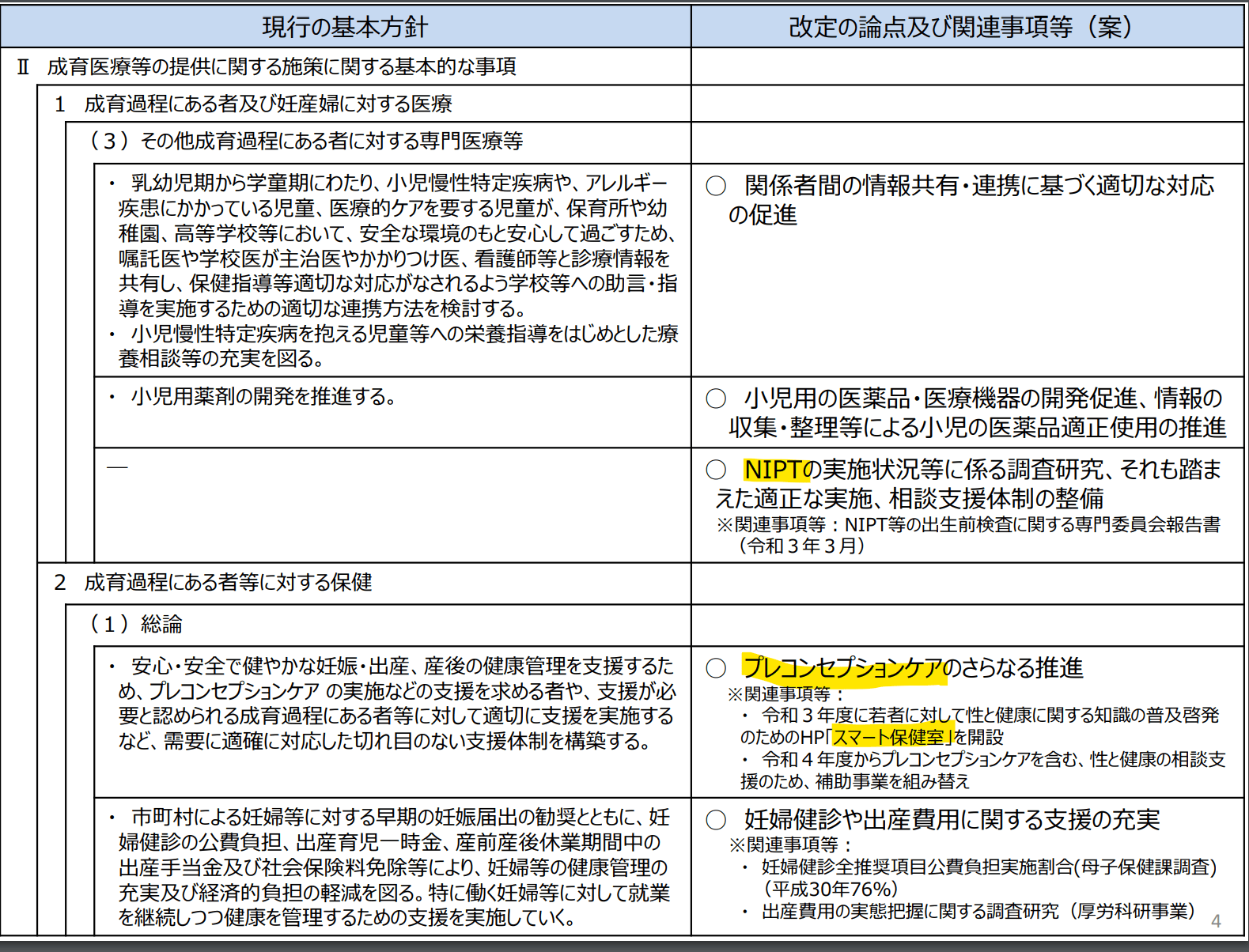本日の成育医療等協議会で出された貴重な意見。
中央区の子育て施策において、施策の点検にも活かして行きたいと思いました。
貴重なご意見ありがとうございました。
委員の皆様、お疲れ様でございました。
*******************
1、5歳児健診ができていない中では、保育園の健診の情報共有を。
2、厚労省の健康教育と、学校保健の健康教育 連携を。
3、県の医療計画立案の前に、成育医療の方針を出すこと。
4、「子ども家庭庁」とどう連携するか。
5、学校の健診は、高い受診率であるが、うまく、課題が解決されるものへとするには、どうするか。
6、助産師外来の設置。きがかりな妊婦の把握などで。
7、ICTをどう活用するか。
8、適切な情報共有をできるように。食事、生活、保健などの包括的な情報の共有。
9、栄養の観点を入れていく。
10、子どもの意見を取り入れる。
11、産後ケア、普遍的に利用できるようにはできていない。
出産費用も、差が大きい。
12、地域の情報を妊娠中から得られるように。
13、医ケア児に対応できる訪問歯科の人材が少ない。養成を。
14、妊婦の歯科検診も広がりがまだ。
15、産後ケアのサービスを、広域連携でできるような施設配置を。町村が持てない場合など。
16、費用負担の軽減。「個別支援」などいうと、自治体間で格差がでるため、財源確保した上で、施策をいうべき。
17、子ども意見を聞けることの情報発信、子ども家庭支援センターとの連携。
18、チャイルド・デス・レビューCDRをモデル事業から発展を。
19、グリーフサポート、ピアサポート、当事者支援。
20、産後ケア、人材不足ゆえ、人材育成を。
21、学校に、ソーシャルワーカーを入れることで、地域とつながり飛躍的によくなる。
22、ガイドラインを用いることを方針にいれる。
23、成育医療を、使えるように広報を。
24、「母子保健」の母子の表現の現代的な検証。夫婦でという概念の導入。
25、第2子以降の里帰り出産における兄弟姉妹の保育園問題。在籍園、里帰り地区の保育。
26、次回まで6年の見直しは長いための対応を。
など。
*******たまたま「こども家庭庁」の記事、日経新聞2022.5.18******

















 議事次第 第7回成育医療等協議会[PDF形式:74KB]
議事次第 第7回成育医療等協議会[PDF形式:74KB]