日本人の清潔好きは世界でも有名ですが、過度の清潔は自己免疫力を弱めるみたいです。
---------- 【ここから引用】 ----------
【AFPBBニュース】幼少期の清潔すぎる環境は成人後の疾病リスクを高める 2009年12月10日 09:59 発信地:ワシントンD.C./米国
http://www.afpbb.com/article/life-culture/health/2673173/5019874
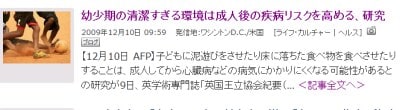
研究の主著者である米ノースウエスタン大(Northwestern University)のトーマス・マクデイド(Thomas McDade)准教授(人類学)は「幼少期に非常に清潔で衛生的な環境にいると、成人してから炎症を起こしやすくなり、多様な疾病にかかるリスクが高まる可能性があることが分かった」としている。
研究チームは、フィリピンの大学が行った、子ども時代の環境がタンパク質の生成にもたらす影響に関する調査を分析した。タンパク質は炎症が起こると増加する。これは体が感染やけがと闘っているサインとみることができる。
調査は1980年代にフィリピンで生まれた子ども3327人の母親を対象に、最初の2年は2か月ごとに、その後は子どもが20代になるまで4~5年ごとに、子どもを取り巻く衛生環境などについて追跡調査するもの。
研究チームは調査の中から、ブタや犬などの家畜が放し飼いになっているかなどの「衛生状態」と家族の「社会経済的状態」を分析。その結果、フィリピン人は米国人に比べ、幼少期にずっと多くの感染症にかかっている一方、成人後の血中C反応性タンパク(CRP)の濃度は80%も低いことが分かった。フィリピン人の20代前半の平均CRP濃度が1リットル当たり0.2ミリグラムだったのに対し、米国人のそれは1.0~1.5ミリグラムだった。
研究から、CRP濃度の高い成人は、幼少期に家庭で動物の排泄物にさらされる機会が少なかったことが分かった。
マクデイド准教授は、幼少期に一般的な微生物や細菌にさらされることが重要だと指摘する。「これらの微生物や細菌が臨床疾患につながることは決してない一方、調節ネットワークの形成において重要な役割を果たす」のだという。
准教授は、免疫系の発達にも脳の発達と同様に環境との関わりが必要だとし、自身の2歳半の息子が床に食べ物を落としたときには、「迷うことなく拾って食べるように言う」のだそうだ。(c)AFP/Karin Zeitvogel
---------- 【引用ここまで】 ----------
日本で生活をする分にはなんでもない人でも、中国やインドなどへ行くとすぐに下してしまうみたいです。
バングラデシュに数年間滞在したことのある知人は、「向こうにいる間はずっと腸が緩かったですよ。腸の中で細菌が入れ替わるような気がしたものです」と言っていました。
普通の日本人ならば、そうしたところへの旅行中は瓶詰めのミネラルウォーターかビールしか飲めないのが普通のようですし。
日本では当たり前の清潔の度合いも、世界標準では過保護ということなのでしょうね。日本で落としたものを拾って食べるくらいではとても世界標準には追いつかないかもしれませんが、それでも3秒ルールなどで落としたものも素早く拾って食べるようにしたいものです。
そのことが自分を鍛えていることだったとはねえ。生活のレベルが高すぎるというのも考えもの。不便や少し足りないくらいがちょうど良いのかもしれません。
占いでも中吉が良い、大吉だったらあとは下がるだけ、と言いますもんね。
---------- 【ここから引用】 ----------
【AFPBBニュース】幼少期の清潔すぎる環境は成人後の疾病リスクを高める 2009年12月10日 09:59 発信地:ワシントンD.C./米国
http://www.afpbb.com/article/life-culture/health/2673173/5019874
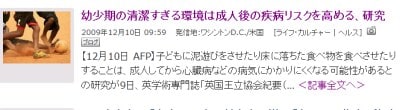
研究の主著者である米ノースウエスタン大(Northwestern University)のトーマス・マクデイド(Thomas McDade)准教授(人類学)は「幼少期に非常に清潔で衛生的な環境にいると、成人してから炎症を起こしやすくなり、多様な疾病にかかるリスクが高まる可能性があることが分かった」としている。
研究チームは、フィリピンの大学が行った、子ども時代の環境がタンパク質の生成にもたらす影響に関する調査を分析した。タンパク質は炎症が起こると増加する。これは体が感染やけがと闘っているサインとみることができる。
調査は1980年代にフィリピンで生まれた子ども3327人の母親を対象に、最初の2年は2か月ごとに、その後は子どもが20代になるまで4~5年ごとに、子どもを取り巻く衛生環境などについて追跡調査するもの。
研究チームは調査の中から、ブタや犬などの家畜が放し飼いになっているかなどの「衛生状態」と家族の「社会経済的状態」を分析。その結果、フィリピン人は米国人に比べ、幼少期にずっと多くの感染症にかかっている一方、成人後の血中C反応性タンパク(CRP)の濃度は80%も低いことが分かった。フィリピン人の20代前半の平均CRP濃度が1リットル当たり0.2ミリグラムだったのに対し、米国人のそれは1.0~1.5ミリグラムだった。
研究から、CRP濃度の高い成人は、幼少期に家庭で動物の排泄物にさらされる機会が少なかったことが分かった。
マクデイド准教授は、幼少期に一般的な微生物や細菌にさらされることが重要だと指摘する。「これらの微生物や細菌が臨床疾患につながることは決してない一方、調節ネットワークの形成において重要な役割を果たす」のだという。
准教授は、免疫系の発達にも脳の発達と同様に環境との関わりが必要だとし、自身の2歳半の息子が床に食べ物を落としたときには、「迷うことなく拾って食べるように言う」のだそうだ。(c)AFP/Karin Zeitvogel
---------- 【引用ここまで】 ----------
日本で生活をする分にはなんでもない人でも、中国やインドなどへ行くとすぐに下してしまうみたいです。
バングラデシュに数年間滞在したことのある知人は、「向こうにいる間はずっと腸が緩かったですよ。腸の中で細菌が入れ替わるような気がしたものです」と言っていました。
普通の日本人ならば、そうしたところへの旅行中は瓶詰めのミネラルウォーターかビールしか飲めないのが普通のようですし。
日本では当たり前の清潔の度合いも、世界標準では過保護ということなのでしょうね。日本で落としたものを拾って食べるくらいではとても世界標準には追いつかないかもしれませんが、それでも3秒ルールなどで落としたものも素早く拾って食べるようにしたいものです。
そのことが自分を鍛えていることだったとはねえ。生活のレベルが高すぎるというのも考えもの。不便や少し足りないくらいがちょうど良いのかもしれません。
占いでも中吉が良い、大吉だったらあとは下がるだけ、と言いますもんね。

















