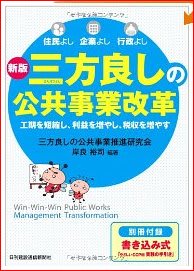さて問題です。
「上司から緊急の仕事頼まれました。さてやろうとすると、別な上司からも『すまん、これ急ぎでやってくれないか』という指示。ところがさらに別な3人目の上司から『頼む、これ大至急やって』という依頼が。こんなときあなたならどうしますか。どれから取り掛かるべきか。いっそ全部とりかかろうか…、どうしよう」
こんな状況が少なからずあると思いますが、実はこれ、今日職場で行われた講演会での講師からの質問でした。
いわゆるマルチタスク状態に陥った時に、どういう順番で仕事をするのが良いか、というのがポイントです。
そこで講師は、三つの作業をする一つのゲームを参加者にさせました。
それは、まず紙を用意して、一つ目のミッションは縦に数字を1から20まで書くもの、二つ目のミッションは、縦にアルファベットをaからtまで書くもの、そして三つ目は、「〇△◇」をこの順番で20個書くというもの。

これを、最初は、1→a→○→2→b→△→…と繰り返して、最後までいくやり方を行ってみます。
大体一文字を書くのは、0.3秒といわれるそうですが、まあ甘く見て一個1秒として、「用意、ドン」で皆一斉に書き始めます。
講師は時計を見ながら、「できた人から手を上げてくださいね」と言いましたが、結局目標の1分以内に書き上げた人は一人もいませんでした。
◆
次に、同じ三種類の文字を20個ずつ書くミッションを、今度は数字だけ1、2、3…と書いて、書き終わったら今度はアルファベットをa、b、c…と書き、最後に「〇△◇」を繰り返し書きます。
これまた「用意、ドン」で書き始めてみたところ、最速で終わった人が35秒で手を挙げて、皆続々と手が上がり、ほぼ全員が1分以内に書き上げることができました。
これは「マルチタスクゲーム」と言うそうですが、つまりは、最初にあった、三人の上司から急ぎの仕事を頼まれたときにどうすればよいか、を考えると、まずどれか一つから初めて最後まで終わらせてから、次に取り掛かるのが効率的だ、ということになるのです。
実際にやってみると、横に書いてゆくと数字からアルファベットに意識を写してさらに図形を考えるとなると、脳がイライラしているのが分かります。
同じ人がやって、出来上がった成果は同じものなのに、時間は半分でストレスも少ないやり方があるというわけ。
実際にやってみてください、驚くほどの差が出るものですよ。
◆ ◆ ◆
これは今日の講演の、「三方良しの公共事業改革」のなかの一コマでしたが、つまりさまざまな無駄を日常の仕事の中からみつけてこれを修正してゆくことで、部分最適ではなく、全体としての最適を見出そう、というのが趣旨。
これ以外にもシステムに内在するさまざまな無駄に至る例を示して、結果として成果を向上させることはもちろんですが、それに参加するチームのスタッフがストレスなく、やる気に満ちて達成感と幸せを感じるようになるための様々な工夫を教えてくれました。
講師は国交省のOBで元上司だった方ですが、こういう教養溢れる話を同じ国交省職員から聴けて大変に勉強になりました。
仕事を多面的に見る癖をつけて様々な外部の理論を勉強したところから得たお話は実にためになりました。
ちなみにこの「三方良しの公共事業改革」は同タイトルでの書籍が出ています。 → http://amzn.to/Zp8I78
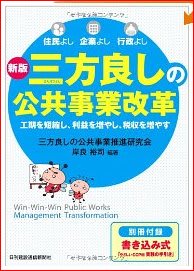
仕事のちょっとした癖や、人間の業みたいなものも見えてきます。
仕事のやり方をよく考えさせられる時間でした。講師のOさん、ありがとうございました。