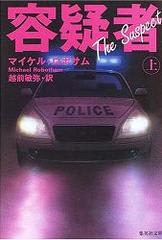
警察の捜査に協力しているつもりが、気がついたらなんと容疑者になっていた。臨床心理士のジョーゼフ・オローリンは、母でさえハンサムだと言わなかったし、茶色い髪は癖が強く、鼻は洋梨型で、日差しを少しでも浴びるとそばかすが出来るという四十二歳の男だった。
家族は大学時代に見初めたジュリアンと一人娘のチャーリーの三人。ジョーゼフは、配偶者が無料で尋ねる質問を、金をもらって尋ねる専門家というジョークの定義はともかく、患者の問題に耳を傾け、そこにひそむ意味を見つけ、本人の自尊心を打ちたて、あるがままの自分を受け入れるように導くことに専心していた。
いろんな症状の患者が来る。渡橋恐怖症や砂漠恐怖症など、高所恐怖症に閉所恐怖症は誰にでも少しはあるだろう。わたしの場合、それに踏切恐怖症と首都高恐怖症に橋上恐怖症が加わる。だからといって冷や汗が出るわけでもない。
踏切での事故や大地震で高速道路の橋脚が崩れたり橋が落ちたりしたのが軽い恐怖症として残っている。
ジョーゼフの身に起こることの発端は、元患者のキャサリンが殺されたことから始まる。身の潔白を証明するために調査を進めると意外な事実が浮かび上がってくる。前半は少し退屈気味だったが、後半はテンポよく展開もスピーディーで、適度のユーモアに彩られた文章と会話による人物造型が印象に残る。
一人娘のチャーリーの可愛さ、可愛いという言葉を使わずに表現している。妻ジュリアのたくましさ友人のジョック、父・母などが鮮やかに描かれる。
著者は、シドニー、カリフォルニア、ロンドンでジャーナリストとして活動。1993年から著述活動に専念し、ゴーストライターとして各界の著名人の自伝10作を手がけベストセラーとなる。初の小説である本書は10数ヶ国語に翻訳され、すでに30ヶ国以上で刊行されている。
















