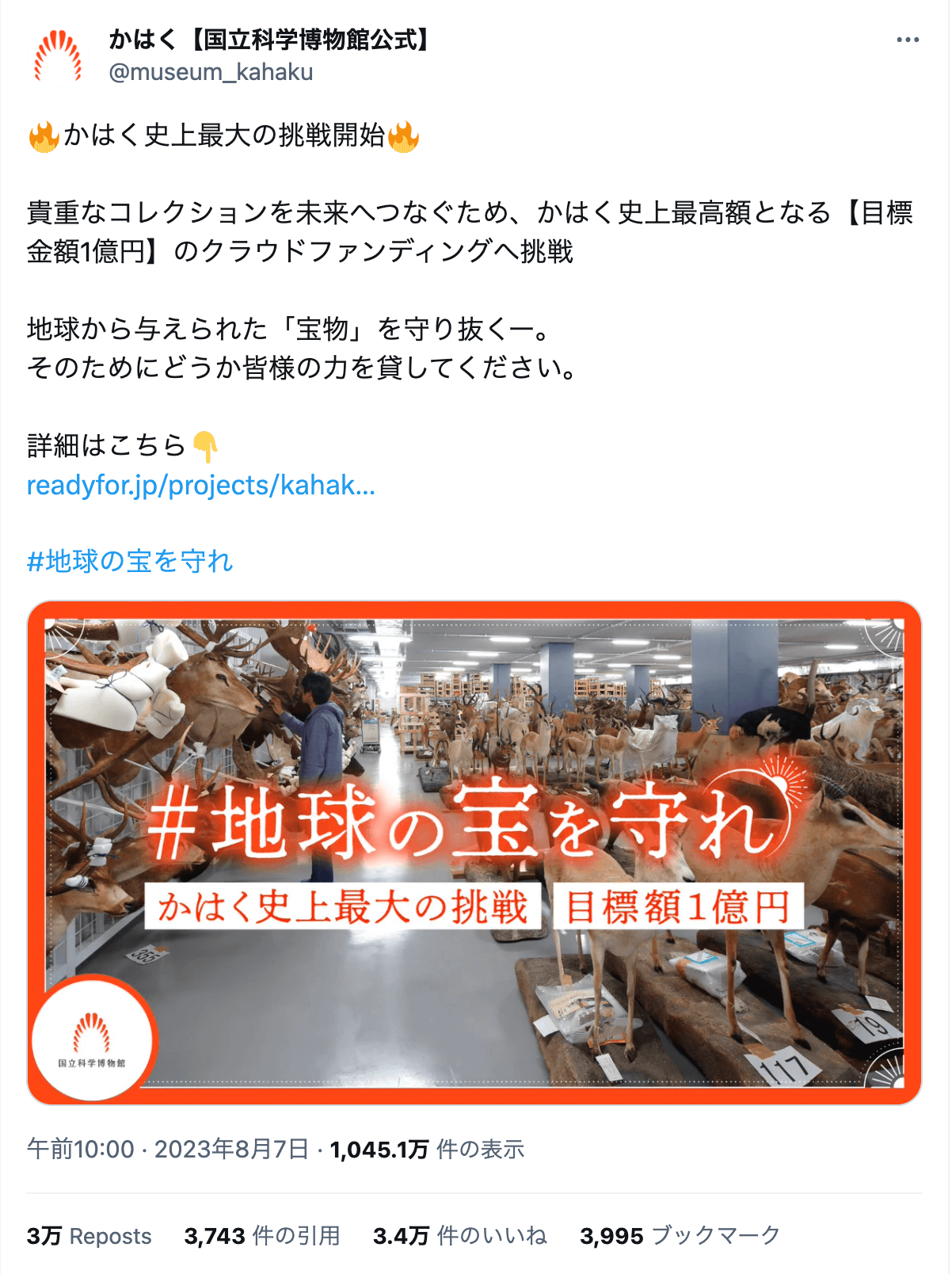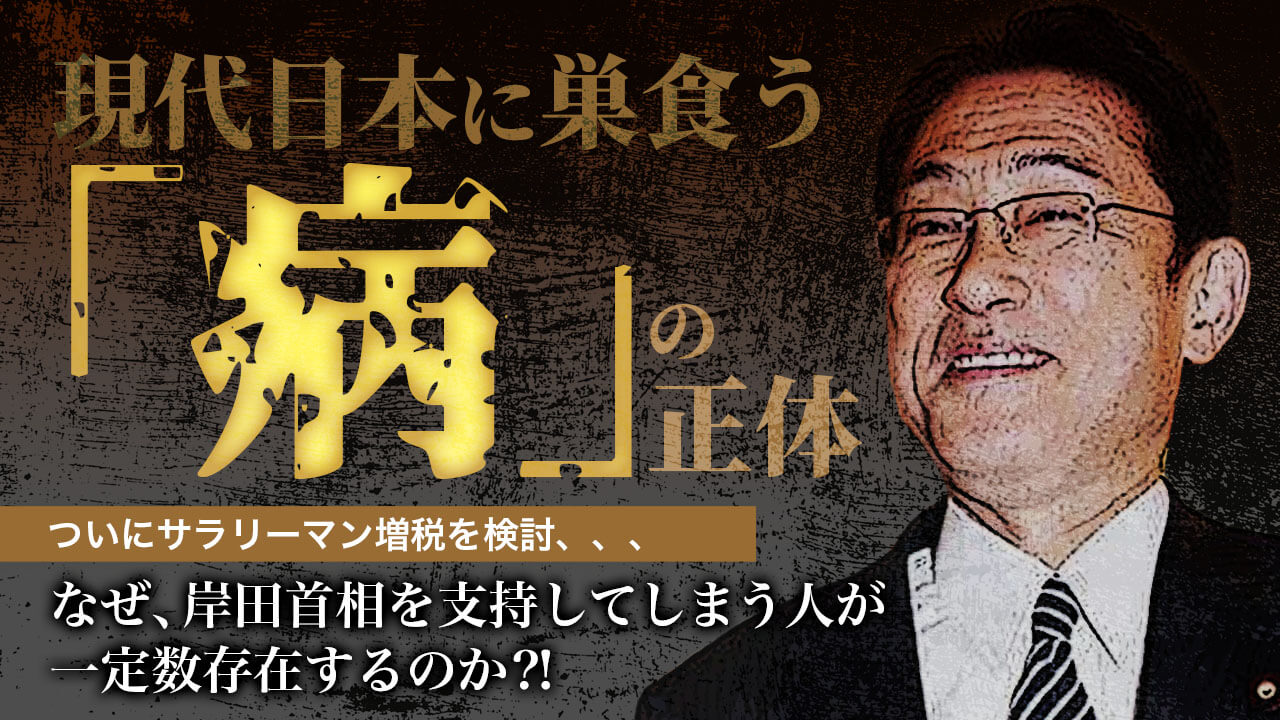「緩和医療に携わる人は、ちょっと変わっている」――。
これは医療界での定説(?)になりつつあるのでしょうか。“変わり者認定”された緩和医療関係者が集う我らが日本緩和医療学会の学術大会も、多少変わっているのかもしれません。今回は、そんな変わり者の一人、緩和医療専門医である筆者が、アナタの知らない学術大会の様子をご紹介します。
大規模集会にありがちな会場のマンネリ化、緩和医療学会のひと工夫
第28回日本緩和医療学会学術大会は2023年6月30日-7月1日の2日間、神戸コンベンションセンターで開催されました(現地とオンラインのハイブリッド開催)。
参加者は例年およそ8000人にのぼります。これだけの大人数になると会場が限られることから、ここ数年は神戸コンベンションセンターかパシフィコ横浜のどちらかが会場となっています。
学術大会と言えば「毎年異なる土地で開催されるもので、空き時間を見つけては観光し、名産品に舌鼓をうつ」のが楽しみの一つですが、開催地が2カ所に限られると、ややマンネリ感が否めません。
そんな参加者の気持ちを察してか、最近の本学術大会のランチョンセミナーでは日本各地の駅弁が選べる仕組みになっています。企業展示コーナーには各地の名産品を購入できるブースが用意されるなどの心配り(?)もあり、さながら百貨店の都道府県物産展の光景です。今回、東日本から参加されたある先生は、広島名物のあなご飯の弁当を食べ、伊勢名物の赤福をお土産に買っていかれました。

筆者は「神戸のすきやき&ステーキ弁当」と「二代目あなごあいのせ重」をいただきました
マイナー領域の学術大会になぜ参加者が多いのか
冒頭から話が弁当に逸れてしまったので戻します。
自分たちで言うのも何ですが、なぜこんなマイナー領域の学術大会の参加者がこれほどまでに多いのでしょうか。
それはズバリ、医師以外の職種の参加者が多いからです。そもそも日本緩和医療学会の会員数は2023年7月現在1万2074名ですが、そのうち医師・歯科医師は6473名、53.6%に過ぎません。看護師、薬剤師、心理士、リハビリセラピスト、栄養士、ソーシャルワーカー等が半数近くを占めており、学術大会にもこれらの職種の方が参加・発表しているのです。
学術大会では、セッションの多くを多職種の演者で構成できるおかげで、緩和医療の根幹であるチーム医療の多様性や連携について知ることができますし、1つのテーマについて多様な視点を通して学ぶことができます。医師が看護ケアに関する講演を聴くこともできますし、治療薬や診療ガイドラインの解説を医師以外の職種が聴講することも可能です。
緩和医療・緩和ケアには医学や看護・薬理・心理・社会福祉の内容を分け隔てなく取り扱う能力が求められます。そのために、各自の専門性を超えて広く学ぶ機会が設けられているのです。

ワークショップ「入院中のオピオイド自己管理に向けた取り組み」開始前の一コマ。
筆者も演者を務めました。
アロハ+短パン姿も、独特の空気感
多職種が参加しているせいもあってか、日本緩和医療学会の学術大会は参加者の服装もさまざまです。過日の会は「クールビズ」が謳われていましたが、第一線で活躍する先生がアロハシャツ+短パン姿で参加されていたのは新鮮でした。女性は華やかでスマートカジュアルな服装の方が多くいます。一面スーツ姿の医師が居並ぶ「学会あるある風景」を、この領域の学術大会で目にすることはありません。
私がいわゆる「学会」というものに初めて参加したのは、大学6年生の時。病院実習の一環で参加した日本医学放射線学会学術集会(会場はパシフィコ横浜)でした。落ち着いた色合いのスーツ姿の先生方で会場が埋まり、独特の緊張感を醸していて、「これが『学会』というものなんだ!」と感動したのを覚えています。
私自身も真っ黒なリクルートスーツに身を包み、少し誇らしげに名札を首から下げて、“医師風”を吹かせてみたことが思い出されます。課題であった講演を聴講したあとはランチョンセミナーのお弁当をありがたく頂戴し、早々に会場を抜け出してレンタサイクルで横浜市内を観光し、夜は担当教官の先生に中華街でご馳走になったのでした。
あれから15年。初期研修後すぐに緩和医療に進んだ私にとっては、一面スーツ姿という「学会あるある風景」の方がご無沙汰になってしまいましたが、他科から転科したり、初めて緩和医療学会に参加した先生方からはいつも、「独特の雰囲気に驚いた」といったコメントをいただきます。ちなみにこの緩和医療学会の雰囲気は世界共通のようで、海外の緩和医療関連学会に参加した時には、同じような空気感に親しみを覚えたのでした。
アンバサダーが講演スライドを撮影、要約してX投稿
これだけ多数の参加者を誇る日本緩和医療学会学術大会ではありますが、残念ながら、緩和医療に関わる医療者は決して多くありません。特に医師の数は少なく、所属診療科も内科、外科、精神科、麻酔科などさまざまで、専門医を育成する教育体制も十分とは言えません。専門的な緩和医療が提供されている地域は限られており、緩和医療について十分な指導が受けられず、後進が育たないという課題もあります。
コロナ禍で学会や研究会、セミナーがオンライン開催されるようになり、これまで現地参加がかなわなかった方々も最先端の知識を学ぶ機会が得られるようになりました。日本緩和医療学会でもこの流れに沿った取り組みを行っており、これから緩和医療を勉強したいという人にとってハードルが下がったと思います。しかし、さらに多くの医療者に緩和医療の専門性や重要性を伝え、緩和医療をより身近なものとして広めていく必要があります。
現在、私は本学会広報委員会の委員を務めており、医療者を対象として緩和ケア・緩和医療に関する正しい知識をわかりやすく伝える取り組みを行っています。学会や緩和ケア自体のブランド力の強化と認知度の向上、そして緩和ケアに関心を持つ人を増やすための活動です。
今回の学術大会では、会員の中でtwitter改めXを活用する“twitter民”(“X民”?)を「大会公式アンバサダー」として任命し、自由闊達な広報活動を行っていただきました。予め演者の許可を得た講演について講演スライドを撮影し、講演内容を要約して、投稿していただく任務です。
お手本は日本循環器学会学術集会のtwitter協力員です。学術大会を盛り上げるだけでなく、緩和医療が専門ではないけれども知識を習得しておきたい方、勉強に十分な時間を取れない方などに向けた“タイムパフォーマンス重視の学び”となりました。
めまぐるしく変化中の領域、EBMを得てさらなる一歩
緩和医療・緩和ケアの分野は、がん治療の進歩や高齢社会の加速に伴い、めまぐるしく変化しています。ナラティブで個別性や経験則が中心だったこの分野に、臨床研究を経て構築・蓄積されたエビデンスに基づく科学的な視点が加わり、国際水準の緩和医療に向けさらなる一歩を踏み出そうとしています。
これからも「日本緩和医療学会って、なんかおもろいことしてるやん」と思っていただける活動を続けていければと思っています。
今回の大会ではオンデマンド配信を2023年8月31日まで行っています。何から視聴したら良いか迷う方や、参加登録できなかった方、そもそも緩和医療学会ってどんなことをしているのだろうと思った方は、是非「#jspm2023」で検索してみてください。
次年度の学術大会は日本サイコオンコロジー学会との合同で、2024年6月14-15日の2日間開催されます。来年も神戸の地で、一人でも多くの先生方にご参加いただけますよう、お待ちしております。
国立病院機構大阪医療センター 緩和ケア内科 医師
緩和医療専門医/医学博士