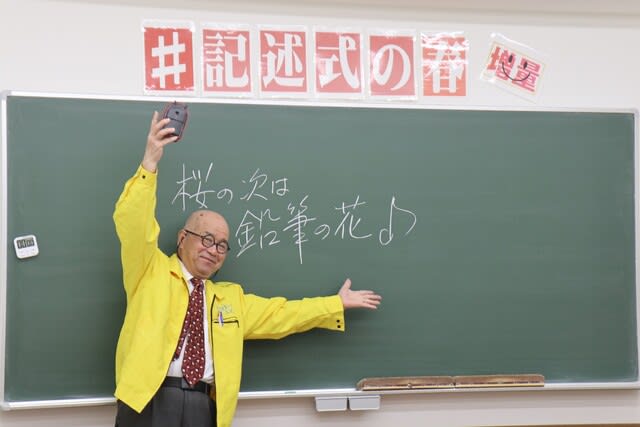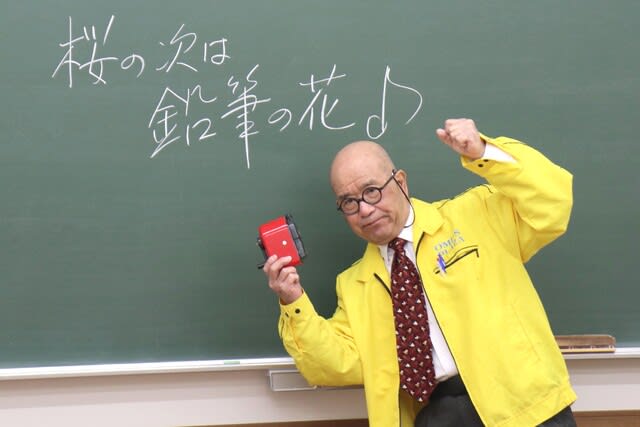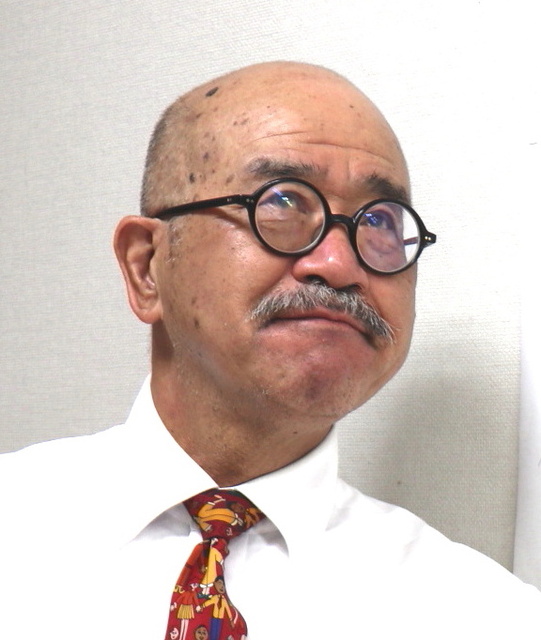世界のニュースから。
*いきなり注意を。
「入試では時事問題が出題されることが多いから、ニュースには注意しておきなさい。新聞の切り抜きなどを作っておくと、入試に役立ちます」
などと言われることがありますが、そんな事実はありません。
後になってから「あぁ、この問題は、あのニュースがきっかけになって…」などと言うだけです。問題そのものは、ニュースから出ているわけじゃない。
今春の滋賀県、社会科の地理で、「アメリカ合衆国の自動車工業が、デトロイトで」というのが出ていて、「おお。トランプ大統領がアメリカの工業を復活させると言っていたなあ…」などと。もともと地理で普通に勉強する内容だから、特別な時事問題でもないですよね。
時事問題などは特に気にせず、教科書、「新研究」にのっていることをマスターしておけばOKです。小ワザに走らず、真正面からオーソドックスに。
ついでに。
アメリカの大統領・トラ男(匿名希望。なお、音声は変えてあります)に言っておくと、関税の役割と影響をちゃんと勉強してなかったのですね。今からでも遅くないから…遅いけど…歴史の江戸時代のラストあたりと、公民の経済の勉強をしなさい。あ。公民の政治編の「三権分立」も勉強しなさい。
大統領は「行政権」ですから、めったやたらに大統領令に署名したらダメ。法令を決めるのは国会(議会)だよ。モンテスキュー、知ってますか…「知らない!」…そうですか。
ローマ教皇が御逝去。
フランシスコ教皇は、イエズス会に所属していたとのこと。ローマ・カトリックの総本山には、そういう政党や流派のようなものがあるのだなあ。
生徒諸君へ。
マニアックにならんように気をつけつつ、イエズス会の勉強をします。
1,虐げられていた民衆を支えたキリスト教は、やがてローマ帝国の国教になって、政治権力と結びついた。
2,教会は税金を取り立てるなどの特権を持ち、一部の神父は富をたくわえた。
3,アラビア地方でイスラム教が誕生し、急速に勢力を広げて、聖地・エルサレムも支配するようになった。キリスト教徒は、エルサレムへの巡礼に行けなくなった。困ったぞ。
4,ローマ教皇が、聖地を奪い返す戦いを呼びかけ、ヨーロッパ諸国からキリスト教諸国の軍隊・十字軍が中東方面に出撃したが、失敗を繰り返した。
5,ドイツで、マルティン・ルターが「教会が免罪符を販売して金儲けをするのはおかしいぞ!」と抗議(プロテスト)をして、宗教改革が始まった。これにカルヴァンが続いた。
6,各地で対立や戦争がおこったが、古いキリスト教・カトリックよりも、新しいキリスト教・プロテスタントが優勢になった。
ドイツ、フランス、イギリス、オランダはプロテスタントが多く、アメリカ合衆国もプロテスタントが多い。
カトリック系が多いのは、イタリア、スペイン、ポルトガル、南米諸国など。
7,古いカトリックの側では、反省が生まれて、質素な生活や厳しい戒律を唱えるグループ・イエズス会が誕生した。
8,イエズス会のメンバーのフランシスコ・ザビエルは、アジア方面へ布教をするためにインドへ、そして1549年には鹿児島へ来て、日本で布教活動をした。
この後は、豊臣秀吉の弾圧、島原天草一揆、江戸幕府の鎖国、踏み絵へと歴史の勉強がすすみます。
備考① フランシスコ・ザビエルは教科書に登場していますが、このたび亡くなったローマ教皇もフランシスコ教皇です。
備考② 神父はカトリック教会の司祭、牧師はプロテスタント教会の信者の指導をする人。
備考③ イエズス会は、上智大学を運営している。
滋賀県では、光泉カトリック高校がカトリック系、近江兄弟社はプロテスタント系。
京都府では、ノートルダム女学院がカトリック系、同志社、平安女学院がプロテスタント系です。
写真のラストのあたりは、金沢市。
道路のマンホールの蓋(ふた)が、はて、何だろう。
兼六園に行ったら、池のほとりに実物がありました。
琴の糸を張る器具です。さすが加賀百万石。マンホールの蓋も風流です。
石灯籠から、雅な琴の音が響いてきそうです。
*徽軫灯籠(ことじ とうろう)
兼六園のシンボルとしてよく知られ、観光写真でも度々登場する2本脚の灯籠。
水面を照らすための雪見灯籠が変化したものです。形が楽器の琴の糸を支え、音を調整する琴柱(ことじ)に似ているため、その名が付いたと言われています。
二股の脚は元々同じ長さでしたが、何かの原因で折れてしまい、石の上に片脚を乗せてバランスを保っています。
手前に架かる虹橋と傍らのモミジの古木との三位一体となった風景はとても絵になり、多くの観光客がここで記念撮影を行っています。
(金沢トラベルガイド から引用しました)
そういえば、理科の問題で
図のことじをAの方向に動かすと、音はどうなりますか。
ア 高くなる。 イ 変わらない。 ウ 低くなる。
というのがあって、生徒が「コトジって何ですか?」と。ことじで、弦の長さを調節して、音の高さを変えるのです。
まあ、琴なんかは今では珍しいから、知らないですよね。私の家には琴があって、鳴らして遊んで、ものすごく叱られましたー。乱暴に鳴らすと、弦が切れるのです。すみません。