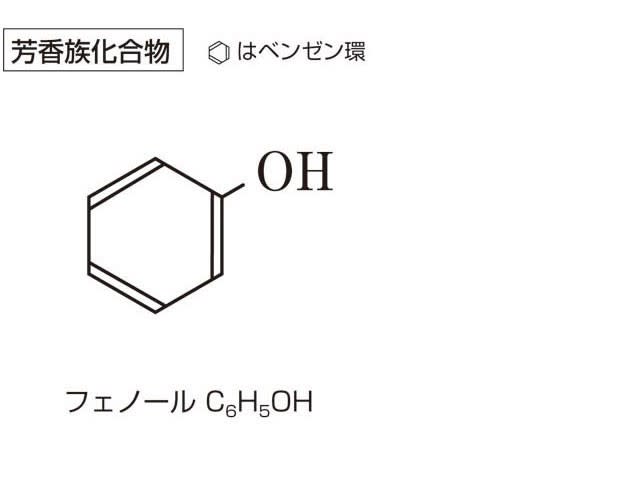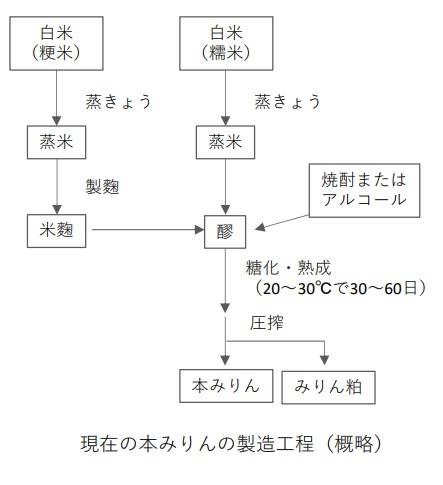祝日の昨日の朝は、リハビリがてらのジョグ/ウォークで上野公園へ。
噴水の広場のところで、こんなイベントをやっていました。

ジャパンホットカクテルフェア
その名の通り、ホットカクテルのイベントのようなのですが、会場内には、他のイベントでも出るようなフードの屋台がずらりと並んでいます。

その中にはビールやサワーを売る店もあって、「どこがホットカクテル?」という感じだったのですが、中央ではありますがひっそり?とホットカクテルのプレハブブースが2つ並んでいました。

売られていたのは20種類(うち5種類はノンアルコール)のホットカクテル。
アルコール入りの方を列挙してみましょう。

1 ホットワイン
2 サングリア
3 ホットウイスキーAppleJam
4 ホットバタードラム
5 スウィートウォッカグリーンティー
6 アーモンドブロッサム
7 柚子マッコリ
8 日本酒和風だし割り
9 梅カルピス
10 芋ジンジャー

11 ブラッコア
12 ホットダージリン
13 テキーラレモネード
14 ミードコーヒー
15 ホットウイスキーSoyMilk
16特選甘酒
17サングリア(ノンアル)
18レモネード
19ココア
20ドリップコーヒー
周囲のテーブルを見てもあまりホットカクテルを飲んでいる人が少なかったこともあり、応援の意味も込め、「ホットウイスキーAppleJam」というのを頼みました。
(頼んだら10秒で出てきたので、作り置きのようです)
その名の通り、 ウイスキーにリンゴジャムと蜂蜜が入っているカクテル。
リンゴジャムには果肉が沢山入っていて、「温かくて甘くて体が暖まるなぁ!」という感じでした。
その上で思ったのは、「アルコール度数はかなり低そう」ということ。
温かいのでアルコール臭が立っているかと思いきや、全然立っていないし。
ウイスキーはBuffalo Traceというバーボンで、瓶を見ると45度とありましたが、カクテルの度数は体感でビールと同じかそれよりも低い感じ。
ホットワインの度数も5~7度と言いますから、そんな感じなのでしょうか。
作り置きを保温している分、アルコールも飛ぶのかな。
でもこのくらいであれば、カップ1杯(1合くらい)飲んでも酔っぱらう感もないし、お散歩中のホッと一息に良いですね。
「スマートドリンク」の良い例になるかもしれません。
他のカクテルも気になるところですが、それはまた今度。
★★お酒に関する諸事万端のご相談を承っております(商品企画/情報提供/寄稿等)★★
酒ブログランキングに再度エントリーしました。
 ←クリック頂けるとうれしいです。
←クリック頂けるとうれしいです。
応援のクリックを↑↑↑↑↑

【アルバイト・契約社員募集中!】
(1)飲食部門(フロアスタッフ兼新規開店企画)
(2)酒類営業部門(倉庫管理兼営業企画)
(3)酒類営業部門(通販管理)
日時・時間はご相談。正社員登用もあり。男女問いません。詳細は当社HPまで。